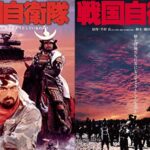2019年1月17日にアマゾンプライムビデオで動画配信の始まった『MAGI(マギ)』。
潤沢な資金と、それに負けない骨太なシナリオは歴史ファンの心を掴んで離さず、私も思わず熱が入ってしまい、一回一回のレビューがかなり長くなってしまいました。
そこで今回は、内容を端的にマトメた総評をお送りしたいと思います。
もしもまだ同作をご覧になられていない方は、ご検討を。
アマゾンプライムに加入している方で、戦国ファンでしたら、必ずやご納得されることでしょう。
シーズン1の主な舞台となるのは、天正遣欧少年使節の活躍した欧州。
精緻な時代考証と、クレームなど気にしちゃいない!といった殺伐な描写は、リアルな戦国を追い求める迫力に満ちております。
では、総評へ。
高難易度、追試なし 本作は鬼教官
初めに包み隠さず申し上げておきます。
本作のネックとなりうる点は、歴史的難易度がかなり高いことです。
日本史知識:中学生レベルが最低でも欲しい
世界史知識:高校生レベルが最低でも欲しい
特に世界史に関しては、大学入試問題になってもおかしくないほどの内容であり、しかもドラマ本編内での説明が少ないため、受験で日本史を選択された方は戸惑いを覚えるかもしれません。
それを補うように、大河ドラマでの「紀行」に当たるエピソードも用意されております。
併せて何らかの書物に目を通し、本レビューで取り上げた関連作品でもご覧いただければかなり理解が深まる――そんなレベルで仕上がっています。
一番重要な歴史は、宗教改革関連ですね。
とにかく本作は、その流れを把握しておくと、よりいっそう味わいが深まる。
そんな特性があります。
関連書籍をバリバリ読んでやるぞ、という気合いで挑みましょう。
配信特化型
本作は、配信というフォーマットに特化したスタイルです。
タブレット端末で見ながら
【停止】
【巻き戻し】
などを駆使して、わからないところは何度でもジッと見るのが良さそうです。
作りても、だからこそ高難易度に設定できるのでしょう。
一度ではなく、複数回の視聴が前提として作られている部分も感じます。
日本のテレビ番組は【ながら見】を前提としているようで、歴史作品の難易度低下が著しい。
それとは真逆の、ビシバシと脳みそをフル回転させろと訴えてくる本作。
新らしい時代を感じます。
日本人がターゲット・オーディエンスではない
本作は、全世界に向けて配信されております。
これも大きな特徴です。
対象とする視聴者は世界。
日本人が考える【クールジャパン】も【おもてなし】も、最初からどうでもよい。
むしろ、日本人が発信したい日本の歴史なんて正直どうでもエエわ!という意識すら感じるのですね。
このことに苛立ちを覚え、怒りをぶつける人がいることはレビューからも伝わって来ます。
織田信長がカッコイイ!
とか
忍者と侍がクール!
とか
世界の人が知りたいのは、そんな話じゃないんですね。
「こういう話は日本人には受け入れられない!」と言われたところで、配信側としても「わかりました。では、さようなら」で終わり。大河と違ってそういうものです。
ただし、日本人の目を意識していないわけではない。
以下の記事にありますように、以前、BBCの関ヶ原ドラマをレビューしました。
-

英国人から見た家康と関ヶ原の戦い!BBC版『ウォリアーズ』は一見の価値あり
続きを見る
全体的に見るとレベルが高いものではありましたが、初歩的な考証ミスも目立ったものです。
間違ったというよりも、イギリス人向けのサービスや、どうせ気づかれないだろうという手抜きですね。
同じ番組のナポレオンあたりと比べると、ちょっと苦笑いしてしまうレベルのものでした。
それと比較すると、本作の考証はかなりシッカリしています。
ミスがないわけではありません。
全体のレベルがここまであがったものかと驚かされたです。
制作サイドは、日本人の気持ちを慰撫するつもりはない。
ただし、日本人が見てあきらかにおかしい考証ミスは避ける。
そんな毅然とした態度が、そこにはあるのです。
「クール・ジャパン」は国内外で異なる
本作は、日本人が発信したいクールジャパンではなく、海外が見たいクールジャパンを追求しています。
ここで思い出したのが、タランティーノの作品です。
彼の追及するクールジャパンは、『キル・ビル』に濃縮されておりました。
いわば、70年代テイストですね。
本作からは、そんなタランティーノあたりが涎を垂らしそうな、殺伐としたテイストがみっちりと感じられました。
血しぶき!
キリシタン弾圧!
日本刀アクション!
うぇーい!!
そういう映像や演出テイストもそうなのですが、シナリオの部分がとても70年代だなと思ったんですねえ。
歴史は、人間の精神性が動かすのだ、人はそんな巨悪に踏み潰されるだけに過ぎない——。
そんな殺伐としていて虚しい気持ちを感じたのです。
コレって、太平洋戦争体験者の考え方も根底にあると私は感じています。
歴史の流れの中、人の命が踏み潰され、一体、日本人とは何だったのかと、暗い気持ちで歴史や社会を見つめていた層の感覚だと思えるのです。
戦後の一時期、GHQは戦争を引き起こした原因に【武士道讃美】があると考え、時代モノを禁止処分にしました。
それが終わると、武士道って一体なんだったんだ、実は残酷だったはずだという、そんな作品が出てくるようになりました。
現在まで人気と知名度があるのが、以下の作品です。
『シグルイ』原作である南條範夫『駿河城御前試合』。
『バジリスク』原作である山田風太郎『甲賀忍法帖』。
『Y十M』原作である同『魔界転生』。
あまりに残酷であるとか、暗い想念に満ちているとか、性描写とか……そういう理由で、どちらかといえばB級扱いされております。
わかりやすく言えば、大河ドラマの原作には絶対に選ばれない。
戦争経験があればこそ、日本の歴史のよいところを見たい――そう願った司馬遼太郎の世界観のほうが日本人には好まれました。
これは、現在に至るまでそうですね。
ただ、司馬遼太郎的な世界観って『実はガラパゴス的な人気だったのだなぁ』と本作を見て思い知りました。
むしろ海外がクールジャパンとして求めているのは、山田風太郎原作であるとか、深作欣二監督であるとか。そういうテイストなのではないのか?
脚本家が鎌田敏夫氏であることにも、ストンと落ちたものです。
例えば『戦国自衛隊』も鎌田氏脚本の作品です。
-

信玄の恐ろしさを堪能したいなら映画『戦国自衛隊』を見よ!その迫力いまだ衰えず
続きを見る
歴史を扱っていながらのSFには違いない。
されど、あの映像の中には【人間の精神性がどこまで荒れ果てるのか】という凄まじさを描く覚悟がありました。
ナルホド、ああいう世界観か……そこに行きたいのか。
そう納得できたものです。
70年代にあった、戦中派の苦悩がみっちりと詰まった、歴史を見る冷たい目。
それこそが本作にはあります。
歴史劇のトレンドは「翻弄される人々の生き方」
何度も繰り返しているように、本作は日本人が見たいドラマではなく、世界的な歴史モノの流行を取り入れています。
70年代のB級日本歴史モノは、実はこの世界的な流れと合致する部分があります。
日本の歴史ものの映画タイトルに、特徴があることにお気づきですか?
それは名の知れた人物の名前を、強引なまでに入れてくることです。
顕著なのが、ヒトラーとマリー・アントワネットあたりですね。
『ヒトラーの忘れもの』にせよ『マリー・アントワネットに別れを告げて』にせよ、元々のタイトルに人名は入っていません。
特にヒトラーはナチスがらみだと、ともかく入れ込むべし!入れ込むべし! という傾向にあります。
まったくヒトラーが出てこなくても、そりゃ不思議でも何でもないという……。
それが日本の時代モノですと、ともかく英雄を出したがる。
英雄がいかにして日本の歴史を切り拓いたのか、そういう物語にしたい。
未だにそれはあるはずです。
ところが、世界的には英雄ではなく、むしろ歴史に埋もれていたはずの庶民、女性、兵士の目線から見たものが増えつつあります。
戦争画で例示すると、こう。

デラウェア川を渡るワシントン/wikipediaより引用
この絵は、アメリカ独立戦争の際のワシントンを描いたもの。
英雄であるワシントンを讃えています。
それが、第一次世界大戦ともなると、兵士たちの苦闘を描くようになりました。

Canadian_Gunners_in_the_Mud/wikipediaより引用
英雄がカッコよく戦場を駆け回り率いる。
そんな話はちょっと古い。
海外の作家ですと、架空の軍人が主人公で、英雄は脇役であるものが多いのです。
※イギリスでも屈指の名君アルフレッド大王の時代なのに、一人の戦士が主役である『ラスト・キングダム(→link)』
本作が日本史を取り上げる上で、三英傑ではなく、彼らに翻弄される少年たちを描いた理由には、こうしたトレンドもあると思えます。
歴史という荒波に翻弄される人々。それを見たい、それが世界的な流れなのです。
輝く少年たち、そしてキャスト
本作のキャスティングはおそろしいものがあります。
吉川晃司さんの信長と、緒形直人さんの秀吉は……よくもこんな絶妙なことをやったなとのたうち回りたくなるほど素晴らしい!
もう悔しくてくやしくてなりません!!
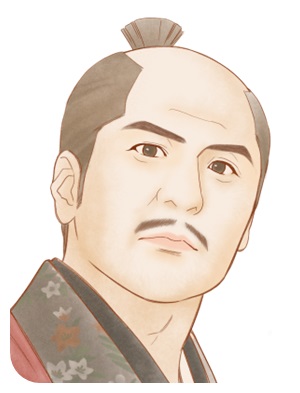

そして四少年とドラードを演じられた俳優たちも「彼らは世界に羽ばたいていくのだろうなぁ」とため息をついてしまいます。
伊東マンショの野村周平さん。
彼のまなざしが忘れられないような、そんなメインビジュアルです。

この眼力こそ、彼を起用した理由だろうと思えます。
意志の強さがうかがえるまなざしは、本当に忘れられない、心をつかまれるものがあります。この目こそが、彼にもとめられているものです。
中浦ジュリアンの森永悠希さん。
彼の優しげなまなざしと、声音。本当にジュリアンは、優しさにあふれた少年です。

イメージ的に、史実としても、もっとも殉教者の清らかさがないといけない役。その役を果たしています!
原マルティノの井ノ脇海さん。
マルティノは難しい役のはずです。ラテン語から英語まで、彼は三カ国語でスラスラとセリフをいう必要がある。しかも、流暢でなければならない。それだけでも大変なはず。
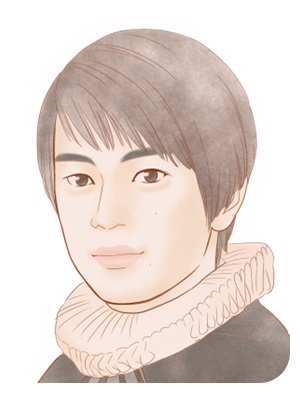
しかも、マルティノはいついかなる時でも、知性あふれるふるまいが求められています。その高いハードルを飛び越えたのです。これぞ世界に羽ばたく逸材だ……!
緒形敦さん。
彼が大河ではなく、本作に出たということは、おそろしいことだと思うのです。
祖父(緒形拳さん)、父(緒形直人さん)に続いて、敦さんが大河に出たならば、どれほどフィーバーになるか想像がつくというもの。
そんな彼が、こちらを選んだ。これはおそろしいことです。
彼の血筋については、これ以上語りますまい。
ミゲルも、これまた難しい役。
彼は信仰心だけではなく、そこから目を背けるところを滲ませねばならない。しかも、それは彼の邪悪さゆえではなく、正義感も背後にあるのです。

ミゲルは正義感にあふれた人物です。その一方で、どこか時折暗い狂気をのぞかせる。こんな難しい演技を、彼はよくこなしているのです。
ドラードの佐野岳さん。
これも繊細で大変な役です。その血統ゆえに虐げられ、悲しい思いを味わってきた。汚いところも、きれいなところも見てきた。穏やかな性格なのに、時折激昂をにじませる演技は感動的です。

海外のキャストも、世界各地からよくぞこんな人たちを集めてきたものだと感動すらしてしまいます。
全員ミスキャストがいない。これまたスゴイことです!
宗教の歴史的な意義を問う
本作のおそろしいところ。
それは、宗教の存在意義というところまで踏み込んで来たところです。
本作の日本描写がどうこう言われておりますが、むしろ狙い澄ましてブスリと突き刺すのは【宗教そのもの】であります。
本作に描かれているカトリック描写は、本当に一番突かれたくないところを狙っている、そんな気迫を感じさせました。
・奴隷制度
・人種差別
・異端者惨殺
・海外侵略
本来の教えとはほど遠く、血を流し、人々を苦しめ、踏みつけにする。
そんな残酷な行為を止めるどころか、推奨してきた勢力こそが、カトリックであると本作は喝破しきっているのです。
問い続けることこそ祈りなのだ——。
どうしてあなたたちは、すぐに答えを出そうとするのだ——。
本作で示されるこの問いかけは、宗教の存在意義にも迫りかねない、そんなおそろしいものが含まれています。
世界にあるありとあらゆる疑問、不思議なこと。
統治者が民の不満を封じるために、信じ込ませたいこと。
そういうことへの答えとして、「神がそうしたからなのです」ということにしてしまえば、丸くおさまるのです。
異議を唱える人には「異端者め!」、「信仰心が足りない!」と言えばそれで終わり。
宗教というものは、疑問を氷解させて、問い続ける人の口塞ぎをする、そんな使い方もできます。
本作にはそんな宗教関係者や権力者が、東にも西にも、数多く出没します。
そうじゃないはずだ――そう思いませんか?
本作は、マンショ、信長、ヴァリヤーノ、法皇らの口を通してそう語りかけてくるかのようです。
この歴史、権力、宗教の問題は、四百年前のことではない。今も、同じことがあるはずです。
差別。自分と意見が異なる人を排除しようと躍起になること。知識を語る相手を憎み、罵倒すること。悪を黙認することが現実だという見方。
本作は、そういうことを放置せずに問いかけてみろと、そう語りかけてくるようです。
本作は、まさに戦国時代のようなドラマだと感じました。
火縄銃が伝わってきたとき。
カトリックを教えられたとき。
西から来たものを、東の日本人がアレンジして、独自のものを生み出した。
それが歴史です。
本作も、Amazonという西から来たものを、東の日本人がアレンジして、何か新しいものを造った。
そういうダイナミズムがあります。
大河のようで、大河ではない。
これは日本史のドラマか?
そうではなく、世界史の中の日本史を描いた作品であると思うのです。
一筋縄ではいかない。
何度も何度も、この作品は何なのかと考えてしまいます。
それこそが、本作を楽しむということ。そうなのかもしれません。
おそろしい作品が誕生してしまったものです。是非、あなたの目でお確かめください!
【参考】
◆アマゾンプライムビデオ『MAGI』(→amazon)
◆公式サイト(→link)