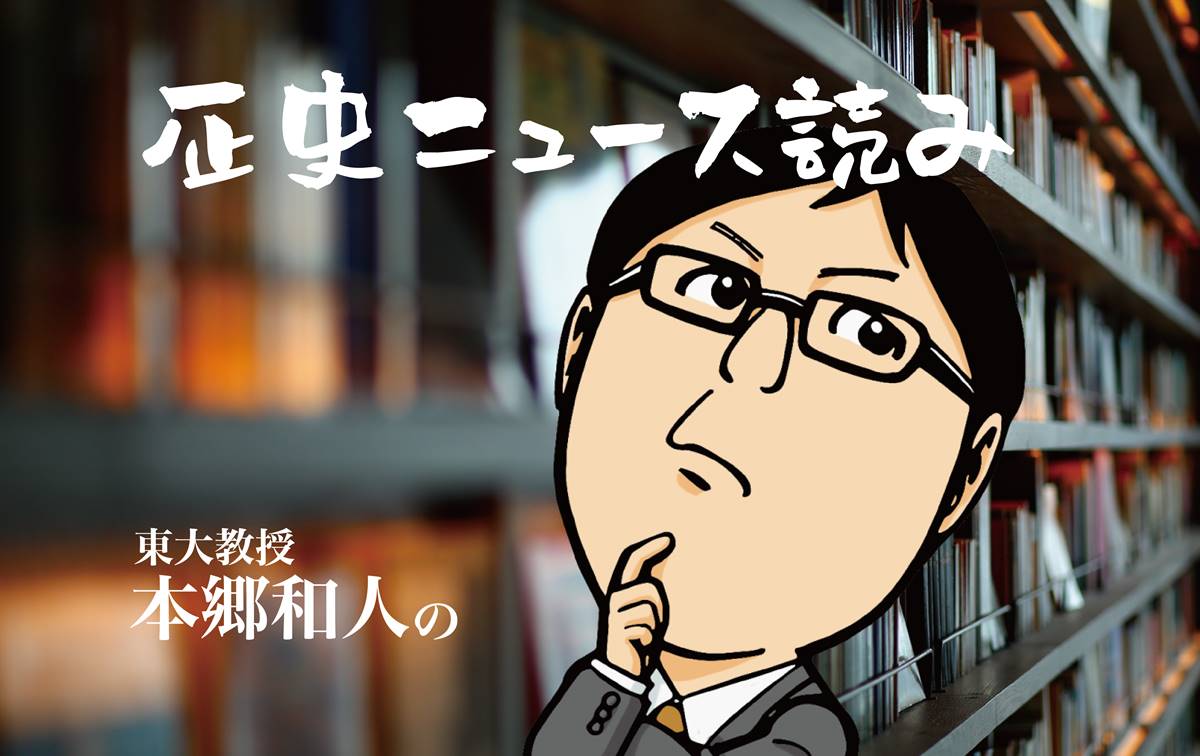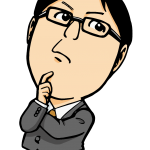日本中世史の本郷和人・東大史料編纂所教授が歴史ニュースに注目する「歴史ニュースキュレーション」。
今週のメインテーマは「鎌倉幕府の成立年……というか幕府ってそもそも何?」さらには武将たちの「肖像画」をめぐる諸問題です!
鎌倉幕府は何年に成立?
◆鎌倉幕府は何年に成立?正解を言えますか/東洋経済オンライン 6月13日(→link)
姫「あら、あなたにぴったりの記事じゃない。いつもお仕事(しよーばい)で戦国時代や江戸時代のことをしゃべってるけれど(苦笑)、一番の専門は鎌倉時代なんでしょ。説明してよ」
本郷「うーん。どう言ったら良いんだろうね。一番大事なことが分かってない記事だよね。それをあげつらっても仕方がないから、少しお話をしましょうか。どこからいこうか。そうだ、そもそも、幕府ってあったんですか? って聞かれたらどう答える?」
姫「この記事にも言うように、そりゃあ、あったんじゃないの?」
本郷「いや、北条時政や畠山重忠らの御家人たちに、『あなたは鎌倉幕府に所属しているんですよね?』って聞いたら『鎌倉幕府ってナニ?』って言われる。これホント」
姫「えええええ? どういうこと?」
本郷「幕府っていう言葉を、武士たちは知らないんだ。この言葉を使ったのは、室町時代の物知りの禅宗のお坊さん。江戸幕府の人たちは『幕府』じゃなく、『柳営』っていってるでしょ。幕府という語が一般的に広まるのは、明治になって、学術用語としてなんだ」
姫「あら、そうなの。いちいち、『鎌倉にあった武士たちの政権』というのは面倒くさいから、明治の研究者が『幕府』って言い出したのね」
本郷「そう。だから、『そもそも幕府というのは遠征中の将軍の本営をいう言葉で……』とか言い出す人の話はだいたいマユツバ。本質の分かってない人ほど、そういうことを言い出すんだね、ぼくは経験則でよく知ってます、はい」
姫「ふーん。そうか、『幕府』なんて名称はなかった。御家人たちは、幕府なんて知らない。だから『鎌倉幕府』はなかった、というわけね。でも、政権というか権力組織は厳然としてあるんじゃないの? それはまちがいないんでしょう?」
本郷「そこだ! そこが大事なんだよ。名前があって、実体が生まれるのか。実体があるから名前を付けるのか。名前が先か、実体が先か。そこが議論の分かれ目なんだな」
姫「なるほどね。天皇が『征夷大将軍』に任じたから、幕府がスタートした、というのは、名前が先だ、という考えなわけね。そうじゃないんだ、と考えるならば、それは実体が先だ、その実体はいつできたと認識するべきか。そういうふうに考えなさい、という事ね」
本郷「その通り。そこで1185年説が出てくる。全国に守護――守護はまあ武士のリーダーだね――を置くこと。それと荘園に地頭を置くこと。それを公認されたのがこの年。守護・地頭を置くことにより、幕府は政権としての実体を獲得する。そう考えるので、幕府は1185年にできた、とする。この説を支持する学者が多いんだね」
姫「なるほどねー。では、あなたは1185と1192と、どっちを支持するの?」
本郷「ぼくは実体が先で、そこに名前が付く、と考えるので、どちらも支持しないよ」
姫「え? 実体が先、名前があと、は1185年説じゃないの?」
本郷「いやいや。だって、1185年説にしたって、朝廷が認めた、という点に関しては一緒でしょ。それじゃあ、実体がいのち、ということにならないじゃない」
姫「じゃあ、いつなの?」
本郷「源頼朝が南関東を実力で制圧して、鎌倉に本拠を定めたとき。つまり1180年だね。このときすでに、鎌倉の武士政権、イコール鎌倉幕府はできていた、と考えるんだ」
姫「なるほどね。まあ、理屈としては成立するのね。で、それに賛同する人は?」
本郷「いまのところ、その説を唱えているのはぼく一人。つまり、支持者はゼロだね」
姫「なにそれ? 誰も認めてくれないんじゃダメじゃない」
本郷「まあ、仕方がないね。パイオニアはいつも孤独なんだよ」
姫「唯我独尊ね~。あきれるわ。うーん、それから例の源頼朝象なんだけれど」
本郷「ああ、神護寺さんのね。足利直義説が出ているヤツね」
姫「それについてはどう思う?」
本郷「うーん。面倒なことが2つあるんだ。1つは研究者の人間関係ね。ぼくの聞いた話では、この像の像主が誰か、というのは、既に学問的な話じゃないらしい。像主が帯びている刀がどう、衣服がどう、みたいな科学的な話ではなくなっているんだって。おれは大物研究者のAだが、足利直義説を唱えるBが気にくわないので、おれの目の黒いうちはあの像はぜったいに頼朝だ、みたいな研究者のメンツの話になっているらしい」
姫「うわあ。なまぐさいわねえ。でも、ありそうな話ねえ。面倒なこと、その2は?」
本郷「あんまり大きな声では言えないけれど、所蔵者の問題。つまり神護寺さんだよね。神護寺さんは、この像を源頼朝というならOKだけれど、足利直義というのはもってのほか! もろもろの許可は出しません! という立場なんだ。この像を使いたいメディアにとっては大問題だよね」
姫「うーん、わかるような、わからないような」
本郷「最近でいうと、高野山の成慶院がもっている長谷川等伯が描いた武田信玄像。重要文化財に指定されていて、でっぷり太った貫禄ある信玄が描かれている。あれ、信玄じゃないという説が有力なのは知ってる?」
姫「うん。知ってるわ。長谷川等伯は能登の七尾の出身だけれど、その七尾に本拠を構えていた能登の戦国大名、畠山氏の誰か、という話だったわよね」
本郷「そう。それでいまは、同じ高野山の持明院に所蔵されている、やせ形の武田晴信肖像を用いることが多い。こちらは武田菱が描かれている衣服を着ていて、まあ、晴信(剃髪後、信玄)で間違いない、というわけだね。でも、等伯の信玄像は絵画としても見事だから、博物館は借用して展示をしたい。ところが、高野山は信玄像としないならば貸し出しには応じません、掲載許可も出しません、ということみたいだね」
姫「うーん。でも、持っている方のご意向だから、仕方がないわね~」
本郷「じゃあ、最後にとっておきの話を教えてあげる。ぼくもつい一週間前に、史料編纂所の若い友人から仕入れたんだ」
姫「なに、なに?」
本郷「京都東山の六波羅蜜寺に、平清盛の木像があるでしょう?」
姫「重要文化財に指定されている,とても写実的な木像よね」
本郷「あれ、清盛じゃない、という論文が出たんだ。」
姫「え! 清盛じゃないの? じゃあ、だれなの?」
本郷「浄海という往生人(おうじょうにん)」
姫「え? 清盛は仁安3(1168)年、51歳で出家して浄海と名乗るんでしょう?」
本郷「うん。平家ゆかりの六波羅に建つ六波羅蜜寺に浄海という人物の木像があった。だからこれは清盛だ、ということだったんだね」
姫「ふんふん」
本郷「だけど、当時は極楽往生した、と噂される人の伝記を書いたり、像を造ったりして、人々が往生を願った、という風潮があった。だから、あの像は往生を遂げた浄海という人物の像ではあるけれど、清盛とは何の関係もない、というのがその論文の主張なんだ」
姫「六波羅蜜寺さんは、どういう反応?」
本郷「もう、カンカンでね。こんなばかげた論文を書いた者には謝罪を求める、という事みたいだよ。さあ、今後どうなるんだろうね」