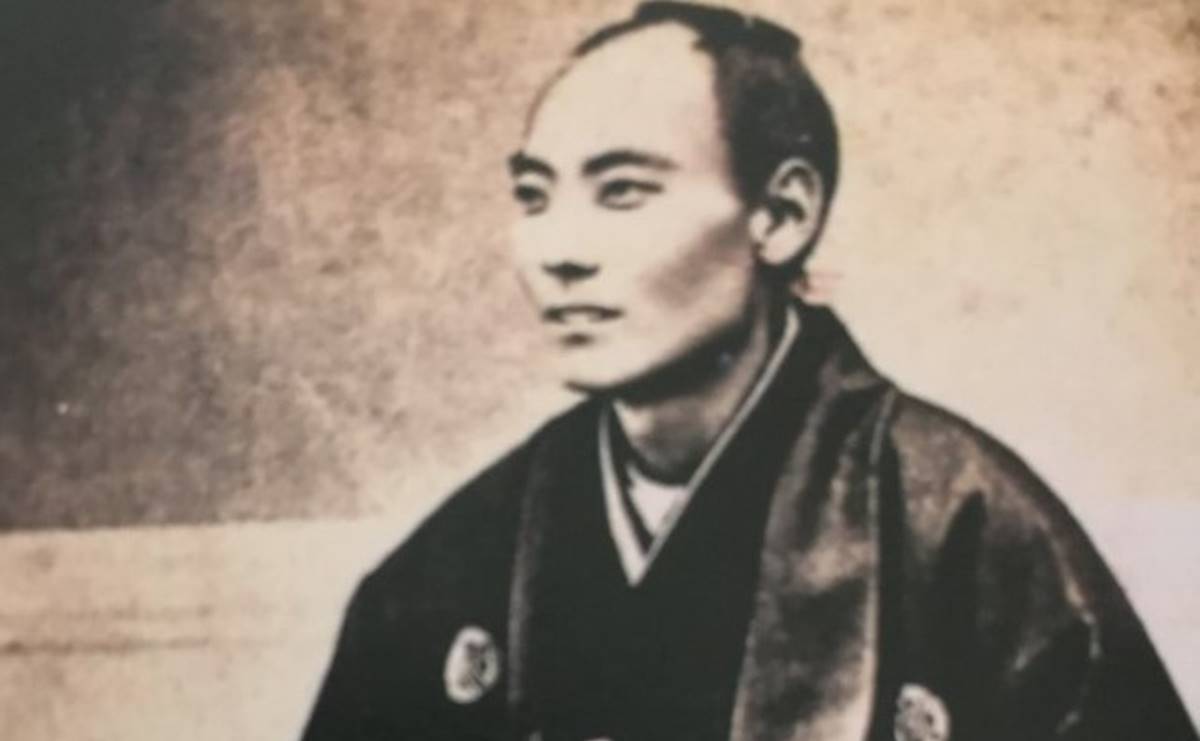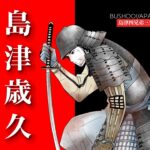大河ドラマ『西郷どん』で、突然の切腹により命を断った赤山靭負。
このとき、首を落とす介錯人のお願いに来たのが、赤山の弟・桂久武(かつらひさたけ)であり、劇中で同役を演じていたのはお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんでした。
『初の大河出演で、いい役を貰ったなぁ』
余計なお世話ながらそう思ったのは、この桂久武という人物が名門の出でありながら西郷と共に命を落とす、劇的な人生を送っているからです。
一般的な幕末史にはあまり名を見せない。
されど彼もまた、熱き薩摩藩士として、1877年西南戦争にて最期を迎えています。
1830年7月4日(天保元年5月28日)はその生誕日。
一体どんな人物で、どんな一生を送ったのか、桂久武の生涯を振り返ってみましょう。
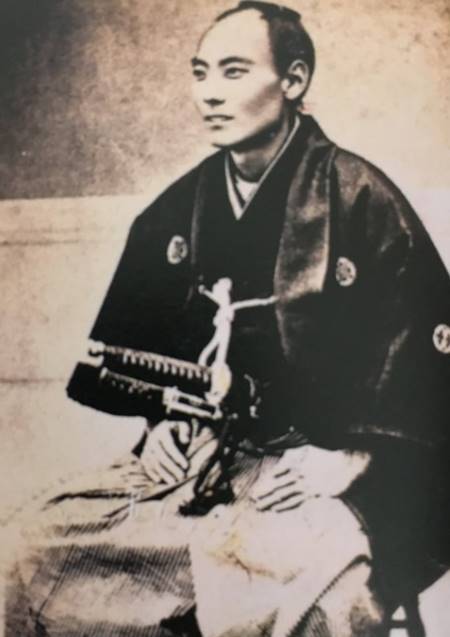
桂久武/wikipediaより引用
日置島津家の兄弟
前述の通り、桂久武は、赤山靭負の弟です。
彼らは戦国時代の島津四兄弟・島津歳久を祖先とする名門・日置島津家の出身。
-

薩摩で戦の神と称される戦国武将・島津歳久の生涯~秀吉に矢を放ち最後まで抵抗
続きを見る
久武は天保元年(1830年)、当主・久風の五男として誕生しました。
長男:島津久徴(ひさなる・筆頭家老)
二男:赤山靭負(ゆきえ・お由羅騒動で切腹)
四男:田尻務(つかさ・霧島神宮初代宮司)
五男:桂久武(家老で西郷の盟友/西南戦争・城山の戦いで戦死)
同家では三男が夭折しており、四兄弟が成人しております。
日置島津家の兄弟は、長男の久徴をのぞいて、それぞれが養子に出されました。
久武は桂久徴の養子です。
しかし日置島津家の兄弟は、全員が斉彬派に属したため、お由羅騒動では処罰対象となってしまいます。

島津斉彬/wikipediaより引用
前述の通り赤山靭負は切腹に処せられました。
同じ島津斉彬派の西郷や大久保とは大きな身分差もあり、ドラマのように幼い頃から密接な関係は築けないと推察しますが、実際、二人は時代が進むに連れて親しい間柄になっていくのでした。
西郷の親友となった桂久武
名門の御曹司である久武は、元々、造士館演武係方を務めていました。
弓術はかなりの腕前を誇っていたのです。
しかし、そんな順調な人生も島津斉彬の死(1858年)によって暗転します。
斉彬派だった久武は文久元年(1861年)、左遷同様に奄美大島へ。

奄美大島
大島守衛方・銅鉱山方という、島流しよりややマシな程度の役目に就任します。
これを機に、西郷との距離が一気に縮まるわけで、そこに至るまでの西郷の道筋も簡単に説明しておきましょう。
西郷は、1858年から始まった【安政の大獄】で、幕府から追われる身となった勤王の僧・月照を連れて、薩摩まで逃げ帰りました。
この月照、薩摩にとっては非常に厄介な存在でありまして。
万が一、匿っていたのがバレたら、安政の大獄を断行する幕府(井伊直弼)にどんな難癖をつけられるかわからない。
かと言って、表立って殺してしまうのも、薩摩の非情な決断が世に知られて、具合が悪い。
そこで藩が命じたのは「暗黙の了解」による殺害命令――他ならぬ西郷が月照を殺すこととなったのです。
西郷は悲観し、彼を殺すぐらいなら、と月照と共に錦江湾へ入水。
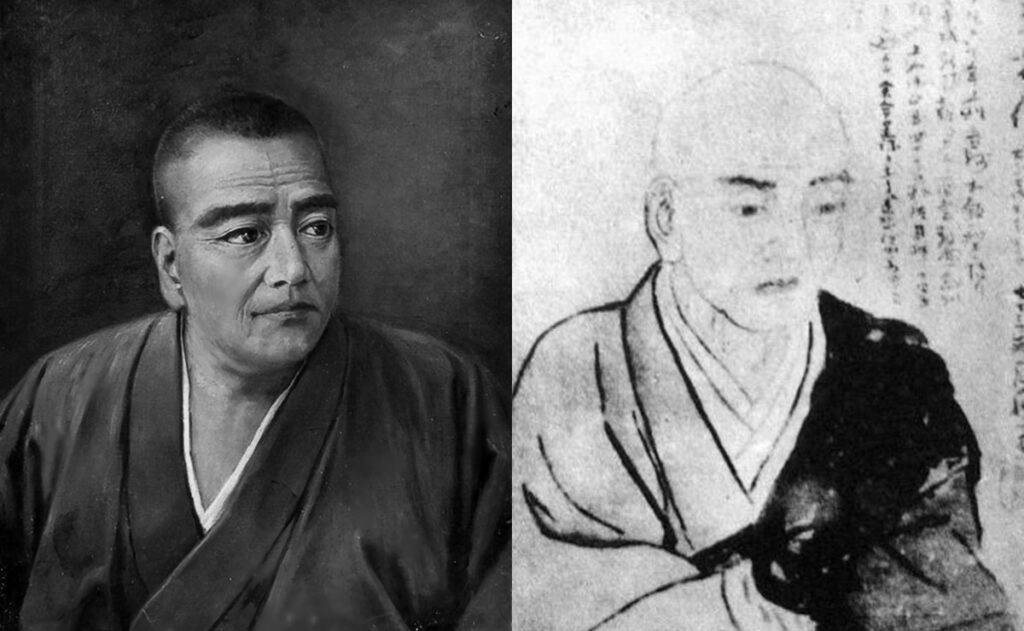
月照(右)と西郷隆盛/wikipediaより引用
結果、自分だけが助かってしまいます。
そして、薩摩藩では「(西郷は)死亡した」と処理して、奄美大島への流刑とするのでした。
期せずして、奄美大島で再会した西郷と久武。
同じ斉彬派であった二人が、自然に恵まれた奄美の青い海を見つめながら、将来や政治を語り合ったであろう時間は、かけがえのないものであったことでしょう。
ここで二人は親友とも呼べる間柄となるのでした。
※続きは【次のページへ】をclick!