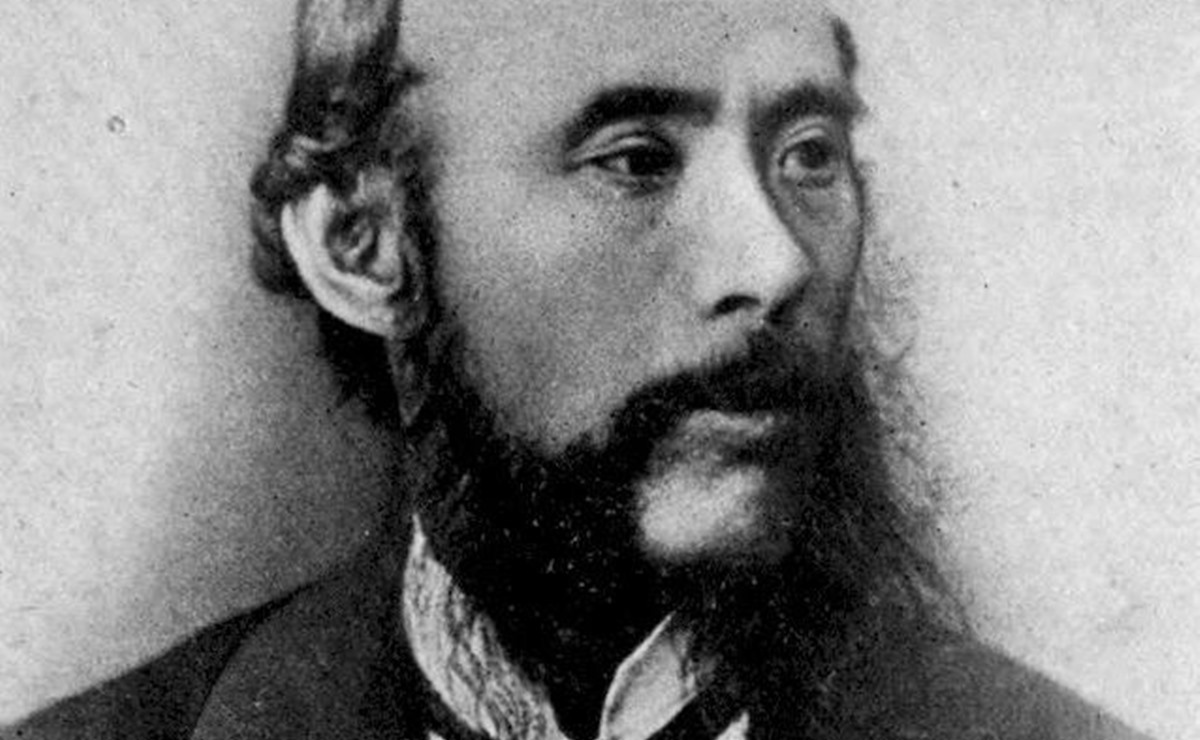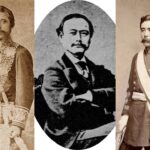明治11年(1878年)5月14日は大久保利通の命日です。
西郷隆盛、木戸孝允と並び、「維新三傑」と称される幕末維新の立役者ですが、近年の大河ドラマはじめ他のエンタメ分野でも割を食っているように思えます。
大河ドラマ『西郷どん』では【西南戦争】へ向かう過程で幼稚なイジメじみたことをして西郷隆盛を追い詰めたかと思えば、2021年『青天を衝け』では渋沢栄一をネチネチといじめる器の小さい政治家という印象。
一体なぜ、そんな描き方をされてしまうのか?
華々しく散った西郷が悲劇の英雄として崇敬されるのに対し、生き残って明治政府を立ち上げた大久保は計算高い人間だ――そんなバイアスがかけられやすい状況も影響しているのでしょう。
本稿では、そうしたフィクションでの印象をできるだけ横におきながら、大久保利通の生涯を辿ってみたいと思います。

大久保利通/wikipediaより引用
加治屋町郷中の秀才
文政13年8月10日(1830年9月26日)、薩摩国鹿児島城下高麗町に住む薩摩藩士・大久保利世と福の夫妻に長男が生まれました。
幼名は正袈裟(しょうけさ)とされ、同年同月に長州藩では吉田寅次郎(後の松陰)が生まれています。
加治屋町に越したため、彼は加治屋町郷中に入りました。
郷中とは薩摩藩の少年教育制度のこと。
加治屋町が名高いのは、以下のように、歴史に名を残した者たちが多く輩出したためとされます。
大久保利通
西郷隆盛
西郷従道
大山巌
村田新八
黒木為楨
東郷平八郎
山本権兵衛
明治維新だけでなく、日清・日露戦争で活躍した名将まで輩出した、歴史的な土地と言えるでしょう。
司馬遼太郎は鹿児島県の鍛冶屋町を指して「一町内で明治維新をやったようなもの」と評した程ですが、土佐出身の切れ者である陸奥宗光からすれば、こうなります。

陸奥宗光/wikipediaより引用
「薩長の人に非ざれば殆ど人間に非ざる者のごとし」
その是非は後述するとして、鹿児島城下に熱気溢れる少年たちがいたことは事実。
大久保は、その中で身体頑健でもなく、薩摩藩士の自顕流は習得できなかったとされています(西郷隆盛も怪我のため剣術は挫折)。
その代わりに大久保は柔術を身につけ、指だけで畳を回す「畳踊り」なる宴会芸ができたとか。
※以下は薩摩武勇伝の関連記事となります
-

とても映像化できない薩摩藩士たちのトンデモ武勇伝!大久保 従道 川路 黒田
続きを見る
フィクションでのキャラクター付けもあってか、大久保は「冷静で学問ができる」という個性が強調されがちです。
ただし、薩摩藩士には共通する特性があります。
郷中教育は体力訓練や剣術だけでなく、漢籍教養を学ぶカリキュラムも充実。
何よりも、少年期からチームワークを身につけています。
忠義に篤く、教養にあふれ、団結力がある――彼らはそんな特性を身につけてゆき、その様はロシア人から「極東のスパルタ」と評されたほどでした。
【精忠組】を率いて斉彬の目にかなう
天保15年(1844年)に元服した大久保は、正助(しょうすけ)と名乗り、弘化3年(1846年)には藩に出仕。
何度か名を変えていますが、本稿は以下「利通」とします。
嘉永3年(1850年)、藩主をめぐる御家騒動【お由羅騒動(高崎崩れ)】が勃発。
このとき父の大久保「利世は喜界島へ流され、利通も連座で罷免されてしまいます。
ただでさえ下級藩士である大久保家に、厳しい生活が待ち受けていました。
まだ20歳の利通は、父の無事を願い神社へ欠かさず日参し、借金をしてでも生きていく道を模索せねばなりません。
時代的には、この辺りから、幕末政治闘争の幕が開きます。
水戸徳川家の斉昭、福井藩の松平春嶽、宇和島藩の伊達宗城らは、島津斉彬を薩摩藩主に押し上げるべく動き、彼らは老中・阿部正弘までお動かし、ついに嘉永4年(1851年)、斉彬が第11代藩主の座に就任。

島津斉彬/wikipediaより引用
これにより、多くの藩士たちが復帰を果たし、嘉永6年(1853年)5月、大久保利通も復職となりました。
そしてこの頃から、利通は西郷隆盛と共に幕末薩摩藩を動かす【精忠組】の領袖となります。
激動の時代に理想な政治を追い求めた薩摩隼人たち。
しかし、安政5年7月16日(1858年8月24日)、理想の名君である斉彬は急死を遂げてしまうのです――と、美化してまとめたくなりますが、少し冷静になってみましょう。
何事にも開明的であった斉彬は、確かにこの時代にあって優秀と判断できるのかもしれません。
しかし同時に彼は、思わぬタイミングで逝去してしまったためか、ロマンを込めて過大評価され、反対に弟の島津久光は絵に描いたような馬鹿殿扱いをされる傾向があります。
そこは注意して振り返る必要があるのではないでしょうか。
※続きは【次のページへ】をclick!