こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【藤原彰子の生涯】
をクリックお願いします。
不遇な女性のシェルターだった?
当時は「高貴な身分の女性が宮仕えに出るのは好ましくない」とされていた時代。
伊周も「今は帝や太政大臣の娘でも出仕するようになっているが、私の娘は決して面目を潰さないように」という遺言を残していました。
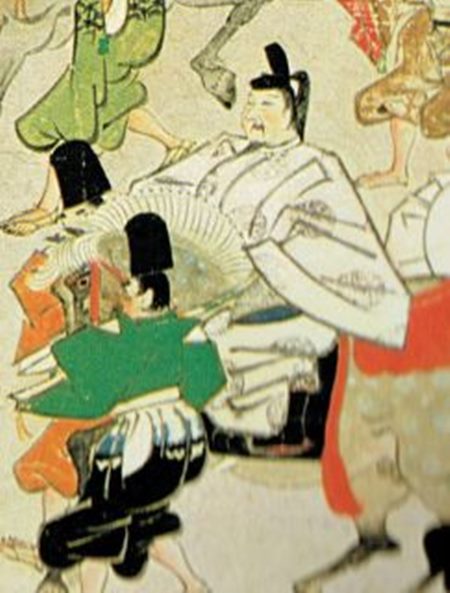
藤原伊周/wikipediaより引用
しかし、もはや敵無しの道長や彰子の意向には抗いきれません。
伊周の次女は寛弘七年(1010年)頃に出仕して「師殿の御方」と称される女房になると、その後は「周子」と呼ばれ、寛仁二年(1018年)には従五位下の位を受けています。
また、伊周の孫にあたる娘も彰子に仕え、彼女は「中将三位」と呼ばれました。そこには一条天皇の意向もあったとされます。
他にも、花山法皇の皇女や、清少納言の娘、あるいは紫式部の娘・大弐三位や、和泉式部の娘・小式部内侍など彰子の元にいました。
いかがでしょう?
こうした状況は一見すると「勝者が敗者を召し出して意地悪をした」ように見えなくもありません。
特に伊周の娘や孫たちの点だけ見ると、道長と彰子は「なんて傲慢な父娘なんだろう」という印象を持たれる可能性もあります。
しかし、これは完全に私見なのですが。
「師殿の御方」がきちんと叙位されていることや、花山法皇の皇女などいわゆる「訳アリ」な女性もいたことを考えると、「不遇な女性のシェルター」という側面もあったのではないでしょうか。
道長はともかく、彰子には女房たちへの気配りがあったように感じてなりません。
頼通が摂政となり姉弟で政治を進める
中宮としての役目を無事に果たし、順風満帆かに見えた藤原彰子。
ところが「禍福はあざなえる縄の如し」とはよくいったもので、次男の敦良親王を産んだ2年後の寛弘八年(1011年)5月、一条天皇が病に倒れると、翌月には崩御という悲しみを味わいます。
倒れた時点で一条天皇は、第一皇子の敦康親王を皇太子にする望みを捨てていませんでした。
前述の通り、その実母は藤原定子です。
彰子も前々からその意向を聞いていたのではないかと思われます。
しかし現実は、一条天皇の思い通りになるものではありません。
蔵人頭(天皇の秘書官長)を長年務めていた藤原行成に説得されると、一条天皇は敦康親王の立太子を諦めたといいます。
行成は道長の意向を受けていたとされ、それを知った彰子は怒りを覚えていたようで……。
それでも政治経験の浅い彰子では、父を止める事はできません。
一条天皇の次は、道長を外戚に持たない三条天皇であり、新たな皇太子には彰子の長男である敦成親王が立てられました。

三条天皇(居貞親王)/wikipediaより引用
この後しばらく三条天皇と道長の政争が繰り広げられ、彰子の存在感が増してくるのは、三条天皇が譲位して、敦成親王(あつひらしんのう)が後一条天皇となった後のことです。
敦成親王は幼少の身でしたので、道長が摂政となり、彰子も母后として権勢を振るうようになりました。
藤氏長者(藤原氏の代表者)と摂政の座は、間もなく彰子の弟である藤原頼通へ引き継がれますが、頼通は彰子の意向を重んじたため、まるで彰子が母后と摂政を兼ねているかのような状態になります。
白河天皇の時代まで生きた
自身の子供が即位して、ますます忙しくなっていく藤原彰子。
寛仁二年(1018年)に太皇太后を経て、万寿三年(1026年)に出家をすると、伯母の詮子に倣って「上東門院(じょうとうもんいん)」の院号を与えられました。
上東門は道長の本邸ともいえる土御門第の異称で、彰子はこちらにいることも多かったため、院号にそのまま使われたようです。
この時期になると彰子にも老いが忍び寄って来ますが、それよりも先の長元九年(1036年)に長男である後一条天皇が、寛徳二年(1045年)には次男である後朱雀天皇が崩御。
さらには孫の後冷泉天皇が治暦四年(1068年)、後三条天皇が延久五年(1073年)と次々に崩御してゆきます。
平均寿命が非常に短かった時代です。
長生きはめでたいことではあれど、息子どころか孫にまで先立たれるとなると、深い悲しみを味わったことでしょう。
彰子の長寿祝いのタイミングも多々ありましたが、ほとんど行われていません。
また、藤原北家嫡流出身の姫たちが皇子を挙げられなかったこともあって、時代は徐々に移り変わっていきました。
承保元年(1074年)に彰子が崩御した際の天皇は、ひ孫の白河天皇です。
後に院政を始める人物としてよく知られた存在ですよね。

白河天皇/wikipediaより引用
つまりは彰子の死が藤原北家の失権を象徴していた――というのも、あながち言い過ぎではないような気もします。
彰子の足跡は、これ以降の皇室や朝廷において、先例として権威付けの根拠となり、その存在は今日まで決して無視できないものになっています。
『紫式部日記』の中で「おっとりとしたお嬢様」といった描かれ方をしている彰子。
類まれな長命と後世にまで影響を及ぼす存在にまでなるとは、さすがの紫式部も想像できなかったことでしょう。
あわせて読みたい関連記事
-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか
続きを見る
-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは
続きを見る
-

史実の一条天皇はどんな人物だった?彰子や道長とはどんな関係を築いていたのか
続きを見る
-

藤原定子が最期に残した辞世の句の意味は?一条天皇に愛され一族に翻弄された生涯
続きを見る
参考文献
- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)
出版社: 吉川弘文館(国史大辞典 公式案内ページ/ジャパンナレッジ) - 服藤早苗/日本歴史学会編『人物叢書 藤原彰子(新装版 通巻294)』(吉川弘文館, 2019年5月, ISBN-10: 4642052879 / ISBN-13: 978-4642052870)
出版社: 吉川弘文館(人物叢書 公式ページ) |
Amazon: 商品ページ




