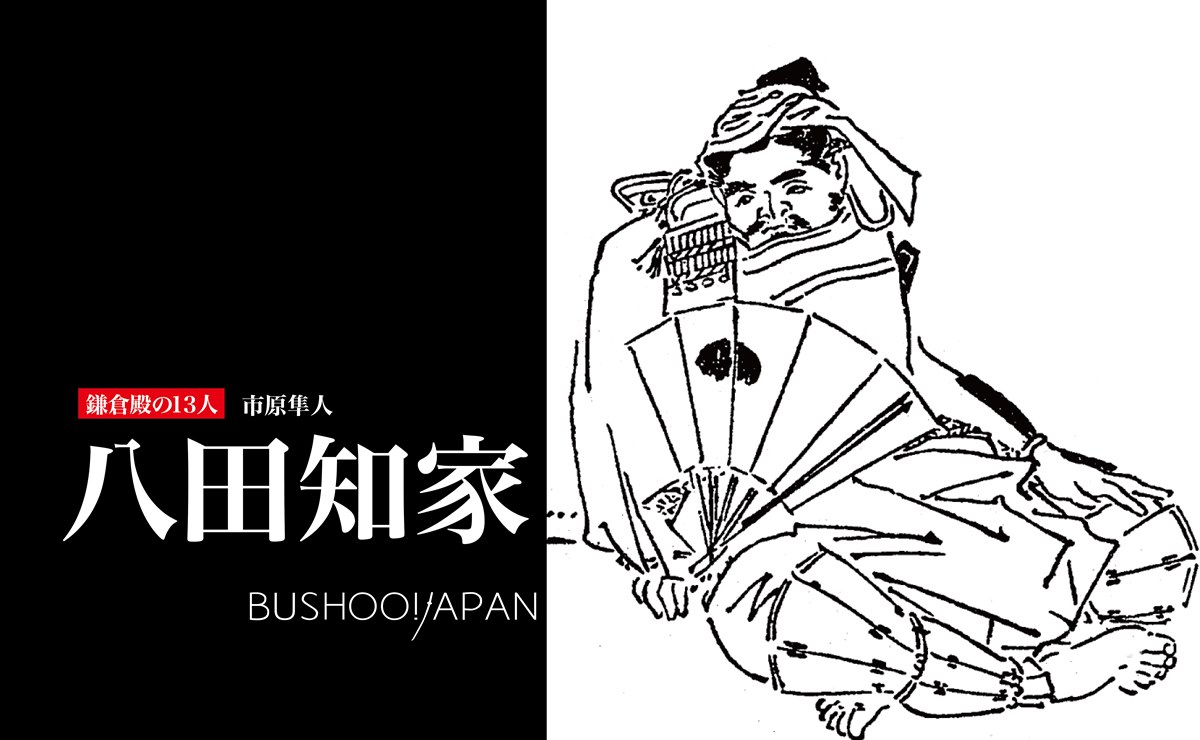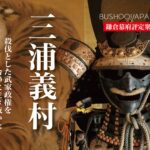こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【八田知家】
をクリックお願いします。
北条氏とガッチリ
この後から、不穏な動きのあった御家人を処分する場面で、八田知家の名が度々登場するようになります。
例えば
建久四年(1193年)12月13日に常陸の豪族・下妻弘幹
建仁3年(1203年)6月23日に頼朝の異母弟・阿野全成(あの ぜんじょう )
という両者を知家が処刑した、という記録があるのです。
前者は多気義幹の兄弟で、北条時政に恨みを抱いていたといわれています。
-

なぜ北条時政は権力欲と牧の方に溺れてしまったのか 最期は政子や義時に見限られ
続きを見る
全成(ぜんじょう )は、北条氏と共に反頼家派を形作っていたため、先手を打って北条氏に対抗しようとした頼家が、知家に命じたのだとか。
もともとは醍醐寺の僧侶ですが、以仁王の令旨が出たときに密かに抜け出して頼朝に合流し、北条政子の妹・阿波局と結婚していました。
阿波局は実朝の乳母でもあります。
しかし頼家の時代になってから北条氏と接近していたため、処刑されたのでした。
全成の息子・頼全も京都で誅殺されています。
要は”北条氏に敵対していた人の始末を、知家が命じられた”ということです。当然ながら背後に北条義時の陰もチラつきますよね。
実際、知家は、建久五年(1194年)2月2日の北条泰時元服式にも参列しています。
-

鎌倉幕府を支えた北条義時62年の生涯~殺伐とした武家社会を乗り切った手腕とは
続きを見る
-

人格者として称えられた三代執権・北条泰時の生涯~父の義時とは何が違ったのか
続きを見る
知家と北条氏の結びつきが確実になるような出来事は記録されていませんが、建久四年の時点で揺るぎないものになっていたのでしょう。
ただし、その後も基本的に、仏事・神事への参列などの場面でしか登場しません。
頼朝存命中の知家は、大きな役職を与えられていませんので、史料上の出番が少ないのも致し方ないところでしょう。
建久六年(1195年)1月8日には、それ以外の話題で一度登場します。
毛呂季光と中条家長という二人の御家人が大喧嘩をして、すわ戦かという状態にまでなったことがありました。
このときは侍所別当の和田義盛が間に入り、刃傷沙汰にまではなりませんでしたが、大きな騒動を起こしたことは問題。
そこで頼朝は、両人を処罰します。
家長は知家の養子だったため、頼朝は知家に「家長に出仕停止だと伝えよ」と命じました。
季光については将軍御所に呼びつけ、
「源氏一門に準ずる立場でありながら、御家人相手に諍いをするとはどういうことだ」
と、頼朝が直接叱責したそうです。
季光は源氏の縁者ではありませんが、
・有職故実の家である藤原北家小野宮流の血を引いていたこと
・頼朝の挙兵時点から仕えていたこと
などによって、一門に準じる扱いを受けていたとされます。
このいさかいの原因は、どうも家長・季光双方の日頃の態度にあったようです。
季光は先述の通り、他の御家人より一段高い身分を与えられていました。
そして家長は家長で、知家の養子であることを威張り散らしていたのだといいます。
そこで季光が家長に注意をしたところ、騒ぎになったのだとか。
鎌倉初期にはよくある話なのですが、それにしても血の気が多すぎますね。
二人とも頼朝の挙兵時点から仕えていますから、「若気の至り」といえるような歳でもありませんし。
京都の名医を呼び寄せるも
その後は建久六年(1195年)に頼朝の二度目の上洛に随行したり、これまでと変わらず各種行事に参加しています。
他の御家人同様、頼朝の死去前後から、ほとんど動向は記録されていません。
建久十年(1199年)2月に頼朝の長男・頼家が将軍の座を継ぐと、2ヶ月後には十三人の合議制が設置され、八田知家もその一員として参加。
記録としては乙姫に関するものがあります。
このころ頼家の妹(頼朝の次女)である乙姫の病気が悪化。
正治元年(1199年)5月7日に、わざわざ京都の名医・丹波時長を派遣させています。
というのも、乙姫は入内が決まっていたため、鎌倉の人々としてはなんとしても回復してもらいたかったのです。
そのため、名医とされる時長への期待はかなり高く、これでもかと厚遇されています。
まず宿所などの手配が大江広元と八田知家に命じられ、接待も知家の他、北条時政や三浦義澄・三浦義連、梶原景時が毎日日替わりで行っています。
-

三浦義澄(義村の父)は頼朝の挙兵を支えた鎌倉幕府の重鎮~史実でどんな実績が?
続きを見る
-

なぜ梶原景時は鎌倉御家人たちに嫌われたのか 頭脳派武士が迎えた悲痛な最期
続きを見る
乙姫は5月29日にいくらか食事を取れるようになりましたが、6月14日には再び悪化。
すると時長は「これはもう人の手が及ぶものではない」と匙を投げ、6月26日には京都へ帰ってしまいました。
前日25日には、乙姫の乳母父である中原親能が急遽京都から帰ってきていることと、対照的にも見えますね。
-

中原親能は大江広元の兄だった?朝廷官吏から頼朝の代官に転じた鎌倉幕府の重鎮
続きを見る
乙姫は6月30日に14歳の若さで亡くなり、知家ら多くの御家人が葬儀に参加しました。
承久の乱にも?
正治二年(1200年)1月5日に椀飯を行っていますが、このあたりから知家に関する記述は激減します。
建暦三年(1213年)12月1日の火事で知家邸も被害に遭った
承久三年(1221年)の承久の乱では後方での指揮にあたった
この二点のみといっても過言ではありません。
【承久の乱】では、息子の知尚が上皇方について敗死していますが、それに関する知家の言動も伝えられていません。
-

なぜ承久の乱は勃発しどう鎮圧されたのか?後鳥羽上皇が義時や鎌倉に抱いた不信感
続きを見る
-

なぜ後鳥羽上皇は鎌倉幕府との対決を選んだのか?最期は隠岐に散った生涯60年
続きを見る
知家の没年を建保六年(1218年)とする説もあるようですので、後者については誤伝の可能性もあります。
実像をうかがえるのは、やはり頼朝存命中の言動ということになるでしょう。
・うっかり平家討伐の最中に無断で任官を受けてしまったこと
・上洛出発の日に遅刻しながらも馬についてアドバイスをする肝の太さ
・多気義幹を陥れた謀将としての顔
・結果、頼朝には嫌われていないこと
うーん、やっぱり不思議な方としか言いようがないですね。
あわせて読みたい関連記事
-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか
続きを見る
-

坂東のカリスマ・源義朝が鎌倉の礎を築く! 頼朝や義経の父 その実力とは?
続きを見る
-

伊豆に流された源頼朝が武士の棟梁として鎌倉幕府を成立できたのはなぜなのか
続きを見る
-

源範頼が殺害されるまでの哀しい経緯 “頼朝が討たれた”の誤報が最悪の結末へ
続きを見る
-

源頼家の生涯~権力闘争の末に風呂場で急所を斬られて粛清された二代将軍
続きを見る
-

殺伐とした鎌倉を生き延びた「三浦義村」義時の従兄弟は冷徹に一族を率いた
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
安田元久『鎌倉・室町人名事典』(→amazon)
岩波書店辞典編集部『世界人名大辞典』(→amazon)
『日本人名大辞典』(→amazon)