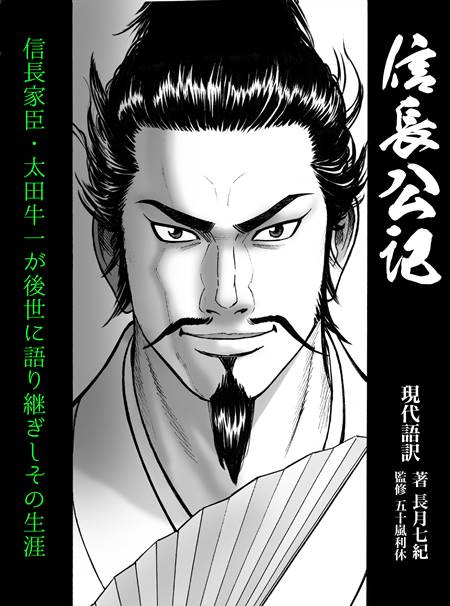前回から始まった織田家の伊勢攻略。
名門・北畠氏を追い込むため、豊臣秀吉が先陣きって阿坂城を陥落させたところまで進みました。
むろん、他にも北畠の城はいくつか残っています。
普通ならば支城を各個撃破するところですが、そこは信長。
やはり目の付け所が違いました。
いきなり北畠氏の当主親子がいる城に攻めかかるという、大胆な伊勢攻略を始めたのです。
本拠地は霧山城 大河内城から西へ30km
実は、足利義昭を奉じて京都へ上るときにも同様の戦術を駆使しておりました。
美濃から京都までの上洛で立ちはだかった六角氏(南近江)。
その本拠地・観音寺城へ一気に攻め入り、あっという間に陥落させているのです。
というか六角氏がそそくさと逃げ出したんですけどね。
北畠氏の本拠地は霧山城といって、もう少し内陸に入ったところにあったのですが、このときは信長の侵攻に備え、もう少し東側の大河内城にいました。
黄色=岐阜城
赤色=(左)霧山城 (右)大河内城
大河内城に、当主の北畠具房と、隠居の身ながら実権を持ち続けていた北畠具教がいたため、信長はここを攻略しようと考えたのです。
成功すれば、まぁ手っ取り早い戦略ではありますよね。
そんな簡単にいくのか?という疑問も当然ありましょう。
織田軍は、まず城下まで進軍、東の山に布陣して町を焼き払いました。
そして、永禄十二年(1569年)8月28日になると、城の周囲を駆け、地勢を確認。
配下の諸将を大河内城の東西南北に配置します。
いよいよ本格的な大河内城攻めの始まりです。
かなりの大人数で敵をガッチリ囲む
織田軍もかなり本気だったのでしょう。
『信長公記』に掲載されている攻撃武将も、かなりの大人数が記載されております。
ここでは現代でも知名度が高い人を何人かピックアップしておきましょう。
東:柴田勝家、森可成、佐々成政 他
西:木下藤吉郎(豊臣秀吉)、氏家卜全、安藤守就、佐久間信盛 他
南:織田信包、滝川一益、稲葉一鉄、池田恒興、蒲生賢秀、丹羽長秀 他
北:坂井政尚、磯野員昌 他
地形や城の造りとしては
東:阪内川・二の丸
西:谷・西の丸
南:谷・搦手口
北:矢津川・大手口
となっており、これらの中心に本丸がありました。
配置された武将の数からすると、南側が最も兵数が多く、その次が東側、ついで西側で、北はやや薄めという感じでしょうか。
大河内城から西へおよそ30Kmほど行くと、前述の通り北畠氏本拠地の霧山城や、阪内城があるため、攻めやすさと北畠方の連携を防ぐことを両立した割り振りだと思われます。
さらに、城の周囲には柵を二重三重に巡らせ、前田利家を始めとした警備隊が巡回していました。
完全な包囲網といえるでしょう。
とはいえ、今回の戦はこれまで信長がやってきた城攻めとは少々勝手が違います。
清州城乗っ取りや稲葉山城攻めの際は、内通者や敵方家臣の切り崩しに成功したことが大きな勝因。
そして北畠は、六角氏の観音寺山城攻めのように、向こうが勝手に逃げ出してくれる――という場面も考えにくい状況でした。
初日の攻撃は雨で鉄砲不発
信長も時機を見計らっていたのでしょう。
次の行動に出たのは9月8日のことでした。
城の周囲に陣を張ってから約10日がかかっており、これまでの信長行動パターンからすれば、かなり時間をかけた判断ですね。
この日、稲葉一鉄・池田恒興・丹羽長秀の三人に、それぞれ分かれて西側から夜襲をかけるように指示しました。
が、攻撃開始から程なくして雨が降ったため鉄砲が使えず、予想外の苦戦となります。
三隊合わせて、20余名が討ち死にしてしまいました。
翌9日、今度は滝川一益に命じて、大河内城ではなく霧山城の焼き討ちと稲の刈り取りをさせました。
いわゆる刈田狼藉というやつで、北畠方にとってみれば本拠地を焼かれた上に兵糧が届く見込みもなくなり、大河内城に籠もっている将兵にとっては絶望的な状況です。
実は大河内城自体も長期戦を想定しておらず、この時点で既に餓死者が出ていた……と、信長公記には書かれています。
そのため、北畠親子はついに降参を決意。
詫びを入れてきた彼らに対し、信長は
「俺の次男を養子に迎えて、家督を譲るなら許す」
という条件をつけました。
ここまで真正面から「お前の家は今日から俺のもの」と言われて、北畠にとっては屈辱以外の何物でもなかったでしょう。
村上源氏の血を引く超名門 息子の織田信雄に継がせる
本来、北畠氏は村上源氏の血を引いた超名門。
南北朝時代には南朝方について後醍醐天皇の覚えめでたく、それ以降、ずっと伊勢国司を引き継いできた家柄です。
要は「由緒正しきお公家さん」の血筋なわけで……それが新興勢力である信長にあっさり負けてしまったのですから、プライドがズタズタになったことでしょう。
いかにも戦国時代という話です。
なお、信長の次男とは、織田信雄のことです。
当時はまだ元服前で「茶筅丸」といいました。
名実ともにまだ子供で城の受け取りはできませんから、その役は滝川一益と津田一安(織田忠寛)が務めています。
一安は、信長の遠い親戚筋といった関係の人で、甲斐武田氏との外交を任されていました。
信長との関係が悪化して甲斐に身を寄せていたという説もありますが、はっきりしていません。
ただし、城の受け取りという重要な役どころを任されているぐらいですから、少なくともこの時点での立場は悪くなかったのでしょう。
その他、北畠氏の城を破壊するよう命じ、伊勢攻略は終了しました。
後始末諸々のため、信長はもうしばらく伊勢に滞在します。
次回以降はそのお話です。
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

斎藤龍興の生涯|美濃を追われ信長へ執拗に反撃を繰り返した道三の孫
続きを見る
-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか
続きを見る
-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)
書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)
出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)
書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)
出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)
出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ