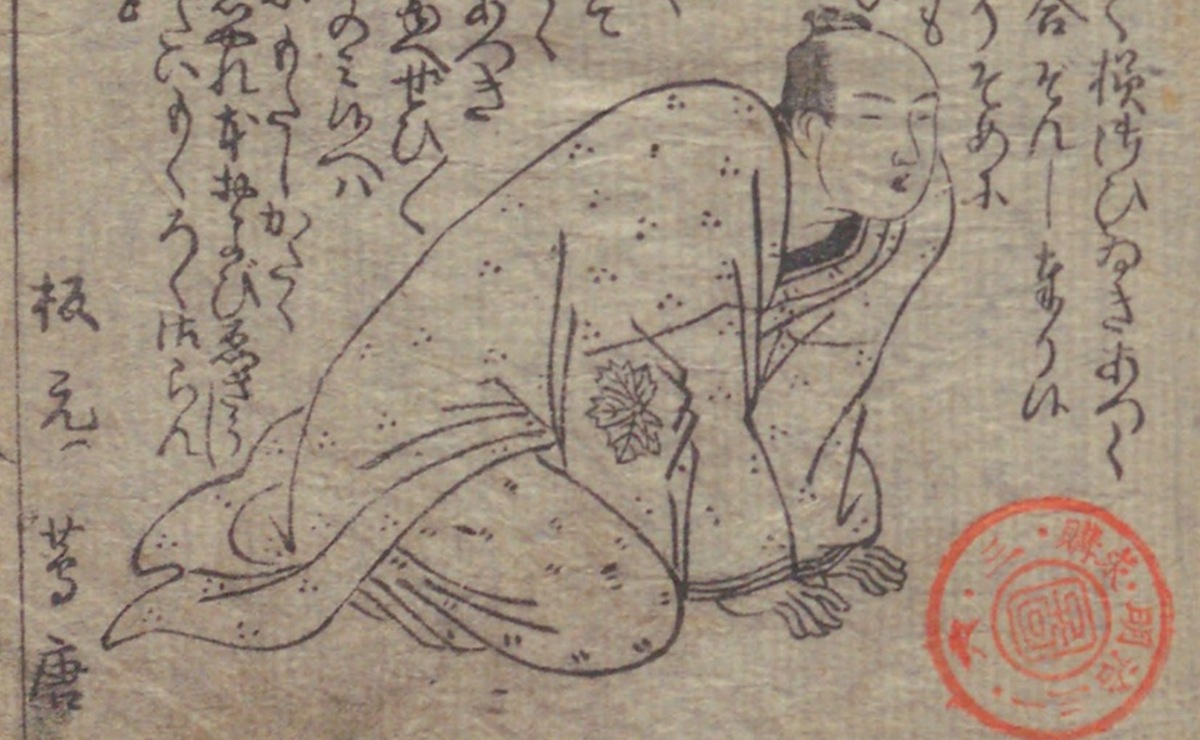こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【なぜ蔦重は地本問屋になれないのか?】
をクリックお願いします。
筋を通していない蔦重
蔦屋重三郎が吉原から出て出版業を目指そうという時、師匠になったのが鱗形屋孫兵衛でした。
すでに実績のある鱗形屋のもとでノウハウを学ぶ。
劇中ではそれと引き換えに蔦重が吉原細見の取材をしたり、青本のネタを提供したり、かなり重要な仕事をこなしていましたが、思わぬところで頓挫してしまいます。
鱗形屋が偽板騒動を起こしてしまうのです。
劇中で「本屋になりたい」とこぼす蔦屋重三郎に、自身の“経験”を語ってくれたのが須原屋市兵衛でした。
彼は【暖簾分け】で店を開いたと語ります。
暖簾分けとは、主人が奉公人に同業での出店を許すことを言い、許可を得れば主人と似た号や意匠を用いることもでき、客の側でもそれと判別できる仕組みになっています。
いわばブランドですね。
現代でもそうした営業形態はあり、飲食店の紹介等で「あの名店で修行を積んだ店長」と紹介されることがあります。
江戸時代はこの形式が盛んでした。

ならまちの織物店/wikipediaより引用
須原屋市兵衛は、江戸時代前半に【書物問屋】を構えた初代・須原屋茂兵衛のもとで奉公し、暖簾分けされました。
この須原屋こそ、江戸の書物問屋の祖ともいえる店であり、上方に負けぬ出版業を盛り上げて欲しいという願いを込めて、市兵衛に暖簾分けしたのでしょう。
暖簾分けは才知と人格が認められてこそ、許されるもの。市兵衛の優れた人柄も腑に落ちます。
こうした暖簾分けまでは一定の年数が必要であり、現在ならば小学生くらいから奉公してきて拓ける道ともいえます。
蔦重が鱗形屋に入ったのは成人後です。
それでも何年か孫兵衛の右腕として働き、信頼を得ていたら、道も拓けたかもしれません。
鱗形屋の災難は、蔦重にとっても大きな蹉跌であったともいえます。
こうした仕組みを見ると、鱗形屋孫兵衛がのちに蔦重に言った激しい言葉の意味もみえてきます。
一度鱗形屋の元に入った以上、蔦重が同業の店を開くのであれば、暖簾分けをしてもらうことが筋を通すことと言える。
しかし蔦重はそうしなかった。
それどころか鱗形屋の売れ筋である『吉原細見』を出したのです。
同業の【地本問屋】である西村屋が『吉原細見』を出したところで、鱗形屋としては奉行所に捕縛されていたからには、致し方ないとはいえる。

初代西村屋与八/wikipediaより引用
鱗形屋が奉行所に連れ去られたあと、西村屋は金を積んで『吉原細見』の板木を買おうと持ちかけていました。
あれは作る手間を省きたいだけでなく、揉めず後腐れなく事業を引き継ぐという意味合いもあったのでしょう。
しかし蔦重がいきなり出したとなれば、「うちから商いを盗んだ」と見なされても仕方ありません。
劇中では【地本問屋】が、
「倍売れる『吉原細見』を作ることができれば認める」
という条件を提示しておりました。
しかし、鱗形屋からすれば、どのみち自分が不在の際に勝手に決められた話で、知ったことではないのです。
蔦屋は吉原という後ろ盾がある
なぜ地本問屋の連中は、蔦重の市中進出を嫌悪するのか。
「吉原者」への差別感情を吐き出した鶴屋喜右衛門に対し、大文字屋が駿河屋が怒りをあらわにするシーンがありました。
しかし、そんな露骨でわかりやすい理由だけではありません。
もっとモヤモヤとした複雑な事情がある。
吉原がバックに居る蔦重は、あまりにも恵まれている――そう思いませんか?
蔦重が渾身の気合いで売り出した『青楼美人合姿鏡』は、出来は良くても売上は伸びませんでした。
そこで蔦重は、売れ残った本を吉原の親父殿たちに買い取ってもらうこととします。
本の制作費用を親父殿たちに無心していたため、収支は赤字。蔦重は借金を抱えることになりました。
「身内だろうがしっかり金を返させる」
蔦重はそうぼやきましたが、その話を聞いた須原屋は「恵まれているな」としみじみ語ります。
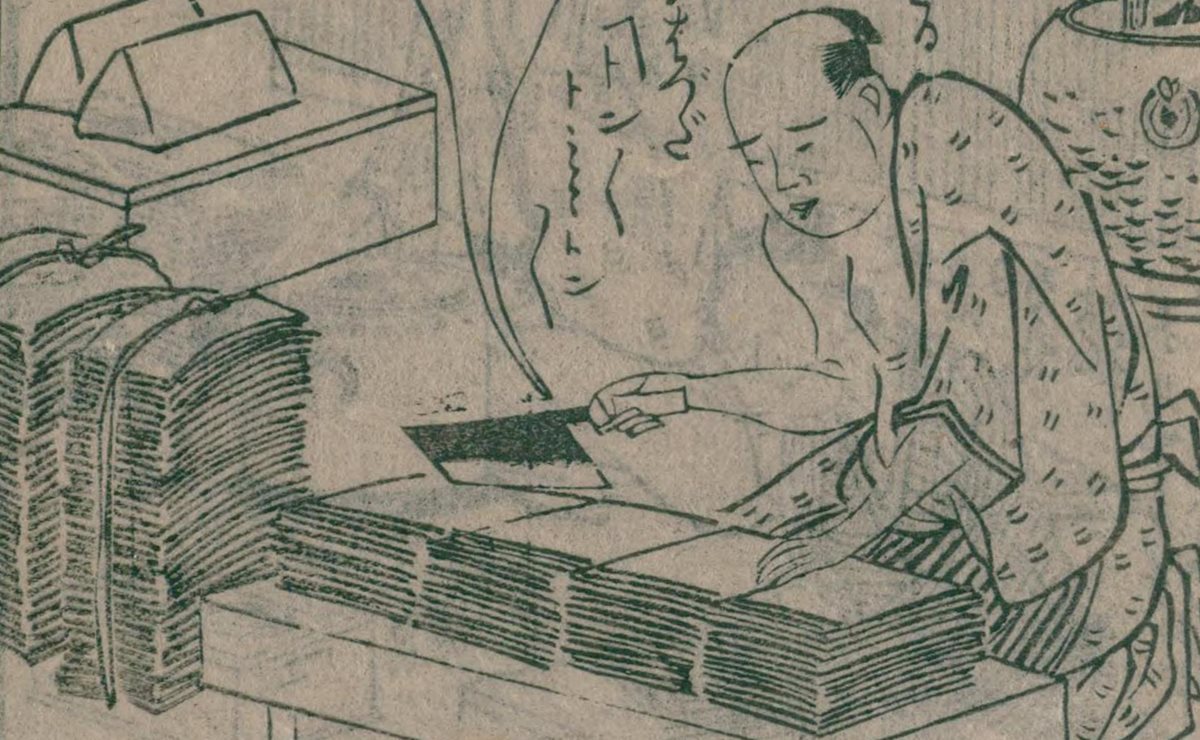
画像はイメージです(地本問屋の様子/国立国会図書館蔵)
須原屋が語るその背景には【座頭金】に取り立てられる鱗形屋の苦境がありました。
一方で蔦重はどうか?
実は大博打をしているようで、実情はそうではない。
素晴らしい大技を決めているようで、命綱をつけたパフォーマンスをこなしている状況と言えます。
遊女を紹介する本として『一目千本』を作る過程が劇中では描かれました。同じジャンルの『急戯花の名寄』もこのあと出しています。
こうしたガイドにせよ『青楼美人合姿鏡』にせよ、吉原本となれば売れなくても配布するという手段が取れます。それで吉原の評判が上がれば、そこまで厳しい評価は受けません。
失敗しても許されるんですね。
しかも赤字になっても、身内から金を借りられる。
この二点が、実は大変恵まれていると言えます。
視聴者がそのことに気づくのが遅れても仕方ありません。蔦重本人ですら、須原屋本人から指摘されるまで気づかなかったのです。
とはいえ、そんなことは地本問屋からすれば知ったことではない。
そんなに恵まれた環境で競合を出してくる蔦重のことが腹立たしくてもおかしくはありません。
ましてや鱗形屋からすれば、売れ筋を盗まれたようなものであり、憎くて仕方ないでしょう。
二男である万次郎は蔦重のことを「疫病神!」と罵倒しました。幼いがゆえに素直な物言いは同時に地本問屋たちの本音でもあるのでしょう。
※続きは【次のページへ】をclick!