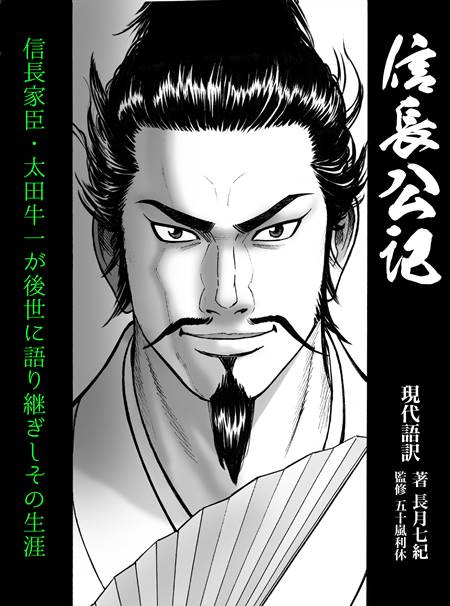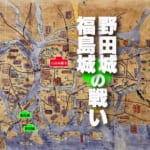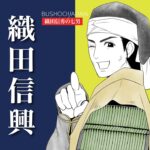今回のテーマは【志賀の陣と宇佐山城の戦い】です。
野田城・福島城の戦いで大坂の本願寺とバリバリやりあっていた織田信長が、浅井・朝倉からの蜂起を受けて非常にドタバタする局面です。
信長が最も追い込まれたとき――と指摘する研究者さんもいるほどで、せわしない攻防に追い立てられます。
いささかややこしいですので、一つずつジックリ見ていきましょう。
志賀の陣・宇佐山城の戦い三行マトメから
まずは大雑把な経過を三行でマトメておきましょう。
①信長が大坂の本願寺とやりあっている頃、浅井・朝倉連合軍が近江の織田軍拠点を攻めてきた
↓
②信長、本願寺攻めを中断して近江へとんぼ返り
↓
③なんやかんやあって和睦
ザックリしすぎてごめんなさい。ともかく織田軍の動きとしては大坂→近江→(和睦後に)岐阜という感じです。
では、もう少し詳しく見ていきます。
舞台は元亀元年(1970年)9月~12月のことです。
まず、9月16日に浅井・朝倉3万の連合軍が坂本(大津市)を攻めました。
信長の留守を狙った形です。
これに対抗したのが、宇佐山城(大津市)にいた森可成。「もりよしなり」と読み、森長可や森蘭丸の父親として知られますね。
-

森可成の生涯|信長が頼りにした織田家の重臣 蘭丸の父は壮絶な最期を迎える
続きを見る
可成は、わずか1,000程の兵を率いて坂本の町外れで浅井朝倉軍と対峙すると、いくつか首を挙げて勝利を収めます。
しかし、その奮闘も長くは続きませんでした。
信長に「天下一の勇士なり」と褒められた道家兄弟
同月19日、浅井朝倉軍が二手に分かれ、再度、坂本を攻めました。
可成は町を守ろうと再び奮闘するも、さすがに大軍に押されて、配下と共に討死してしまいます。
この戦いでは「道家清十郎・助十郎という武士の兄弟も討死した」と『信長公記』には記されております。
彼らは、かつて東美濃に武田信玄が侵攻してきた際、二人で三つもの首を挙げ、信長に讃えられたことがあった勇将です。
二人が使っていた旗指物の白い旗に、信長手ずから「天下一の勇士なり」と書きつけるほどだったそうで。
武田を相手にしたときも、そして浅井朝倉を迎え撃つときも森可成の下で戦っており、このときも命運をともにしたのでした。
名誉もさることながら、忠義心もあっぱれなものです。だからこそ、著者である太田牛一も書き留めたのでしょう。
可成に勝った浅井・朝倉軍は道中で放火を繰り返しながら、京に迫ります。信長にこの動きが知らされたのは、9月22日のことでした。
野生の勘で渡河ポイントを探り当てる!
信長も信長で、それどころではありませんでした。
前回(73話)で敵対した本願寺と【野田城・福島城の戦い】が続いており、押され気味になっていたのです。
-

野田城・福島城の戦い(第一次石山合戦)|信長公記第73話
続きを見る
ドコかで何かしらの転換を図らなければ、ズルズルと被害が増えてしまいそうな状況。そこで浅井朝倉の侵攻を機に撤退を決断し、将軍・足利義昭と一緒にいったん京へ帰還することにします。
翌23日に陣を引き払うと、殿を和田惟政・柴田勝家に任せています。
-

和田惟政の生涯|信長と義昭の板挟みで苦悩した“摂津三守護”の一人
続きを見る
京・岐阜への帰還ルートは、中島から江口川を渡し船で渡って、向かう予定でした。
しかし、どこから聞きつけたのか、一揆勢によって船が隠されてしまいます。
普通ならここでまた一戦するか、かなりの大回りをするかというところですが、さすが信長、そうは簡単に諦めません。
信長は自ら川の上下を見て回り、馬を乗り入れて、馬や人が渡れるところを探し出してしまうのです。
そのおかげで、織田方は無事に渡りきることができました。
普段、この川は水量が多く、舟でなければ渡れないと考えられており、実際、その翌日以降、徒歩ではとても渡れなかったため、みんな不思議がったそうです。
若かりし頃から馬で山野を駆け回っていた信長だけに、川の流れや付近の様子から、川底までの深さなどに対して野生児のような勘が働いたのでしょう。
浅井・朝倉軍をかくまい続ける延暦寺
こうして織田軍は無事に京都まで帰還すると、24日には逢坂山を越えて浅井・朝倉勢と対峙します。
相変わらずの電光石火っぷり。全く予想していなかったのか、浅井・朝倉軍は比叡山延暦寺に駆け込みました。
これに対し、信長は延暦寺の僧侶を10人ほど呼び、
「これからこちらの味方につくなら、ウチの領内にある延暦寺の領地はすべて返そう」
「出家の道理として一方の味方をすることはできない、というなら、浅井・朝倉軍に味方するのをやめ、我々の邪魔もしないでもらいたい」
と、筋道を立てて主張を伝えました。
また、
「もしこの二つに違背することがあれば、そのときは根本中堂・日吉大社を始め、山ごと焼き払う」
という一文も付け加え、稲葉一鉄に命じて朱印状にし、これを延暦寺側に渡しています。
しかし、延暦寺からはなんの返答もなく、浅井・朝倉軍をかくまい続けました。
それだけではありません。
山内の僧侶たちが肉や魚を食べ、女性を引き入れているという乱れっぷりであることが判明。
これが後々、延暦寺焼き討ちの要因となります。
本連載でも後日公開しますが【比叡山焼き討ち】が気になる方は、以下の記事をご覧ください。
-

信長の比叡山焼き討ち事件|数千人もの老若男女を“虐殺大炎上”は盛り過ぎ?
続きを見る
浅井・朝倉軍は将軍とも敵対したことに
この日、信長は下坂本(大津市)に陣を取りました。
翌日からは比叡山を大々的に包囲しています。
著名な武将を挙げておきますと……。
柴田勝家・氏家卜全・安藤守就・稲葉一鉄・佐々成政・明智光秀・村井貞勝・佐久間信盛・織田信広・不破光治・簗田広正・河尻秀隆など。
こうした織田家を代表する武将たちの他に、足利将軍から派遣された兵も浅井朝倉の包囲に参加。名実ともに、浅井・朝倉軍は将軍とも敵対したことになります。
しかし、相変わらずの硬直状態が続き、山本対馬守・蓮養坊という、この地に詳しい者たちが夜な夜な忍び込んでは放火して回ったとか。
物理的にも精神的にもプレッシャーを与えるやり方ながら、浅井・朝倉軍も比叡山も、そう簡単には諦めません。
実に10月20日まで粘るのです。
相手の粘りに対し、さすがに信長のほうがキツくなり、他への影響を懸念し、使者として菅屋長頼を出しています。
この人は若い頃から信長の馬廻りとして仕えていて、前線で戦う武士というよりは、交渉や連絡などの役目をよく命じられていました。
武芸よりも話術や人格に優れたタイプだったのかもしれませんね。
信長は長頼を通して「いつまでもこうしていても不毛だから、一線交えて決着をつけよう。日限を定めて出撃してこい」と伝えました。
帰ってきたのは意外な答えでした。
「和睦したい」
信長ピンチと聞いて秀吉駆けつける
織田信長はこれまでの鬱憤をぜひとも晴らしたかったので、撥ね付けはねつけました。
森可成という得難い家臣をやられた上、散々引っかき回されているのですから、引けない思いも当然でしょう。
軍事的コストを考えれば、ここで一気に片付けておいた方が話も早いです。
南へ目を向ければ、摂津の三好三人衆が野田城・福島城を補強するなどして、信長への敵意を表し続けておりました。
周辺の大名も堅固に守りを固めており、京都方面へ近づくことはできず、膠着状態――。
南近江では六角義賢親子が菩提寺の城(湖南市)まで来ていたとされます。
不幸中の幸いというべきか、こちらは兵力がなさすぎて、戦の準備にすらなっていませんでした。
近江でも本願寺門徒が一揆を起こしたものの、すぐに木下藤吉郎(豊臣秀吉)・丹羽長秀に鎮圧され、こちらも大事には至りません。
もともと彼らは、浅井家の小谷城を見張るため、横山城を守っていたのですが、
【本願寺と浅井朝倉に挟まれて信長大ピンチ】
という一報を聞き、わずかな兵で駆けつけるのでした。
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
なんとも秀吉らしいじゃないですか。大人気の戦国漫画『センゴク』でも一つの山場として描かれていたシーンで、元々は『信長公記』に書かれていたんですね。
信長も大いに喜んだようで、織田軍の士気も上がるのでした。
長島の一向一揆に攻められ弟が自害
しかし11月21日に尾張で悲劇が起きています。
信長の弟・織田信興(織田信与)が、居城としていた尾張・小木江城を長島の一向一揆に攻められ、自害していたのです。
彼は早くから信長に従い、信長も厚い信頼を寄せていた弟でした。
-

なぜ信長の弟・織田信興は一揆勢に殺されたのか 長島一向一揆の幕開け
続きを見る
信興の生年はわかっていませんが、彼は信秀の七男であり、九男または十男とされる信照が1546年生まれなので、信興は1540年前後が妥当でしょうか。
となると、この戦のときは30歳前後。まだまだ将来有望な弟を失ったことで、信長がいかにショックを受けたか。想像に難くありません。
長島も本願寺や延暦寺同様、後に織田軍が大々的に攻めることになります。
これらの戦については「信長の残虐性の象徴」として語られる事が圧倒的に多くなっていますが、信長も大切な家族や家臣を彼らに奪われていたのです。
戦国のならいとはいえ、なんとも無情な気分になりますね……。
信興の件を、信長がいつ知ったかは定かではありません。それに対する反応も、信長公記には書かれていないのです。
22日に六角義賢と和睦しているため、このあたりで他の報告などと一緒に知った可能性もありますが。
朝倉から和睦をしたいと泣きついてきた!?
11月25日、堅田(大津市)の水軍を率いる、猪飼野正勝(猪飼昇貞)・馬場孫次郎・居初又次郎が信長に味方しました。
彼らは六角氏→浅井氏と主を変えてきたのですが、ここに至って織田方につくことを決めたようです。
これに応じ、この夜、堅田へ千人の兵を増派したところ、越前(朝倉)方に攻め込まれて戦闘になります。
各所で応戦し、討ち取った者も多かったようですが、織田方の被害も大きく、快勝とはいえない状況でした。
中でも、坂井政尚と浦野源八親子の活躍がめざましかったと伝わるのですが、政尚はこのときの戦で討死したとされます。
奇襲に成功したのは越前方です。
普通、こういうときは勢いに乗って織田軍へ決戦を申し込むなり、勇ましい選択をするものですが……なんと、朝倉義景は「信長と和睦したい」と将軍に泣きつきました。
-

なぜ朝倉義景は二度も信長を包囲しながら逆に滅ぼされたのか?41年の生涯まとめ
続きを見る
寒さと雪が強まってきたことにより、本国への帰路や連絡・輸送などが心配になったのでしょうか。
旧暦11月末=新暦12月末ですから、自然ではありますが……どうにもこうにも間が悪いというか、今更という感は拭えません。
足利義昭はこれを容れて、和睦調停を信長に申し入れます。
信長自身としてはやはり決戦を選びたいところ。
しかし、11月29日に義昭が三井寺(大津市)まで来て説得しにかかったために断りきれず、不本意ながらも和睦を結ぶことになりました。
状況だけ考えれば、織田軍も相当苦しかったと思うのですが……。信長礼賛の『信長公記』だけに、いささか強がりも入っているという印象は拭えません。
いずれにせよ和睦は和睦です。
野田福島の戦いから4ヶ月も戦い、実りナシ
和睦が成立したのは12月13日のことでした。
朝倉方からの条件は、次の通りです。
・織田方は琵琶湖を渡り、勢田(大津市)まで退くこと
・浅井朝倉軍が高島(高島市)へ退くまで、織田方から人質を出すこと
これに従ってまず織田軍が撤退し、その後浅井・朝倉軍が山を降り、この戦は終わっています。
信長が岐阜城へ帰ったのは、12月17日のことでした。
包囲などの帰還も含めると、8月に野田城・福島城の戦いに臨んでから、おおよそ4ヶ月戦をしていたことになります。
それでほとんど得たものがなく、家臣や弟を失っただけ……となれば、信長の無念や怒りも想像できますね。
あわせて読みたい関連記事
-

野田城・福島城の戦い(第一次石山合戦)|信長公記第73話
続きを見る
【参考】
国史大辞典
『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)
『信長研究の最前線 (歴史新書y 49)』(→amazon)
『織田信長合戦全録―桶狭間から本能寺まで (中公新書)』(→amazon)
『信長と消えた家臣たち』(→amazon)
『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)
『戦国武将合戦事典』(→amazon)