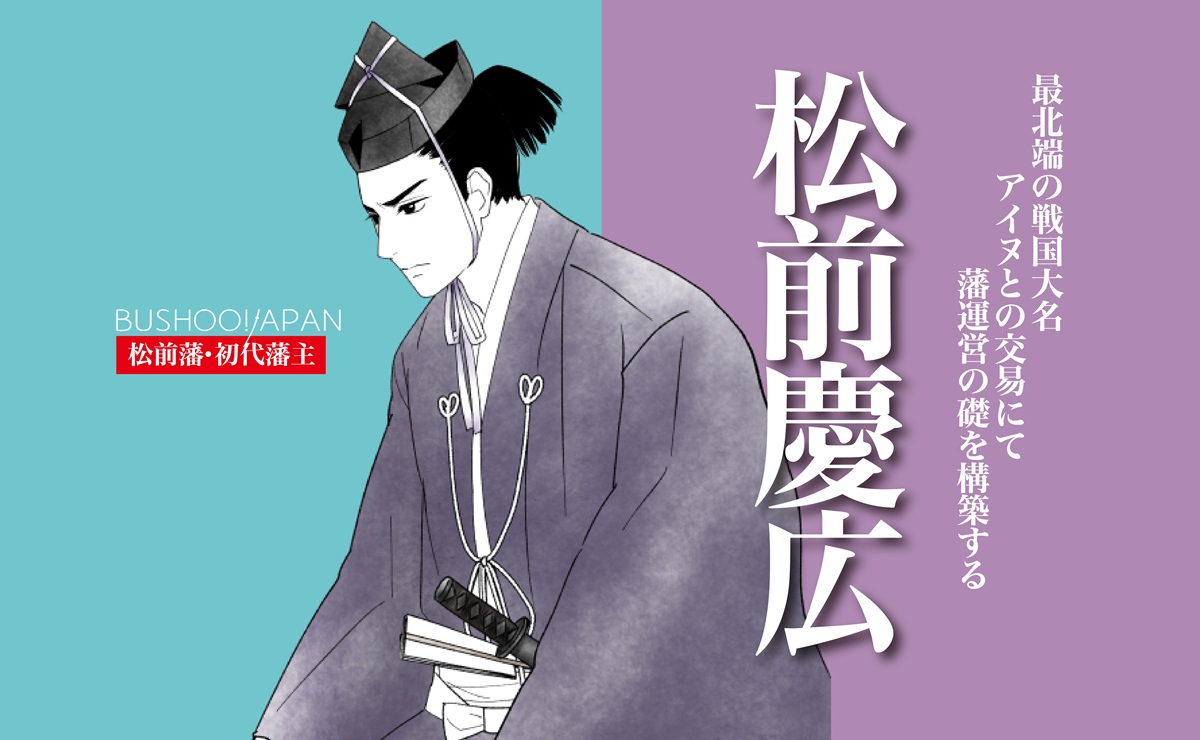戦国時代、日本列島の最南端で大きな勢力を築いた武家と言えば、島津氏。
では“最北端”でもっとも大きな勢力だった戦国大名は?
そう問われて即答できる方は少ないでしょう。
安東氏や蠣崎氏、南部氏に津軽氏など、いくつか有力武家の名は浮かんできても、誰を選ぶべきかいまいち判断がつかない。
島津氏のような圧倒的存在が北には無く、そもそも最北端の定義として当時の“蝦夷(北海道)”を入れるかどうか?という判断から迷ってしまうかもしれません。
今回は、そんな曖昧だった北の地で、蝦夷に独特のポジションを築いた戦国大名に注目。
松前慶広(蠣崎慶広)です。
江戸時代の松前藩といえば石高ゼロで運営ができた稀有な藩として知られますが、その初代であり礎を築いたのが慶広。
もともとは安東氏の家臣だった慶広に、なぜそんなことが可能だったのか?

絵・小久ヒロ
その生涯を振り返ってみましょう。
※名前の表記は「松前慶広」で統一します
幼名は「天才丸」
松前慶広は天文十七年(1548年)9月3日、蠣崎氏四代当主・蠣崎季広の三男として生まれました。
幼名は「天才丸」といい、なかなかインパクトありますね。
父の蠣崎季広は幼名が「卯鶴丸」だったので、代々の伝統というわけでもないようです。
母の蔦姫は、蝦夷地で開拓に励んでいた河野季通(こうの すえみち)の娘でした。
河野季通はアイヌとの戦いで窮地に陥り、娘の蔦姫と父の河野政通を逃がした後に自害したとされます。
慶広の幼少期は詳細不明です。
ただ、元服の前後あたりに慶広の一族内で、恐ろしい連続暗殺事件が起きています。
しかも事件の犯人というのが、長女である姉――なかなかインパクトのある事件ですので少し詳しく見ておきましょう。
この姉というのが、かなり猛々しい性格をしていて「私が男だったら家を継げたのに!」という不満を抱いていました。
彼女の実名や通称は不明ですので、仮に【毒姉】としておきましょう。
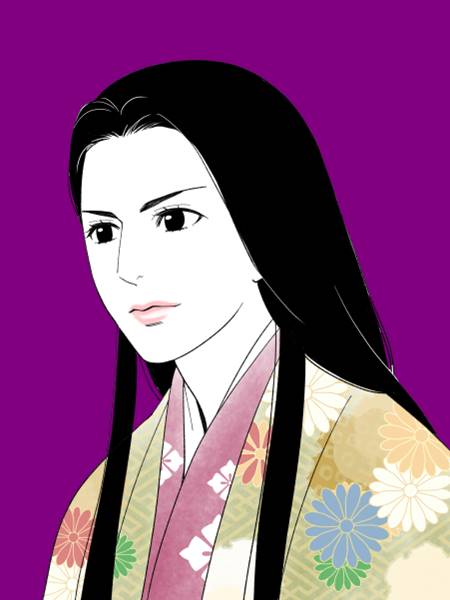
絵・小久ヒロ
家督を継げない毒姉は、政略のため南条広継という人に輿入れすると、夫を動かして実家である蠣崎氏の実権を握ろうと考えました。
ただし、真っ向から戦をしかけても勝てないと考えたのか。
毒姉は、自分の弟たちを毒殺し、広継に権力が回ってくるよう画策します。
そこでまず狙われたのが、慶広にとっては兄にあたる蠣崎舜広(としひろ)でした。
暗殺事件に関連する、慶広のきょうだいを以下に記しておきますね。
◆当時の蠣崎家(父で当主は蠣崎季広)
長女・毒姉(南条広継に輿入れ)
長男・蠣崎舜広(としひろ・嫡子)
次男・明石元広(明石家に養子)
三男・松前慶広(本稿の主人公)
毒姉が次々に兄弟を毒殺
松前慶広の兄で、蠣崎家の嫡子だった蠣崎舜広は永禄四年(1561年)に毒殺されました。
そしてその翌年の永禄四年(1562年)、今度は明石家に養子に出されていた明石元広も毒殺されてしまいます。
鮮やかというか、あからさまというか……。
次は三男の慶広が狙われたのか?
と思いきや、事件の犯人が毒姉であることが判明し、夫の南条広継と共に自害へ追い込まれました。
夫の広継はこの件に絡んでいなかったとも指摘されており、それが事実ならば気の毒どころではありません。
ともかく慶広に毒牙は及ばず、本人も周囲もホッとしたことでしょう。
慶広は、この騒動の直前である永禄三年(1560年)頃に元服したと考えられています。
その際の烏帽子親は北畠具運(ともかず)でした。
具運の北畠氏(浪岡北畠氏)は、南北朝時代の名将・北畠顕家もしくはその弟・北畠顕信の末裔を名乗っていた家。

北畠顕家/wikipediaより引用
その血統について証明する史料はまだ見つかっていませんが、戦国時代には山科言継(やましなときつぐ)と連絡を取って官位を受けたこともあるので、「公家の一員」という扱いではあったようです。
北畠具運は、周囲を南部氏と安東氏に挟まれていたため、対岸の蠣崎氏と親交を結んでおきたかったのかもしれません。
蠣崎氏は蝦夷に拠点を持ちながら、立場としては安東氏の家臣となります。
具運としては、自身の子である北畠顕村が松前慶広と同世代でしたので、将来を見据えて強固な関係を築こうとしたのでしょう。
あるいは、より有利な条件でアイヌとの交易ができるように……なんて狙いもあったかもしれません。
なんせ北畠具運は、わざわざ松前慶広に陸奥の潮潟(青森市後潟)を与えたぐらいですので、色々な見返りを望んでいたことは想像できます。
※ただし浪岡北畠氏は天正六年(1578年)、津軽為信に本拠・浪岡城を落とされて滅亡します
家督相続
毒姉の手により、上の兄弟が二人も亡くなった松前慶広。
棚ボタですんなり家督が回って……きませんでした。
一応、ライバルとして、同年に生まれた異母兄弟の蠣崎正広がいたのです。
正広は天正六年(1578年)、安藤愛季(ちかすえ/よしすえ)の家臣である南部季賢(すえかた)のお供で上洛し、その途中、織田信長にも会っていました。

織田信長/wikipediaより引用
上洛の経験で、正広は自身の優位性を感じ取ったのか、それとも上方で何か刺激されたのか。
帰国早々、正広は謀反を企てます。
しかし、試みはあっさりバレてしまい、安藤氏のもとへ逃げるという情けない騒動を起こし、その後、天正十四年に腫れ物で病死していました。
もしかしたら場当たり的に謀反を思いついたのでしょうか。
結局、松前慶広が家督を継いだのは天正十年(1582年)のことで、すでに35歳になっていました。
なぜ正広の謀反未遂から約4年もの日数を要したのか。
慶広の父である蠣崎季広が既に70代になっていましたので、もっと早くても良さそうなのに不思議なことです。
主君の安東愛季が急死
蠣崎氏は、代替わりしてもしばらくは安東の家臣という扱いでした。
しかし天正十五年(1587年)9月1日、絶好の機会が訪れます。
主君の安東愛季が急死したのです。

安東愛季/wikipediaより引用
北東北で有力大名の一つであった安東氏は、南部氏や津軽氏と勢力争いを繰り広げており、愛季の急死はその最中のことでした。
しかも跡を継いだのが12歳の安東実季だったため、同家は大混乱。
天正十七年(1589年)2月には、分家である湊安東家の通季が宗家に対して謀反を起こし、混迷を極めていきます。
こうなると蠣崎氏としてもどちらかの派閥につくのが自然な流れです。
しかし松前慶広は動きません。
どちらかに肩入れするのは危険だと判断したのか。
慶広は、南部氏に手紙や鷹を送りながら、タイミングを見計らっているようなスタンスでいます。
上方とのツテが濃い南部氏は利用価値は高そうだけれど、主君筋の安東と戦闘中では必要以上に近づけず、距離を保ちながら親交を温めておくのがベストという判断でしょう。
結果、安東氏の家督争いは実季が勝利。
蠣崎氏は、今しばらく安東氏の家臣として振る舞うことになりました。
※続きは【次のページへ】をclick!