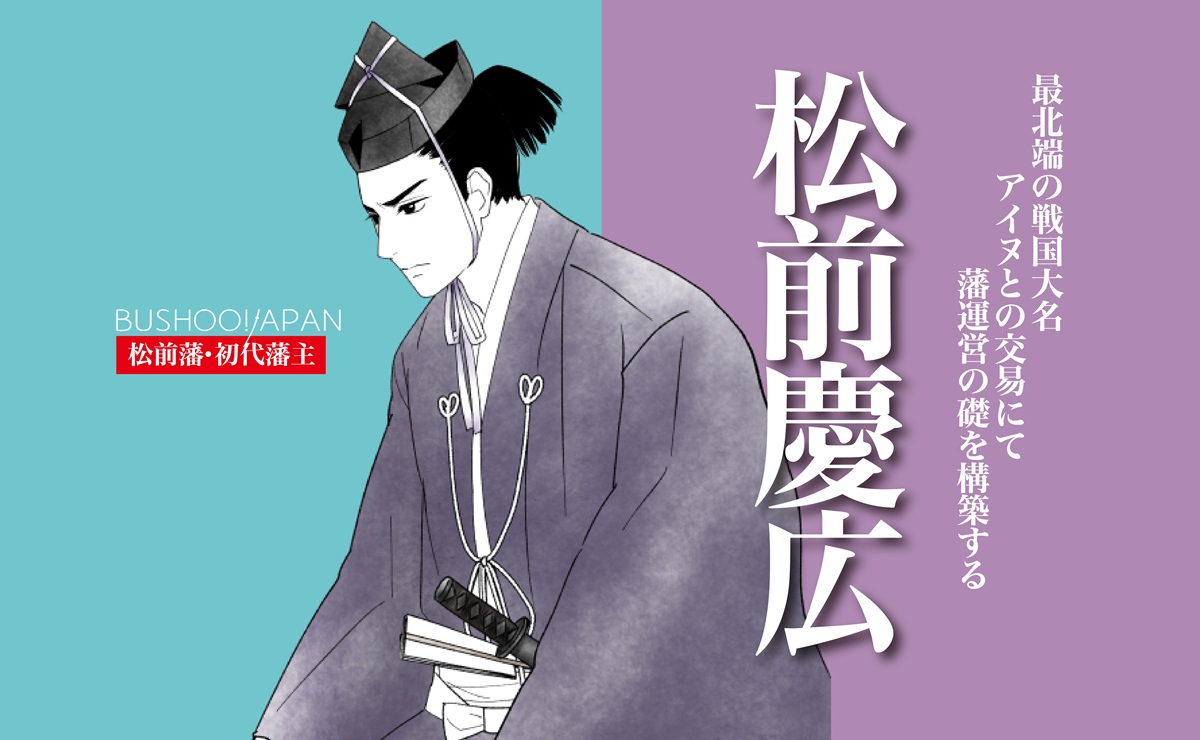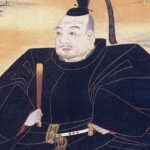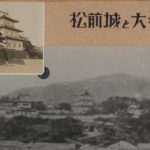こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【松前慶広(蠣崎慶広)の生涯】
をクリックお願いします。
日本海の交易に乗り出し北前船の礎を作る
遠隔地であることが強く影響してか。
蠣崎氏と松前慶広は文禄・慶長の役や秀吉死去前後のゴタゴタにはあまり関与していません。
ただし、自領のため松前家のため、きちんと動いています。
慶長元年(1596年)、嫡子の松前盛広を江戸で家康に謁見させました。
秀吉が存命中のときに大丈夫なのか?という懸念はありますが、文禄・慶長の役で破綻の始まった豊臣政権と、何かと手堅い徳川家康を比較して、慶広の中で答えは出ていたのでしょう。
日本の最北端に拠点を構え、上方に基盤の無い慶広だからこそ、冷静に気付けたのかもしれません。

徳川家康/wikipediaより引用
また、慶長四年(1599年)頃から、慶広は日本海航路を使っている商人に対して積極的に連絡を取り、「特権をあげるので、松前でも商売してくれませんか」と頼み始めます。
本州・松前領・アイヌで交易を拡大させ、さらに利益を上げようとしたのです。
現代まで続くその名残りが富山県で消費される昆布でしょう。
江戸時代の北前船により北海道の昆布が日本海側の各地を経由して運ばれるようになり、特に富山県で消費されるようになったのですね。
慶広は、さらに同年11月、今度は次男の松前忠広を連れ、大坂城の家康を訪ねました。
家康は蝦夷の地理や蠣崎氏の系譜について尋ね、慶広は地図や系図を示しながら説明したそうで、家康との関係が確実に構築されたことを伺わせます。
そしてこの年、慶広は蠣崎から”松前”と改め、以降は松前氏として存続していきました。
松前城を建造
慶長五年(1600年)4月に松前へ戻り、夏からは新たな居城・福山城(松前城)の建造を開始。
同年6月には嫡子の松前盛広に家督を譲り、将来に向けて着々と準備を進めていきます。

冬の松前城
関ヶ原の戦いやそれに関連した戦には参加せず、やはり中央政府に関する欲がほとんどないことが浮かんできます。
松前盛広も父に倣い、里村玄仍(げんじょう・里村紹巴の子)の連歌会に参加したり、家康の近辺に留まったり、中央の情報収集に努めていきました。
そのため国元にはあまりおらず、慶広が留守を預かる形が定着。
家督を譲ったのも、最初からこうするつもりだったからでしょう。
これらの方針が好感を得てか、関ヶ原の戦い後の慶長九年(1604年)、家康は改めて松前氏にアイヌ交易独占権を認めました。
これにより、松前氏が得たアイヌの珍品が家康や将軍家、公家などに贈答されるようになっていきます。
慶長十五年(1610年)4月に家康が薬の材料としてオットセイの皮を所望し、慶広がさっそく取り寄せて献上したこともありました。
こうして将軍家の信頼を確実に勝ち得たと感じたのか。
江戸時代に入ったあたりから慶広は東北の大名たちとも親交を結ぶようになります。
津軽氏・佐竹氏・伊達氏などが相手で、特に伊達氏には七男の松前安広を家臣として仕えさせるほど。
当初は前田氏にも五男の松前次広を養子として入れる予定だったそうですが、当人が若くして亡くなってしまったため、実現せずに終わっています。
大坂冬の陣を前に四男・由広を斬る
こうして中央と距離を保ちつつ、自らの権利を確立した松前慶広。
晩年は家中の混乱に悩むことになってしまいます。
跡を継がせた長男の松前盛広が慶長十三年(1608年)、38歳の若さで亡くなってしまったのです。
武家の早逝はお家騒動フラグ――と思いきや、息子の盛広は嫡男となる松前公広を残しており、慶広がその“孫”を後見して家を守ることとなりました。
まだまだトラブルは終わりません、
今度は慶広の四男・松前由広が、大坂冬の陣を控えて東西緊張していた局面で、非常にマズい事態に陥ってしまいます。
豊臣家の片桐且元や大野治長に接近していることが発覚したのです。
片桐且元は、徳川と豊臣の間に立ち交渉を担っていた武将ですが、大野治長は淀殿の側にいる大坂方の要の一人。

大野治長/wikipediaより引用
松前由広との関わりが表沙汰となれば、松前藩全体に累が及ぶリスクは否めません。
いかに対処すべきか?
慶広は極めて果断に動きます。
慶長十九年(1614年)の末、家臣に命じて松前由広を斬らせたのです。
松前藩がいくら遠方といえど……いや遠方だからこそ、「豊臣との関わりなどあってはならない」と慶広も即断したのでしょう。
自身は、翌慶長二十年(1615年)、夏の陣に参戦し、きっちりと徳川方の武将であることを武働きで示します。
こうして不穏な状況をどうにか回避しながら、慶広が亡くなったのは元和二年(1616年)10月12日のこと。
享年69でした。
先立って同年4月、家康はすでに亡くなっており、松前にいる慶広にはその報せが5月に届けられていました。
慶広はその日の夜に出家し、その後、徐々に弱って背中に癌もでき、10月に息を引き取ったとされます。
あまり表立って語られることはありませんが、慶広は、年齢も近い家康に対して友情めいた近しい感情を抱いていたのかもしれません。
武力を使うところと使うべきでないところをきっちりと見極め、自分の欲っするものを欲張らずに勝ち取る――慶広の手腕は、現代人から見ても鮮やかの一言に尽きます。
有名な大名ではありませんが、学べるところが多い人物かもしれません。
あわせて読みたい関連記事
-

秀吉と敵対した最後の武将・九戸政実! 6万の大軍を相手に九戸城5千で籠城す
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

なぜ松前藩は石高ゼロでも運営できたのか?戦国期から幕末までのドタバタな歴史
続きを見る
-

松前城は単なる1万石の城にあらず~鎖国で潤う超リッチな藩だった
続きを見る
-

幕末に外様から老中へ異例の大出世をした松前崇広!最後は失意の失脚に追い込まれ
続きを見る
【参考】
遠藤ゆり子/竹井英文『戦国武将列伝1 東北編』(→amazon)
国史大辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)
世界大百科事典