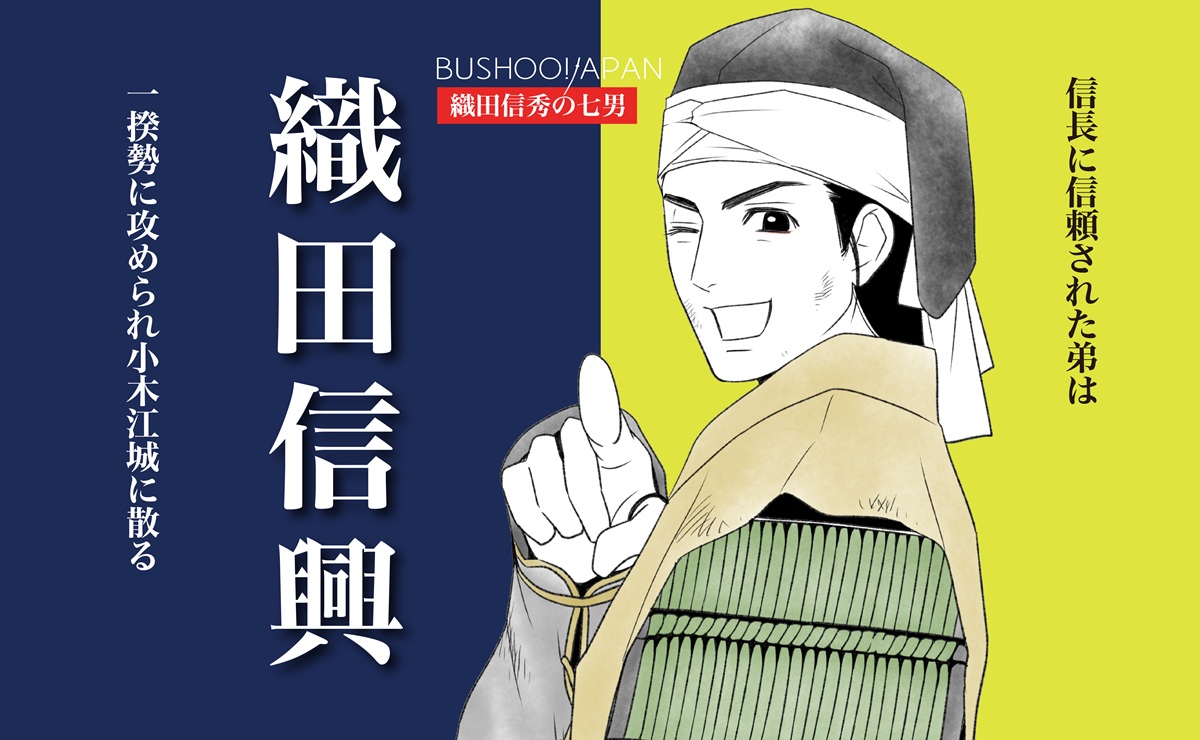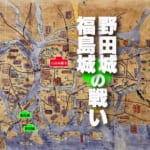天正元年9月26日(1573年10月21日)は信長が伊勢長島の一向一揆勢を攻撃した日。
いわゆる長島一向一揆であり、宗徒2万人を虐殺した事件として有名であろう。
しかしこの争い、ただ単に信長がか弱い一般人を嬲り殺したというわけでもない。
実は戦いは、都合三度にわたって展開されており、
①元亀2年(1571年)5月
②天正元年(1573年)9月
③天正2年(1574年)7月
少なくとも二度目までは一揆勢が優勢だからこそ信長も撤退を余儀なくされ、織田軍も相当な犠牲者を出していた。
その最初の犠牲者が、信長の弟・織田信興(のぶおき)である。
なぜ信興は死に追い込まれたのか。
当時を振り返ってみよう。

織田信興イメージ(絵・小久ヒロ)
父は信長と同じ 信秀の七男・織田信興
織田信興は、信長と父を同じくする織田信秀の七男とされる。
母は不明。
通称は彦七郎で、生年も事績もほとんど不明だが、家督継承後の信長が周囲の親類と争いを繰り広げる尾張統一の戦いの中で、信興は早い段階から付き従っていたとされる。
各国へ勢力を広げる織田信長にとってみれば大切な、信頼できる弟であった。
ゆえに最前線へ配置されたのであろう。
そのことを確認するため以下の地図をご覧いただきたい。
まずは右側の黄色い拠点が信長サイドの拠点・清州城(※このとき信長の本拠地は岐阜城)。
そして左側の黄色い拠点が織田信興に任された小木江城(こきえじょう)である。
一方、そのすぐ下にある赤色の拠点が一揆勢の長島城であり、木曽川・長良川・揖斐川(いびがわ)が合流して伊勢湾に注ぎ込む、中洲に建っていた。
周囲には十数ヶ所の城砦(じょうさい)も設置され、天然の巨大要塞とも言えるだろう。
つまり一揆勢はガチガチに守りで固めており、それだけに小木江城も、対伊勢方面の最前基地として非常に重要で危険な立ち位置にあった。
実際、最初に攻撃を仕掛けたのは一揆勢だった。
信興 天守へ登り自害で散る
元亀元年(1570年)11月、長島勢が織田信興へ攻撃を仕掛けたとき、織田家は大ピンチに陥っていた。
織田軍の主力は石山本願寺と対峙(1570年8-9月)。
ほぼ同時に浅井長政と朝倉義景の連合軍に攻められ、さらには比叡山延暦寺まで加わって敵対するなど(1570年9-12月)、いわゆる【第一次信長包囲網】という苦境に立たされていたのだ。
◆1570年8-9月石山本願寺を相手にした合戦→【野田城・福島城の戦い】
◆1570年9-12月浅井・朝倉・延暦寺と対峙→【志賀の陣】
とても動ける状況にない信長。

織田信長/wikipediaより引用
石山本願寺としては、織田軍の背後を脅かしたい。
ゆえに長島一向一揆勢に参戦を呼びかけ、信長のお膝元である隣国の尾張を攻めさせることにした。
その最初のターゲットになったのが織田信興の守る小木江城。
戦いは数日に渡り、信興も徹底抗戦した。
しかし、ついに城内への突入を許してしまい、信興は「一揆勢の手に掛かって死ぬのは無念」として天守に登り、自害へ追い込まれた。
こうなると織田家も崩壊のピンチでは……と思われるところだが、信長は、同年10月に石山本願寺の顕如と和睦を締結。
むろん一揆勢との戦いは始まったばかりであり、その続きは「長島一向一揆の全貌」をご覧いただきたい。
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

野田城・福島城の戦い(第一次石山合戦)|信長公記第73話
続きを見る
-

森可成の生涯|信長が頼りにした織田家の重臣 蘭丸の父は壮絶な最期を迎える
続きを見る
参考文献
- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)
出版社: 吉川弘文館(国史大辞典公式案内ページ) - 太田牛一/中川太古(現代語訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫)』(KADOKAWA, 2009年6月, ISBN-13: 978-4046000017)
出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線(歴史新書y 49)』(洋泉社, 2010年7月, ISBN-13: 978-4862486165)
出版社: 国立国会図書館サーチ |
Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録 ― 桶狭間から本能寺まで(中公新書)』(中央公論新社, 2002年12月, ISBN-13: 978-4121016379)
出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち』(中公新書ラクレ, 2012年10月, ISBN-13: 978-4121504210)
出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(吉川弘文館, 1995年11月, ISBN-13: 978-4642027410)
出版社: 吉川弘文館(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年11月, ISBN-13: 978-4642013444)
出版社: 吉川弘文館(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ