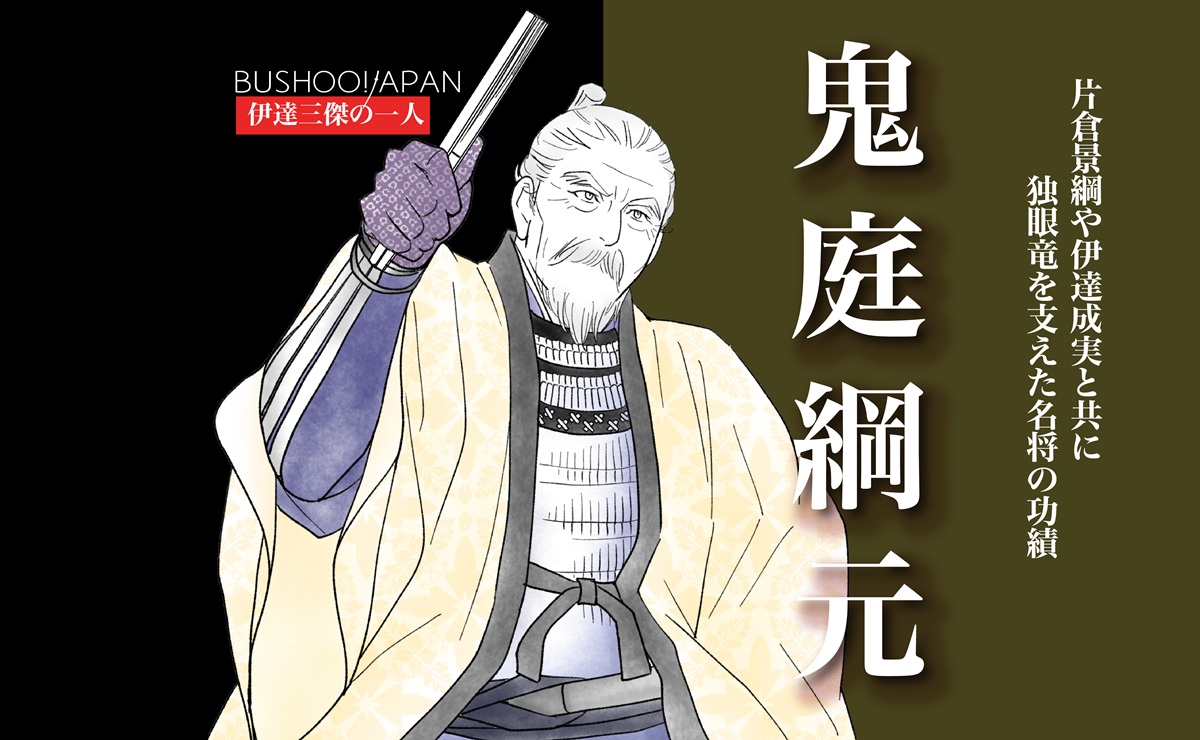こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【鬼庭綱元の生涯】
をクリックお願いします。
小田原参陣で綱元に弱音を吐く政宗
名前からしていかにもな猛将を想像してしまいがちな鬼庭綱元。
実際は文官タイプだったのです。
残された逸話も政治に関するものが多く……まず人取橋の後に鬼庭家の家督を継ぐと、天正十四年(1586年)に伊達家奉行職となり、翌天正十五年(1587年)には5000石を与えられました。
江戸時代の伊達家では”奉行”が他家の”家老”にあたりますので、おそらくこの時代でも同様だと思われます。
自分の家を継いで一息つく間もなく、主君を補佐する柱とみなされたわけです。かなり忙しそうですね。
その間、政宗は版図を広げるべく戦や外交に邁進していましたが、それに待ったをかけたのが豊臣秀吉でした。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
関白となった秀吉は、
「今後ワシに断りなく武力行使をすることは許さん」
という意味の【惣無事令】を出したのです。
政宗は当初これを聞いていないフリをし続けました。
しかし「関白が大名たちを動員して小田原を攻めるらしい」という話になってくると、いい加減、無視できない状況になってしまう。
どうすべきか――。
政宗も悩んだでしょうが、伊達家臣たちも「交戦するか従属するか」で揉めに揉めていたとされます。
その最中と思われる時期、政宗は綱元への書状で、こんな心中を吐露しています。
「関白とのことがうまく行けばいいのだが、もしうまく行かなければ切腹することになるだろう。討死や切腹は本望だが、このことで頭がいっぱいだ」
政宗は傅役の片倉景綱の邸に行き、景綱からの忠告に耳を傾けます。
「関白の軍はハエのようにいくらでもわいてくるでしょうから、一度追い払ったところで意味がありません」
「伊達家をまとめるためには一度頭を下げて好機を待ったほうがよろしいかと」
つまり選択肢は、始めから一つしかなかったんですね。
鬼庭綱元と片倉景綱
かくして小田原への参陣を決めた伊達政宗。
数多いる家臣の中でも、本当に親しくて信頼できたのが鬼庭綱元と片倉景綱だったのでしょう。

片倉景綱/wikipediaより引用
なお、他に相談できる人はいなかったのか?
というと、当時の伊達家はこんな状況でした。
・父の輝宗→既に他界
・父時代からの重臣である遠藤基信→輝宗に殉死
・輝宗の兄弟(政宗の伯叔父)たち→ほぼ他家へ養子に出ている
冒頭で触れた三傑のもう一人・伊達成実は政宗の1歳下であり、しかも抗戦派だったので、弱気なところを見せるわけにはいかなかったでしょう。
また同時期に起きた政宗暗殺未遂→小次郎暗殺事件についても、政宗は手紙で真意を語っており、これもおそらく綱元宛と考えられています。
やはり年長者である綱元の安心感があるんですね。
小次郎暗殺については、まとめるとこんな趣旨のことが記されていました。
「俺に毒を持ったのは母だと思う」
「おそらくは小次郎を擁立するためだったのだろうが、このままでは家が割れてしまう」
「それを防ぐには、可哀想だが弟を殺すしかない」
「母の無事を願っている」
「これらのことを俺から言うわけにはいかないので、お前の裁量でそれとなく世間へ広めておいてほしい」
この手紙などから、かつて母・義姫が政宗を毒殺しようとしていた説が長らく信じられてきましたが、近年では別の見方が有力視されています。
「義姫の出奔はこの事件の4年後だから主犯じゃないのでは?」
伊達家の家臣のうち、最上か周辺大名に近い者が勝手にやったのかもしれませんね。
さらに「この暗殺未遂そのものがなかったのでは」という説もありますが、綱元の話から離れすぎてしまいますので、ここまでにしておきましょう。
綱元一世一代の奉公
小田原で秀吉と対面したことで、ひとまず命を助けられた伊達政宗。
その後、行われた【奥州仕置】を経て、伊達家は旧領に押し戻される形となりました。
これまでの時間や流した血の多さを考えれば、政宗や伊達家臣たちが引き下がりたくないと思うのも無理ない話。
【大崎・葛西一揆】で蒲生氏郷らが鎮圧にやってきた時、
「政宗が一揆を扇動しているのではないか」
という疑いがかかりました。

伊達政宗(右)と蒲生氏郷/wikipediaより引用
この件については、
「本物の私の書状であれば、花押のセキレイの目に針で穴を開けてあります」
と弁明し、秀吉がそれを信じたため許されたという逸話が有名ですね。
しかし、現代まで残っている政宗の書状で”セキレイの目”は全く見当たらず、逸話自体が創作か、秀吉と一芝居打ったかのどちらかだろうとされています。
では、なぜ政宗は許されたのか?
というと、そこで浮上してくるのが鬼庭綱元――上方へ派遣され、政宗の意図や伊達家の潔白を訴えたのです。
政宗はこの件について綱元を送り出す際の書状で
「綱元一世一代の奉公は今このときだ」(意訳)
と記しており、伊達家の命運を託していたことが伝わってきます。
秀吉から、徳川家康や羽柴秀次、佐竹義宣、石田三成などに対し、一時は「政宗討伐の準備をするように」という命令が出た程でしたので、事態はかなり深刻でした。

石田三成/wikipediaより引用
それが以下のような条件で助けられています。
・政宗本人の弁明
・「政宗に逆心はなかったようです」という蒲生氏郷の報告
・氏郷の要望に応じて伊達成実が人質となる
時期は不明ながら、鬼庭綱元は秀吉にも相当気に入られていたようで、こんな逸話があります。
あるとき秀吉が綱元に尋ねました。
「お前の家は長寿の家系だというが、何か秘訣はあるのか?」
「特段秘訣というほどのものはありませんが、『朝晩米を溶かした湯を飲むようにせよ』という家訓がございます」
果たしてそんな家訓が本当にあったのか。
綱元ほど賢い人ならば、秀吉の追及から逃れるため、その場で考えた方便かもしれません。
実際、秀吉はこれを聞いて自分も真似したそうですが、長命というほどではないですしね。
まったくの嘘だったのか、あるいは体質の問題だったのか。因果関係は不明ですが、政宗が亡くなる間際にも「侍医が米粉を溶いた飲み物を飲ませようとした」ことが『木村右衛門覚書』に記されています。
長寿の秘訣かどうかはさておき、伊達家では養生食と見なされていたのかもしれませんね。
※続きは【次のページへ】をclick!