源頼朝からのお墨付きを得て会津地方の統治者となった佐原義連(さわらよしつら)。
その子孫が土着して蘆名家となり、長い間、同地方を統治してきた――その詳細が以下の記事にありますが、
-

東国武家にとって因縁深い会津の地 佐原義連に始まる蘆名一族と共に振り返る
続きを見る
戦国時代に突入すると、野心あふれる男の出現によってその安寧は崩されます。
独眼竜こと伊達政宗です。
中央では豊臣秀吉の政権がほぼ決まり、大名同士の勝手な合戦を禁じる「惣無事令」も出しているという状況なのに、それを完全に無視したかのように会津を攻め、蘆名から奪い取る――。
なぜ政宗はそこまで執着したのか?
いったい会津の何が魅力的だったのか?
フィクションでは「天下も狙っていた」と喧伝されがちな政宗ですが、実は会津に執着していた――その行動履歴を振り返ってみましょう。

伊達政宗/wikipediaより引用
はしゃぐ政宗「ついに会津を手に入れた!」
豊臣秀吉の影がそこまで迫っている――。
にもかかわらず、伊達政宗は、斜陽の蘆名家とは対照的な、楽しい戦国ライフをエンジョイしていました。
その姿は、まさにノリノリ。
撫で斬り自慢書状を最上義光に送りつけたり。
浮かれて落馬骨折したり。
彼氏と激しく愛し合って、愛の証のために太ももを突いたり。
飲みすぎて二日酔いになったり。
家臣に雑な手紙を送りつけたり。
家臣の家に突撃訪問して遊んだり。
伊達成実から「マナーが悪い!」と怒られたり。

伊達成実/wikipediaより引用
もう戦国の青春ここにあり!って感じですね、ハハッ。
まぁ、そんな政宗のエンジョイ青春時代の念願が会津蘆名家の撃破であり、その夢が叶ったのですから浮かれるのも無理はないでしょう。
天正18年(1589年)の1月7日に行われた「七草連歌」。
「若菜連歌」とも呼ばれる伊達家恒例の行事で、この年の政宗は次のような句を詠んでいます。
「七種を一葉によせてつむ根芹」
「七草を一気に積んじゃったよ、ウヒャハー!」
ウキウキの様子がダダ漏れで伝わってきます。
微笑ましいほどのノーテンキです。
しかし、戦国ファンの皆様なら、そろそろ気になられているでしょう。
伊達家ファンの方であれば、ヤキモキする場面です。
翌年の天正18年(1590年)は【小田原征伐】が行われる年。
秀吉の天下統一事業の仕上げは刻一刻と迫っているのでした。
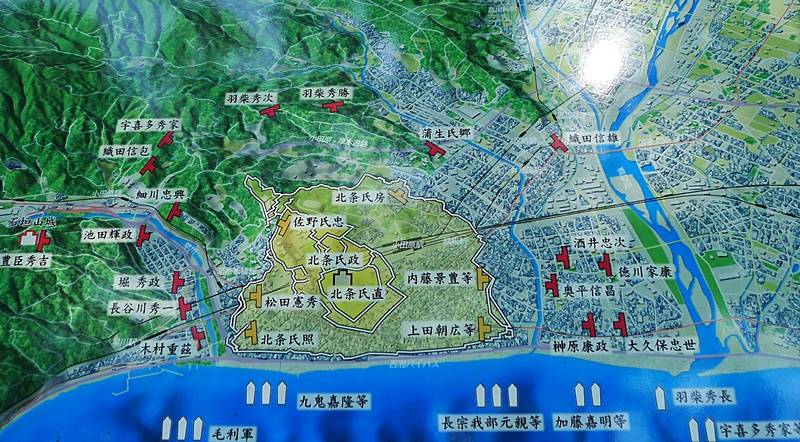
photo by R.FUJISE(お城野郎)
困り顔の義光「惣無事令を知らんの?」
秀吉が関東にやってくる頃。
それはもはや戦国時代ど真ん中の頃とは勝手が異なります。
好き勝手に暴れられる時代は終わり、外交力が切実に問われる環境になっておりました。
政宗周辺の大名――特に伯父の最上義光あたりは、ツッコミたくて仕方のないところでしょう。

長谷堂合戦で直江兼続を追撃する最上義光『長谷堂合戦図屏風』/wikipediaより引用
「あのさ……政宗くん、惣無事令って知らんの? そういうイキリ倒したこと(蘆名討伐)をして、関白が見過ごすと思っているの?」
むろん秀吉が黙っているはずがありません。
会津を追い出されて常陸にいる蘆名義広だって、実家の佐竹義重や佐竹義宣を介して、関白・豊臣秀吉に「惣無事令の違反です」と訴え出ていることでしょう。
秀吉の耳に入るのは時間の問題なのです。
奥羽の大名は誰もが皆
「どうすれば関白にコンタクトを取れるのか?」
と知恵を絞っているところでした。
好例が津軽為信や蠣崎慶広でしょう。

津軽為信/wikipediaより引用
関白への取りなしを電光石火で成功させたがために、無事、大名としての地位を得ました。
もっとも津軽はこの一件で南部とは犬猿の仲となっておりますが、出し抜いた方としては「合戦? もう外交なんだよ、アホか」という時代です。
このとき、一番胃がキリキリしていたのは、最上義光でしょう。
彼は伊達家の監視任務を買って出ています。
義光が陰険な性格だからなのか?
そんな単純なものではないでしょう。なんせ伊達家は最愛の妹の嫁ぎ先でありますし、義光は義弟の伊達輝宗とはなかなか相性がよかった。

伊達輝宗/wikipediaより引用
政宗だって、なんだかんだで血の繋がった甥っ子。何かあれば首根っこつかんででも土下座させたかったのかもしれません。
むろん政宗もバカではありません。
外交において無策ではなく、コンタクトもしておりました。
※続きは【次のページへ】をclick!

