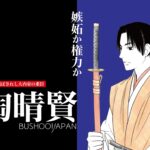こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【吉田郡山城の戦い】
をクリックお願いします。
一隊が囮役 二隊を伏兵に……作戦的中!
城に領民と共に籠もった毛利勢を見てか。
尼子軍は、気長に構えるつもりだったようで、9月15日に風越山に布陣してから一週間ほどは城下に火を付け、それを防ごうとして出てくる毛利方と小競り合いになるという状況でした。
9月23日には風越山から吉田郡山城南方の光井山に陣を移しています。
光井山は標高371mなので吉田郡山城よりも低い山です。
吉田郡山城へ攻めかかるつもりで陣を移したのでしょうか。
するとその動きを見た元就が、すかさず手薄になった風越山の尼子軍に襲いかかりました。
さらに9月26日には大内から来た援軍の先鋒が尼子方の湯原宗綱と戦闘となり、宗綱は深田に馬の足を取られて討死します。
徐々に動いていく戦況――尼子軍は10月11日、放火をしながら吉田郡山城へ近づき始めます。
元就は兵を三手に分けると、そのうち二隊を伏兵にし、残り一隊が囮役となって元就自らが率いることにしました。
ここでも元就が将兵の信用を買おうとしていたことがうかがえますね。いつの時代も、いざというときに一番キツイ役を引き受ける人が一番信用されるものです。
作戦は見事に的中しました。
元就隊と尼子軍が数刻戦った頃合いを見計らって、伏兵の二隊が尼子方の左右から襲撃し、実に500人もの損害を与えたといいます。
毛利軍の強さは「機が熟するまで粘り強く待ち、機が来たら迷わず動ける」ところといえるでしょう。
大内氏の援軍
一方その頃、大内義隆も毛利救援の下準備を着々と進めていました。

大内義隆/wikipediaより引用
陶隆房を先行させると、隆房は12月3日、吉田郡山城の東側・住吉山に陣を置いています。
元就は隆房に礼を述べ、年明けに尼子軍へ総攻撃をかけることを約束。
陶隆房とは、後の陶晴賢のことでして、この15年後に二人が【厳島の戦い】で激突することを考えると、諸行無常といった感がありますね。
一方、尼子軍は夏からの長滞陣で兵糧の確保や寒さに難儀しつつありました。
こうなると焦りも生まれてくるものです。
天文十年(1541年)の年初から毛利軍がたびたび尼子方の陣を襲撃するようになりました。
毛利軍にも損害は出ましたが、尼子軍への精神的プレッシャーはそれ以上の効果があったでしょう。
さらに陶隆房が尼子軍の真正面に軍を移動させ、じりじりと圧力をかけていきます。
これは好機なり!
そう捉えた元就が、陶軍に総攻撃の開始を打診すると、隆房も了承。
両軍揃って1月13日早朝から尼子の陣を襲撃しました。
このときの毛利軍は、文字通り全軍での突撃だったため、城の留守には女子供や百姓だけだったとか。
武装させたり藁人形を歩哨に見せたりといった工夫はしたと思われますが、見通しの悪い山城だからこそできた作戦だったのでしょう。
襲撃された側の尼子軍も応戦します。
しかし、兵だけでなく武将の討死や逃亡が相次ぎ、最終的に200名以上の討死を出したばかりか、陶隆房軍に本陣の背後をつかれて、総大将の尼子久幸まで討たれてしまうのです。
久幸が粘っている間に各方面に散っていた尼子軍の生存者たちは、這々の体で雪の中を撤退していきました。
大内氏からの援軍があったとはいえ、寡勢で山陰の雄・尼子氏を追い返した元就の戦略は見事の一言。
この勝利によって毛利元就の武名はさらに高まるのでした。
あわせて読みたい関連記事
-

中国地方8カ国を制した戦国大名・毛利元就の生涯~稀代の謀将が描いた戦略とは?
続きを見る
-

西の桶狭間と呼ばれる有田中井手の戦い|初陣の毛利元就が兵数5倍の敵を撃破
続きを見る
-

厳島の戦いで毛利軍の奇襲が炸裂! 陶晴賢を破って元就が中国地方の覇者へ
続きを見る
-

なぜ戦国時代の大内家重臣・陶晴賢は下剋上を起こし最終的に毛利に滅ぼされたのか
続きを見る
-

元就の長男・毛利隆元はどんな武将だった? 失って初めて実感する跡取りの偉大さ
続きを見る
【参考】
河合正治編『毛利元就のすべて』(→amazon)
『「毛利一族」のすべて (別冊歴史読本―一族シリーズ (92))』(→amazon)
森本繁『<毛利元就と戦国時代>知将・元就 版図拡大の軌跡を追う (歴史群像デジタルアーカイブス)』(→amazon)
国史大辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)