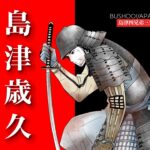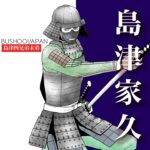こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【島津貴久の生涯】
をクリックお願いします。
南蛮とは付かず離れず?
ひとつめはポルトガル船の漂着による鉄砲伝来です。

種子島火縄銃/photo by wikipediaより引用
鉄砲は種子島 (たねがしま) に流れ着いたポルトガル商人から、同島の主・種子島時尭に売られ、島内の刀鍛冶によって国産化に成功していました。
その一部が島津にももたらされたというわけです。
鉄砲伝来については種子島に辿り着いただけではなく、諸外国との交易があったエリアでは自然と流入してきたという指摘もあります。
一方で「国内の合戦で初めて鉄砲を使ったのは島津貴久だ」という説もあり、いずれにせよ早い段階から実践に投入した慧眼があったのは間違いないでしょう。
島津で鉄砲というと、他にも義弘による【島津の退き口】で使われたり、貴久の孫にあたる島津忠恒(義弘の子)が家臣を暗殺させたり、なかなか強烈な象徴的シーンもありますね。
ふたつめは、天文十八年(1549年)にフランシスコ・ザビエルが来日したこと。

フランシスコ・ザビエル/Wikipediaより引用
貴久は西洋の文物に興味を持ち、キリスト教の布教も許すも、翌年には禁教へ切り替えています。
当初のキリスト教は仏教の一種だと勘違いされていたので、おそらく貴久もそのように扱うも、後から「なんか違うぞ」と気づいたのかもしれません。
もしくは何らかの実害が出てしまったか。
ザビエルの方でも、島津氏の菩提寺・福昌寺の住職だった忍室と親交を結んでこんなことを語ったとされます。
「忍室ほどの学識がある人でさえ、キリスト教における魂の不滅を理解してもらえない」
結局、薩摩を去ることになったザビエルは、仏教の方便(一人ひとりの性質に応じて、教える側が話す内容を変えること)が理解できなかったようで。
「忍室は霊魂が不滅だと言ったりそうではないと言ったりする」
そんな風に困惑していたようです。
あくまで西洋との貿易だけに興味を持っていた貴久としては、布教の許可も直結するカトリックを受け入れられなかったんですね。
円滑な継承
宗家の家督を継ぐ上で混乱の時期を経験したせいか。
島津貴久は早めに長子の島津義久に家督を譲ったとされます。
永禄九年(1566年)前後のことで、その後、貴久は同じく出家していた島津忠良(日新斎)のいた別府城(南さつま市)に移り、しばらくは戦に関与し続けました。
まだ島津に対抗する国衆がいて、四兄弟だけでは手を焼いたためです。
そして貴久は元亀二年(1571年)6月23日に亡くなります。
実は島津は、この時点でまだ薩摩統一を果たしておらず、息子たちの代までもつれこんでいます。
それでも忠良と貴久は、二人で義久たち四兄弟の地盤作りをしたことになるため、二人とも「中興の祖」といわれるようになりました。
こうした流れを踏まえると、大河ドラマ『戦国島津三代』みたいな長編ドラマも非常に面白そうですよね。
島津四兄弟(特に義弘)が大河にならないのは「文禄・慶長の役で問題になるおそれがある」という説も根強くあるようですが、果たして実情はどうなのか。
ぜひ一考していただきたいものです。
あわせて読みたい関連記事
-

戦国大名・島津義久の生涯~薩摩から九州制覇を目前にして秀吉に敗れた無念
続きを見る
-

鬼島津と呼ばれた戦国武将・島津義弘の生涯~関ヶ原を突破し薩摩の礎を築いた勇将
続きを見る
-

薩摩で戦の神と称される戦国武将・島津歳久の生涯~秀吉に矢を放ち最後まで抵抗
続きを見る
-

薩摩最強の戦国武将・島津家久の生涯~次々に大軍を撃ち破った軍神の戦績とは?
続きを見る
-

薩摩の猛将・新納忠元|文武両道で涙もろい忠義者の生涯が熱い!
続きを見る
【参考】
新名一仁『戦国武将列伝11 九州編』(→amazon)
峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)
『戦国武将事典 乱世を生きた830人 Truth In History』(→amazon)
浅見雅一『フランシスコ=ザビエル 東方布教に身をささげた宣教師』(→amazon)
国史大辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)
日本人名大辞典