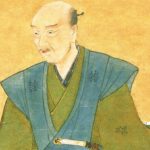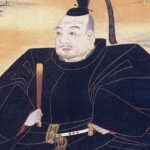戦国武将にとって一番大切なことは、自分の家を残すこと。
群雄割拠の状態から織田→豊臣→徳川政権へと移り変わる中で、それは非常に困難なことでしたが、この難事を成し遂げたにもかかわらず知名度や評価が低い人物は珍しくありません。
慶長十六年(1611年)4月7日に亡くなった浅野長政も、まさにその典型例でしょう。
豊臣五奉行の筆頭でもありながら、立場的には格下であるはずの石田三成よりも目立たず、フィクションなどでもあまり話題にのぼらないのは一体なぜなのか。
その生涯を振り返ってみましょう。
なお、当人は「長吉」と名乗っていた時期のほうが長いのですが、「長政」で語られるほうが多いためこちらで統一します。

浅野長政/wikipediaより引用
命日は4月6日説と7日説があり、今回は7日として進めて参りますので、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
生い立ち
浅野長政は天文十六年(1547年)、尾張国の春日井郡に生まれました。
織田信長のお弓衆であった浅野長勝の養子となり、その娘・ややと結婚、秀吉の正室・ねねとは義姉弟という関係になっています。
これが彼の名を後世に残す出発点となりました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
余談ながら、長政の”長”も”政”もこの時期の人名によく使われた文字であり、同名の人物が戦国時代だけで四人もいます。
・浅井長政(信長妹でお市の方の夫)
・黒田長政(黒田官兵衛の息子で福岡藩初代藩主)
・池田長政(池田恒興の息子)
・浅野長政(豊臣秀吉の義弟)←今回の注目
織豊政権時代にもう一人の長政がいたら、戦国鍋TVなどのパロディ番組で「ナガマサファイブ」とか「◯◯戦隊ナガマサン」とか作られていたかもしれませんね。
と冗談はさておき、こうした著名な長政に囲まれている上に、元の身分が低く、猛将タイプでもないという三拍子が揃っている浅野長政の知名度が低いのは致し方ないことかもしれません。
京都奉行を任され
互いの妻の縁から秀吉の配下に組み込まれた浅野長政。
何だかややこしいことに、天正元年(1573年)の小谷城の戦いにも参加しています。
浅井長政の本拠地であり、秀吉が大きな武功を挙げた合戦ですね。

浅井長政/wikipediaより引用
秀吉がここの主になると、長政も近隣に領地をもらいました。
統治の才能は早くから評価され、順調に加増されてゆき、出世を果たしてゆきます。
悲しいかな、戦場での目立ったエピソードがなくそれが印象の薄さに拍車をかけていると先ほど申し上げましたが、時計の針を一気に進めて【本能寺の変】後に注目しますと、杉原家次とともに京都奉行を任されるまでになりました。
2年後に家次が亡くなった際には、単独で京都奉行を任されますので、やはり実務能力は高かったのでしょう。
しかも同時期には近江の大津城ならびに坂本城の守備も任されます。
この頃には所領が2万石を超えており、大名の仲間入りを果たしていました。
若狭一国の国持大名へ大出世
浅野長政の重要な業務は他にもあり、豊臣家の兵糧や蔵米の管理を任されていました。
兵糧は軍用の食料で、蔵米は年貢として豊臣家に収められた米のことです。
現代風にいえば金庫番というのがわかりやすいでしょうかね。
こうした働きも評価され、天正十五年(1587年)には若狭一国を任されるまでになります。
天正十八年(1590年)の小田原攻略では、主将というよりも他の軍が支城を攻めているところに援軍に行く、という流れで活躍しています。
この流れで、石田三成と共に『のぼうの城』で有名な忍城の水攻めにも参加。

忍城
第一の担当者として名前が出てこないあたり、やはり地味な扱いにされてしまうんですね……。
あまり取り沙汰されることはありませんが、こういった役割は実力もさることながら、温厚な性格の人でないと中々こなせないものでしょう。
秀吉からすると、長政の人格も使い勝手が良いと判断されたのかもしれません。
むろん長政に全くミスがないわけではなく、命令違反で叱責されたこともありますが、小田原攻略に続く奥州仕置(奥州の大名に関する処置の総称)では、石田三成・大谷吉継らと共に奉行を務めています。
その流れで奥州諸大名との取次(他家との折衝役)も任されるまでになります。
しかし、秀吉の判断力が鈍るようになると、長政の立場も怪しくなっていきました。
立場が怪しくなる
なぜ豊臣政権は滅びてしまったのか?
衰微の一因と考えられるのが【文禄・慶長の役】でしょう。
ご存知、明を従えるために朝鮮半島へ攻め込んだこの大戦、文禄元年(1592年)に始まった文禄の役で浅野長政は石田三成と増田長盛と共に渡海しています。

文禄の役『釜山鎮殉節図』/wikipediaより引用
当初の秀吉は、自身も渡海するつもり満々で、三成もそれに賛成していたとされます。
しかし長政は強く反対しました。
歴史を知っている現代人からすれば長政が正解にも見えますが、当時はそんなことはわかりませんので、三成との関係が冷え始めたキッカケになったかもしれません。
ただし、これが原因で秀吉から干されるということはなく、文禄二年(1593年)には甲斐を与えられています。
関東や奥州へ睨みを利かせるだけでなく、旧支配者たる武田家旧臣たちに対する警戒も含まれていたでしょう。
既に武田家が織田家に滅ぼされてから10年経ち、徳川家などに再仕官した者もいましたが、いつの時代もお家再興を願う人はいますからね。
長政は上方にいることが多かったため、領地の管理などは息子・浅野幸長が担当しました。

浅野幸長/wikipediaより引用
秀次事件に連座して切腹の危機
文禄四年(1595年)、豊臣政権下の浅野長政にとって最大のピンチが訪れます。
関白・豊臣秀次の失脚事件です。
このとき長政は「秀次と親しかったから」という理由で、幸長と共に連座させられる寸前まで追い詰められました。
実際は、前田利家や徳川家康の取り成しで取り消されているので、そもそも強くは疑われていなかったのでしょう。
しかし、そんな不確かな状況で、切腹させられかけたというのは実に酷い話で……。
それでも文禄五年(1596年)に起きた慶長伏見大地震の際には秀吉の元へ駆けつけたというのですから、長政の人の良さというか、忠義心というか。
残念ながら、この地震では「地震加藤」という、これまた長政よりインパクトの強いエピソードがあるため、やっぱり目立たなくなってしまっています。
謹慎中の加藤清正が真っ先に秀吉のもとへ駆けつけた、という話ですね。

加藤清正/wikipediaより引用
長政には他にも涙ぐましい話が残されています。
慶長三年(1598年)に秀吉が危篤になってからも側に侍って秀頼の貢献者の一人になったり。
その一方でまだ続いていた朝鮮の役(慶長の役)に出ていた諸大名の軍を無事帰国させるために取り計らったり。
何かと豊臣政権で重責を担わされるのです。
他の武将より秀吉との縁戚関係が濃かったから当たり前……と思いきや、秀吉が亡くなり、いざ迎えた関ヶ原の戦いでは意外な身の振り方を選択することになります。
そう、家康側についているのです。
なぜそんなチョイスとなったのか?
奉行職からの解任と蟄居
なぜ浅野長政は、徳川家康率いる東軍になびいたのか。
慶長四年(1599年)9月にある事件が起きました。
徳川家康が【重陽の節句】のため大坂の秀頼と淀殿を訪れた際、家康の暗殺計画が発覚し、首謀者の一人として浅野長政が疑われたのです。

徳川家康/wikipediaより引用
そのため長政は、奉行職からの解任と隠居を強制され、国元の武蔵・府中での蟄居が言い渡されました。
異心のない証として、長政は家康のお膝元である江戸へ三男・浅野長重を人質に出します。
話が前後してしまいますが、慶長四年は豊臣政権終焉へのカウントダウンが始まった年でもあり、その流れを時系列にまとめるとこうなります。
閏3月3日 前田利家の死去
↓
直後、”七将”による石田三成襲撃未遂事件
↓
三成が奉行職を解かれ、佐和山城へ実質隠居
↓
9月 家康暗殺未遂事件
↓
10月 浅野長政らに対する処分が決まる
そして翌慶長五年(1600年)、上杉景勝に対する反乱の疑いで会津征伐が始まり、関ヶ原に繋がってゆくのです。

上杉景勝/wikipediaより引用
慶長四年で豊臣政権の吏僚を引き剥がし、同五年に武力をごっそり奪ったともとれますね。
家康の脳内にこれらの青写真が描かれたのはいつだったのか、恐ろしい話です。
関ヶ原の戦い
浅野長政は、福島正則などいわゆる”武断派”のように三成憎さで敵対したというわけでもなさそうです。
ゆえに中枢の動きによっては、西軍についていてもおかしくなかったでしょう。
なんせ長政は後年「三成が生きていた頃はマシだったのに」とぼやいた……なんて逸話も伝えられていますので、三成との個人的な確執はあまりなかったと思われます。
息子の幸長については、”七将”に含まれるとする見方があるため、バリバリに対立していたと思われますが……。
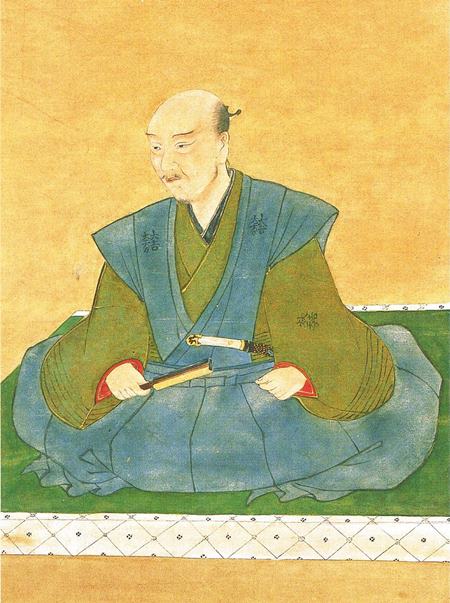
石田三成/wikipediaより引用
隠居したという名目もあり、長政は会津征伐や関ヶ原に従軍はせず、江戸城に残っていました。
幸長は家康本軍に従う形で東海道を進むも、合戦当日は南宮山で毛利軍と睨み合うことになり、大きな戦闘には直面していないようです。
それでも浅野家は、幸長が東軍の先鋒を見事勤め上げた功績で和歌山37万石に移封され、大きく躍進。
長政本人は家康の側で働くことを選んでおり、息子とは別に常陸真壁に5万石を与えられています。
異心がないことを示すためでしょうかね。
そして慶長十六年(1611年)の春、穏やかにその生涯を閉じたのでした。
長政最期の地は江戸と真壁、塩原温泉など諸説あります。
湯治を許されていたんでしょうか。
ここまでなら「ふーん」で済む話なのですが、彼の子孫には超有名人がいます。
名字でお気づきの方もおられるでしょう。
長政の三男・浅野長重の子孫が忠臣蔵(元禄赤穂事件)の当事者・浅野内匠頭長矩なのです。

浅野長矩/Wikipediaより引用
もしかして、こっちが有名すぎるせいで、ご先祖の影が薄くなっちゃってるんですかね……。
いずれにせよ、なんとも不憫なことです。
あわせて読みたい関連記事
-

関ヶ原の戦いは家康vs三成の本戦だけでなく全国各地で合戦が勃発【総まとめ更新】
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

石田三成の生涯|秀吉と豊臣政権を支えた五奉行の頭脳 その再評価とは?
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた
続きを見る
-

なぜ浅野内匠頭(長矩)は吉良上野介に斬りかかったのか 当人はどんな人物だった?
続きを見る
参考文献
- 菊地浩之『豊臣家臣団の系図(角川新書)』(KADOKAWA, 2019年11月9日, ISBN-13: 978-4-04-082325-6)
出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 渡邊大門『黒田官兵衛・長政の野望 ― もう一つの関ヶ原(角川選書 531)』(角川学芸出版, 2013年8月24日, ISBN-13: 978-4-04-703531-7)
出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ