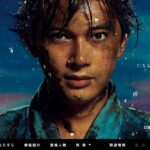享保十三年(1766年)2月14日は、水戸藩五代藩主・徳川宗翰(むねもと)が亡くなった日です。
水戸藩といえば御三家の一つ。
水戸黄門こと二代藩主・徳川光圀や、十五代・徳川斉昭とその息子である徳川慶喜など。
-

徳川斉昭は幕府を揺るがし滅ぼす問題児だった?そして水戸藩も崩壊の憂き目へ
続きを見る
-

だから徳川慶喜を将軍にしたらヤバい! 父の暴走と共に過ごした幼少青年期
続きを見る
幕末のアレコレでも話題に事欠かない家ですし、2021年大河ドラマ『青天を衝け』でもさらに注目度がアップすることでしょう。
しかし、その間のことって、あまり知られてないですよね?
今回はそこに着目してみました。
-

渋沢栄一には実際どんな功績があったか「近代資本主義の父」その生涯を振り返る
続きを見る
-

『青天を衝け』タイトルの意味は? 渋沢の漢詩が由来の2021大河ドラマ
続きを見る
光圀が大日本史に財を投じ過ぎてからの借金苦
当コーナーでも度々取り上げている通り、江戸時代の大名というのは、武家というより政治家としての仕事と立場を強く持っています。
そして、度重なる災害や借金のため、どこもかしこも家計は火の車。
「200年以上も平和だったのは、武士の皆さんがビンボーだったからなんじゃないの?」と思いたくなるような有様です。
御三家や将軍家ならその手のトラブルとは無縁かと思いきや、そうは問屋がおろしません。
-

御三家と御三卿って何がどう違う? 吉宗の創設した田安と一橋が将軍家を救う
続きを見る
特に水戸家の場合は、偉大であるはずの光圀、そしてその息子である三代・綱條(つなえだ)の時代に、転がり落ちるどころか自由落下レベルの財政難に陥っていました。
なんでそんなことになったのかといえば、答えは実にシンプル。
光圀が歴史書『大日本史』の完成を重視するあまり、編纂事業に多大なお金と人手を費やしたからです(TOP画像は大日本史の編纂が行われた彰考館跡・水戸市)。
悪化した財政を改善すべく、跡を継いだ綱條は水戸藩領内に運河を掘り、江戸との交通を便利にすることで、商業を盛んにしようと考えました。
しかし、よりによって農繁期に農民を駆り出した上、給料の支払いを渋ったために非難轟々。
その上年貢の取り立てを厳しくしたというのですから、これはもう自ら蒔いた種としか……畑仕事を滞らせておいて「米を出せ!」も何もないですよねぇ。アイタタタ(´・ω・`)
四代・五代と頑張ってはみたものの
綱條の次、四代藩主になったのは、初代・頼房の長子である松平頼重の血を引く宗堯(むねたか)でした。
何だかややこしいつながりですが、端折って言うと「黄門様のニーチャンの子孫」です。
当初は宗堯も松平姓で、綱條の養子になってから徳川姓になっています。
宗堯は藩主の座を継いだとき、まだ11歳でした。
幼い頃から英邁で知られており、かつ非常に真面目で責任感の強い人だったようで、自ら毎日の食事を一汁三菜とし、倹約に努めて財政改善を図っています。
しかし、まだ体が出来上がっていないような年齢のうちから粗食が常態化していては、健康によくありません。跡継ぎを残すことはできたものの、宗堯は24歳の若さで亡くなってしまっています。
その跡を継いだのが、息子である五代目の宗翰(むねもと)でした。
父親がこんなに早く亡くなったため、宗翰もまた若年で藩主の座に就くことに。
数えで3歳、満年齢で1歳という、若いよりも幼い、幼いというより乳飲み子同然のときから、藩主の重責を背負うことになったのです。
もしこれが徳川家綱~徳川家継(四代~七代将軍)の時代であれば、いかに御三家といえど、何かしらの処分があったかもしれません。
-

四代将軍・徳川家綱を地味将軍と言うなかれ 実は好感度エピソード満載な人だった
続きを見る
しかし、運良く、ときの将軍は八代・徳川吉宗。
リアリティと費用削減を身上とする吉宗は、水戸藩を処罰しませんでした。
-

徳川吉宗の生涯~家康に次ぐ実力者とされる手腕を享保の改革と共に振り返る
続きを見る
移封するにしろ、後釜の大名をどこかから連れてこなければなりませんし、手間とお金がかかりすぎます。
吉宗は水戸藩の家老たちを江戸城へ呼び、「家中一丸となって宗堯を守り立て、良い藩主になるよう育てよ」と直接命じました。
父の血と家老たちの教育により、成長した宗翰もまた、十代中頃から藩政改革を第一と考えるようになりました。
しかし、親族や家老とともにあらゆる策を講じたものの、そう簡単には行きません。
三十代後半になってからは、あまりの行き詰まりようで自暴自棄になり、酒や遊興にふけってしまうようになったといいます。
亡くなる二年前には水戸城が全焼するという追い打ちのような出来事もあり、すっかり気落ちしてしまったようです。
遅すぎた反抗期というか、真面目な人が歳取って道を踏み外すと歯止めがきかないというか……。
宗堯がせめて40歳くらいまで生きていて、宗翰が父から直接教えを受けたり、親子で協力して改革へ取り組んでいたら、もう少し良い結果になったかもしれません。
※続きは【次のページへ】をclick!