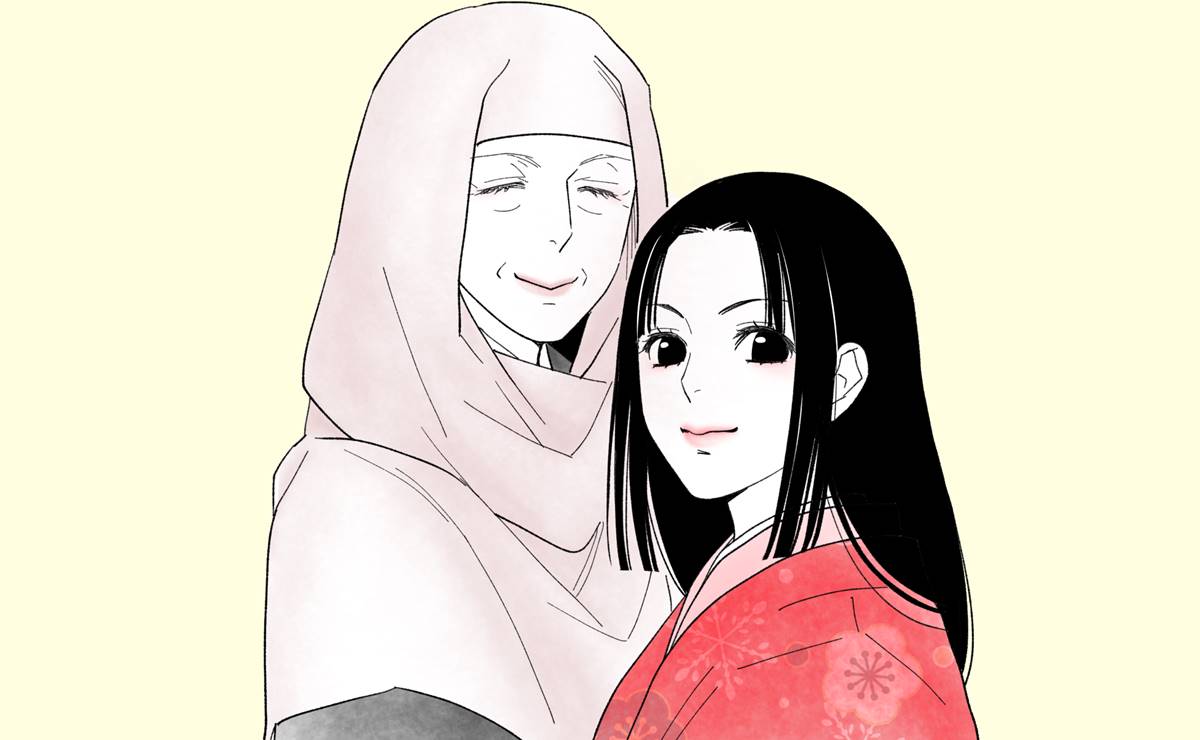こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【浄岸院(竹姫)】
をクリックお願いします。
悪条件のもと24歳でようやく
やっと行き先が決まったのは、竹姫24歳のとき。
当時の感覚では行き遅れもいいところです。
将軍も代替わりが進み、なんと八代・徳川吉宗の時代になっていました。

徳川吉宗/wikipediaより引用
お相手は島津家当主・島津継豊でした。
しかし、これもさまざまな方面から圧力があってのことで、島津家としては到底気分の良いものではなかったようです。
なんせ少し前に長男が生まれたばかりでしたし、吉宗と竹姫の仲がアヤシイというこれまた出所のほうが怪しい噂もありましたし、上記の不吉っぷりからしても島津家で気が進まない理由は揃いすぎていました。
ただ、島津にしても、正室を早くに亡くし、竹姫の出自については何ら問題がないこと。
そして六代・徳川家宣(いえのぶ)の正室だった天英院が実家の近衛家(公家)を通してまで縁談を持ちかけてきたため、ついに断りきれなかったとか。

徳川家宣/wikipediaより引用
それでも最後の悪あがきか。
「竹姫様に子供が生まれても跡継ぎにしませんからね!」等々、当時の基準でいえば「もうこれ諦めたほうが良くね?」レベルの条件をいくつも出してきます。
すると幕府が気前よくその条件を全て飲んでしまったため、竹姫を迎えざるをえませんでした。
竹姫が茂姫を将軍家へ嫁がせていたからこそ
竹姫に憑いていた(?)疫病神も「鬼島津」の血を前にして退散したのか。
彼女はここでやっと腰を落ち着けることになります。
夫婦仲はあまり良くなかったようです。
が、竹姫は子供が好きだったようで、側室の子供である宗信をわが子のように可愛がったとか。
また、こうした経緯からか「自分の役割は世継ぎをもうけるのではなく、将軍家と薩摩藩の仲立ちになること」と考え、宗信の正室探しの際に尾張家との縁談を進めたり(これは双方の早世で沙汰止みですが)、義理の孫にあたる重豪には一橋家の娘を迎えさせたり、外交官のような役割をしていました。
もちろん継室として宗信や重豪の教育もしており、その辺でトラブルになっていないところを見ると一応信頼はされていたようです。
亡くなったのは、嫁いでから四十四年後、62歳でした。
竹姫の最期の仕事は、島津重豪への遺言。
「あなたの娘の茂姫(しげひめ)を、徳川家斉様へ差し上げなさい」というものです。

徳川家斉/wikipediaより引用
この名前、聞き覚えのある方もいるのではないでしょうか?
ヒントは「大河ドラマ」ですね。
そう、幕末に活躍した女性の一人・天璋院篤姫の名前の元ネタで、彼女が将軍御台所になれた要因でもある人です。
茂姫という前例があるので、篤姫もOKということになったんですね。
なぜ茂姫のときはあっさりOKが出たのかというと、結婚した当初は徳川家斉が一橋家の人だったからです。
御三卿なら外様から正室を迎えても良いとかよくわからん理屈ですが、江戸幕府だから仕方ない。
つまり、竹姫が茂姫を将軍へ嫁がせたおかげで、篤姫も歴史に名を残したわけです。
当人達にとってはどうでもいいことかもしれませんが、後世から見ると
「元は行き先に困っていた公家の娘が、後々維新に大きく関係した武家の女性の運命を決めた」
わけで、なかなか感慨深いものです。
人間不遇な期間が長くなったからといって、腐ってばかりではいけないということですかね。
竹姫の日記とか手紙とか出てきたら面白そうなんですが、どこかにありませんかねえ。
あわせて読みたい関連記事
-

徳川綱吉は犬公方というより名君では? 暴力排除で日本人に倫理を広めた人格者
続きを見る
-

富士山の中腹に超ド級の穴を開けた宝永大噴火! 実は直前に大地震も起きていた
続きを見る
-

徳川吉宗の生涯~家康に次ぐ実力者とされる手腕を享保の改革と共に振り返る
続きを見る
-

在任3年で亡くなった六代将軍・徳川家宣は意外とデキる 白石を用いた政治改革へ
続きを見る
-

島津に暗君なし(バカ殿はいない)はどこまでマジなのか?薩摩藩主全12代まとめ
続きを見る
【参考】
国史大辞典
浄岸院/Wikipedia