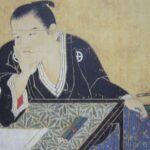こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【宝暦治水事件】
をクリックお願いします。
薩摩の借金は500万両に膨れ上がり
宝暦治水工事に要した費用は最終的に40万両にも上りました。
このうち靱負らが借金で工面した総額が22万両、薩摩での増税などによって調達したのが15万両、幕府が負担したのは9900両とされています。
さすがに酷いですよね。
莫大な金額を都合するため、薩摩ではサトウキビを強引に収めさせ、堺などの商人に渡すことでやりくりしていました。
サトウキビ農家からすれば、ただの強奪でしょう。
薩摩藩は靱負という大切な家老と藩士の多くが犠牲になっただけでなく、領内からの恨みも買うという散々な結果になってしまいます。
あまりにも代償が大きかった。
後年、将軍家との婚姻にかかる費用を押し付けられた薩摩藩の人が「宝暦治水の費用よりはマシ」と言ったことがあるとかないとか。
現代だったら大炎上しそうですが、そう愚痴りたくなる気持ちは理解できますね。
しかも薩摩藩では、宝暦治水事件と将軍家との婚姻により、最終的に借金は500万両にも上ったといいます。
そんな状況でよく幕末に躍進できたな?と思われるかもしれません。
実はこの借金、島津斉興の依頼により、調所広郷が「無利子250年払い」といった強引な返済計画を貸し手に呑み込ませるなどして、実質チャラにしています。

調所広郷/wikipediaより引用
こうまでして完了に漕ぎ着けた工事。
さて、その効果はどうだったのでしょう?
ヨハニス・デ・レーケが工事を指揮
残念ながら「工事は上手くいった」とは言えない状況でした。
上流地域では工事前より水害が増した地点もあったほどで、その後、完全に解決されるのは明治時代に入ってからになります。
お雇い外国人のヨハニス・デ・レーケが工事を指揮したのです。
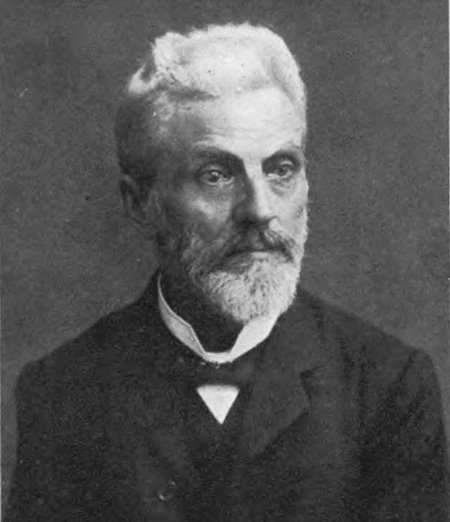
ヨハニス・デ・レーケ/wikipediaより引用
明治時代の三川分流工事は、国と岐阜・愛知・三重の三県によって工事と費用を分担。
当時の日本円で974万6000円かかりました。
こちらも現代の貨幣価値に換算するのは難しいので、明治時代の大きな工事と比較してみますと……。
鹿鳴館の建設費用18万円
敦賀線(米原-敦賀間)約20万円
鹿鳴館を54棟、敦賀線を48回作るのと同じくらいの費用がかかったんですね。
明治時代にそれほどの費用がかかり、お雇い外国人の力まで借りなければならない状況だとすれば、江戸時代に解決するのが不可能だったのも致し方ありませんね。
大正時代にようやく知られる
この悲劇は、幕府との関係や幕末のドタバタに紛れ、少なくとも大正時代あたりまで、地元鹿児島では全く知られていなかったとか。
1920年に鶴丸城の裏あたりに「薩摩義士碑」を設置。
事件の犠牲者を弔う碑が建てられ、ようやく鹿児島でも知られるようになってきたのだそうです。
岐阜県のお寺や神社でも、薩摩義士を葬ったところや、資料館を併設しているところがあります。
いずれかの地を訪れた際には、こういったところにも立ち寄って、悲嘆と無念のうちに亡くなった人々に手を合わせてみてはいかがでしょうか。
ただし、近年の伊勢湾台風などの大きな災害では相変わらず被害は出てしまいます。
最近はゲリラ豪雨などの局地的な災害も起きていますし、日頃から警戒を心がけておくしかありませんね。
みんなが読んでる関連記事
-

実は借金地獄でカツカツだった薩摩藩~武士も農民も苦しかった懐事情とは?
続きを見る
-

ボロボロの財政を立て直したのに一家離散の仕打ち~調所広郷が薩摩で味わった苦悶
続きを見る
-

斉彬と久光の父・島津斉興~藩財政を立て直し薩摩躍進の礎を築いた功績に注目
続きを見る
-

幕末薩摩の躍進を支え現代にも息づく集成館事業~島津斉彬はどう推し進めたか
続きを見る
-

屈強な藩士たちを作り上げた薩摩藩の食文化!唐芋・豚肉・焼酎など異国情緒な食卓
続きを見る
【参考】
安藤優一郎『江戸の給与明細』(→amazon)
木曽三川宝暦治水史料にみる「見試し」施工に関する研究(→link)
宝暦治水の回顧(→link)
海津市ホームページ(→link)
養老町の歴史文化資源(→link)
国史大辞典
世界大百科事典
日本大百科全書(ニッポニカ)