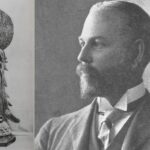こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【聖徳太子御火焚祭】
をクリックお願いします。
藤原氏ゆかりの大将軍神社や上御霊神社でも
藤原氏の祖先とされる、天児屋根命(あめのこやねのみこと)を含む大将軍神社も対象とされました。
天児屋根命は春日大社に祀られている神の一柱であり、天岩戸事件の際、占いをしたり祝詞を唱えたりしています。

春日大社
また、天孫降臨の際に瓊瓊杵命(ににぎのみこと)のお供をして地上にやってきたとされる神様です。
現代の会社でいえば社長秘書みたいなイメージですかね。
天児屋根命は元々、関東の鹿島神宮・香取神宮に祀られていたともされているので、藤原氏が「ウチのご先祖様は代々皇室のご先祖様のお供をしてきたんだぜ!」と強調する意味でこのような話を作った、とも取れますが。
天児屋根命のご利益の一つに「国家安寧」があるところがまたなんとも。
「ご先祖様、ちゃんと仕事をしますので、何卒お知恵をお貸しください」みたいな感じなら殊勝なことですけれども。
不幸な最期を遂げた人物が祀られる
興味深いのは、桓武天皇妃・藤原吉子らを祀る上御霊(かみごりょう)神社が含まれているところです。
藤原吉子は謀反の嫌疑で幽閉され、自害した女性でした。
上御霊神社は他にも不幸な最期を遂げた人物が多く祀られています。
公家の中でも名門中の名門といえる冷泉家が、そうした人々(神)を拝むというのはパラドックスというかなんというか。
他に穀物の神・宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ・稲荷神のこと)も冷泉家が迎える神の一柱とされているのですが、正直これはよくわかりません。
誰もが食べるものですから、誰が祈ってもいい神様ではありますね。
炎の中にみかんやまんじゅうも放り投げ
お火焚きの火には、みかんやおまんじゅうを投げ入れることもあります。
当然火の粉が散ってかなり危険なのですが、「火が高く登るほど神様が喜ぶ」とされているので、むしろ歓迎すべきことなんだとか。人間にとっては怖すぎますけどね……。
明治時代に一度だけ、明治宮殿の”室内で”お火焚きをしたことがあり、女官の中には怖がっていた人もいたようです。そりゃあな。
現代のお火焚きでも、みかんやおまんじゅうを焼いて振る舞うところがあるようです。
聞き慣れないと「みかん焼くの!?」と思ってしまいますが、どちらも甘さが凝縮して美味しいんだとか。
この時期に京都へ出かけたら、お火焚きに参加してみるのもいいかもしれませんね。
お火焚きは曜日に関係なく、毎年同じ日に行われることが多いので、「今年は◯◯神社、来年は××神社」というように、順繰りに訪れるのも面白そうです。
戦国ファンの方でしたら、11月23日の建勲神社(祭神は織田信長)などは面白いのではないでしょうか。
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
同じ日に車折神社(祭神はかまどの神・奥津彦神と奥津姫)でも行われるようですよ。
あわせて読みたい関連記事
-

明治政府の失策から日本文化を救ったフェノロサ~法隆寺夢殿 数百年の封印も解く
続きを見る
-

実は秀才だった蘇我入鹿~古代の悪人代表は捏造エピソードも多い?
続きを見る
-

東大寺金剛力士像を作成した運慶快慶~他にどんな作品が残っているのか
続きを見る
-

なぜ信長は「第六天魔王」なんて呼ばれたのか 本当に魔王のような人物だった?
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
【参考】
米窪明美『明治宮殿のさんざめき (文春文庫)』(→amazon)
島崎晋『日本の神さままるわかり事典 (学びやぶっく)』(→amazon)
京都観光Navi(→link)
広隆寺/wikipedia