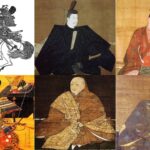こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【清和天皇】
をクリックお願いします。
臣籍降下で多くの源氏や平氏が誕生していた
清和上皇がなぜそこまで苦しい修行を選んだのか。
真意は定かではありませんが、この世にいるうちは安寧を望んだようで、京の中に御所を作らせたのではなく、都の中心からは少し離れた水尾という場所を終の棲家としました。
現在の地名では京都市右京区水尾です。
1200年前からある地名と考えると、さすが京都ぱねえ。
亡くなったのはもう少し離れたところにある清涼寺というところなのですけども、これまた現在の地名では同じ右京区なので概ねご希望が叶ったと見ていいでしょう。
陵(みささぎ・皇族のお墓)は水尾に作られています。
そんなわけで武士とは全く縁のなさそうな生涯を送られた方なのですが、ここで冒頭のお話に戻りましょう。
31歳というお若さで亡くなったものの、清和天皇には数多くの皇子・皇女がいました。
そしてそのうち孫の源経基(父は貞純親王)や源清蔭(きよかげ・父は陽成天皇)が「源」の姓をもらって臣下に降っています。
このようにして皇族の身分を離れることを”臣籍降下”といいますが、一般的にイメージされる”源氏”や”平氏”のほとんどは臣籍降下した元・皇族の子孫達です。
-

なぜ皇族から源氏や平氏が出てくるのか「臣籍降下」による皇位皇族の法則
続きを見る
子沢山な皇族ほど子供や孫が臣籍降下する確率も高く、そのため枝分かれした人の親の名を取って「◯◯源氏」とか「✕✕源氏」というように系統を区別しています。
そのうち「清和源氏」が最も有名で、誰もが知っている武家の源姓は、さらにそこから「河内源氏」となった系統です。頼朝もここですね。
【清和天皇】
│
第六皇子・貞純親王
│
経基王(源経基)初代
│
源満仲(安和の変)
│
源頼信(道長四天王)→ここから河内源氏
│
源頼義(前九年の役)
│
源義家(後三年の役)
ここから先、さらに細かく枝分かれするときには、全く別の名字を名乗ることもよくありました。
有名な例でいうと、足利氏(尊氏の家)や新田氏(義貞の家)、武田氏(信玄の家)は河内源氏の一流になります。
具体的には、以下の図の通り、源頼義や源義家から分かれました。
甲斐源氏の嫡流・武田氏の初代は武田信義で、こちらは『鎌倉殿の13人』に登場していましたね。
-

甲斐武田氏を守り抜いた武田信義の生涯~信玄のご先祖様は頼朝に息子を殺される
続きを見る
武家ではない公家の源氏・平氏も多々おります
そんなわけで「源氏の血筋って言ってるけど名字違うじゃん」というようなことが起きるわけです。
ちなみに元が皇族なので、後々武士になった人たちだけでなく、公家の源氏や平氏もたくさんあります。
清和天皇が亡くなったのも、源融(みなもとのとおる)という貴族の別荘でした。
そこが清涼寺の原型です。
-

平等院鳳凰堂の意外な歴史〜源融から紆余曲折を経て藤原道長から頼通へ渡る
続きを見る
百人一首にも歌が取られていますし、光源氏のモデルの一人ともされているのでご存知の方も多いのではないでしょうか。
光源氏も臣籍降下の一例ですね。
臣籍になる理由は「皇族のままだといろいろ制限があるので生活が苦しいが、臣下になればできることが増えるため、生活を安定させることができる可能性が高い」という切実な状況から、というのが多かったようです。
臣籍降下は、ある意味リストラ・早期退職みたいなもので親近感が湧きますので、こうしたシステムが日本で皇室を存続できた一因なのかもしれません。
清和天皇が亡くなってしばらくの間は藤原無双の時代が続きます。
大河ドラマ『光る君へ』などは、その頂点。
娘を天皇の后にして孫が生まれたらガッチリ手綱を握る――そんな外戚政治は道長のずっと前から行われていたんですね。
しかし、その後、源氏によって武家政権が作られ、概ね700年ほど武士中心の世の中になっていくことを考えると、清和天皇が荒行で祈ったことは決して無駄にはならなかったのかもしれません。
🗿 古代日本|飛鳥・奈良を経て『光る君へ』の平安時代までを総覧
あわせて読みたい関連記事
-

清和源氏とその他の源氏の違いは何か?ややこしい源氏軍団をスッキリ整理しよう
続きを見る
-

甲斐武田氏を守り抜いた武田信義の生涯~信玄のご先祖様は頼朝に息子を殺される
続きを見る
-

伊豆に流された源頼朝が武士の棟梁として鎌倉幕府を成立できたのはなぜなのか
続きを見る
-

藤原良房が皇族以外で初の摂政に就任! 貞観14年(872年)藤原無双が始まる
続きを見る
-

藤原体制を盤石にした「応天門の変」真犯人は誰?伴善男の流罪で良房ウハウハ
続きを見る
【参考】
国史大辞典
歴史読本編集部 『歴代天皇125代総覧 (新人物文庫)』(→amazon)
山本博文『ビジュアル百科 写真と図解でわかる! 天皇〈125代〉の歴史』(→amazon)
清和天皇/wikipedia