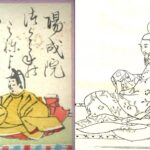平均寿命が延びたことや戦争が減ったことにより、現代の王様はシニア層になってからの即位が珍しくありません。
ただ、過去にも例がないワケではなく、元慶八年(884年)2月23日に即位した光孝天皇(こうこう)は、実に当時55歳でした。
なぜそんな歳での即位となったのか?
当時の事情を見てみましょう。

光孝天皇/wikipediaより引用
乱暴だから退位させたら次の候補がいない
なぜ55歳という、当時としては高齢での即位となったのか――本人の問題というより、当時の朝廷内のいざこざに原因がありました。
ときの帝は陽成天皇という方。
言動が粗暴だということで無理やり退位させられたところ、次の天皇にふさわしい人物が若い世代にいないという衝撃の事実が明らかになったのです。なぜ先に決めておかなかった……。
厳密に言えば陽成天皇の子女はいたのですが、まさかそういう理由で退位させた人の子供を位につけるわけにもいきませんしね。
ちなみに陽成天皇の素行が悪かったというのもアヤシイ点が多々あるのですが、それは以下の記事に(記事末にもリンクがあります)。
-

上皇生活が65年も続いた~陽成天皇が不遇だったのは藤原基経に陥れられたせい?
続きを見る
そして、しらみつぶしに次の候補を探した結果、品行・能力共に適任と思われたのが当時、時康親王と名乗っていた光孝天皇でした。
上記の通り、即位したとき55歳ですから、この時代の平均寿命を考えるとかなり危険な状況です。
ご本人はそれがわかっているのかいないのか。あるいは政治的な配慮からか。
自らの子孫に皇統を移すつもりはなかったと宣言するかのように、子女全てを【臣籍降下(皇族の身分ではなくなって臣下となり姓を賜る)】させます。
要は、皇位の継承権を放棄させたんですね。
しかし、後に適切な人物が見当たらなくなり、臣籍降下した一人を皇族に戻して次の天皇にしております。
それが源定省こと、のちの宇多天皇――。
こうしたゴタゴタが結果的に藤原家の権力をさらに強化させることにも繋がっています。

宇多天皇/wikipediaより引用
関白を事実上創設
話を少し戻しまして、陽成天皇を退位させたのは藤原基経(もとつね)です。
光孝天皇は自分を推してくれたことで藤原基経に感謝していたようで、実質上の関白にあたる職へ任じています。
基経もこの時点で50歳近かったのですが、光孝天皇よりも長生きしていますので、これは大正解でした。
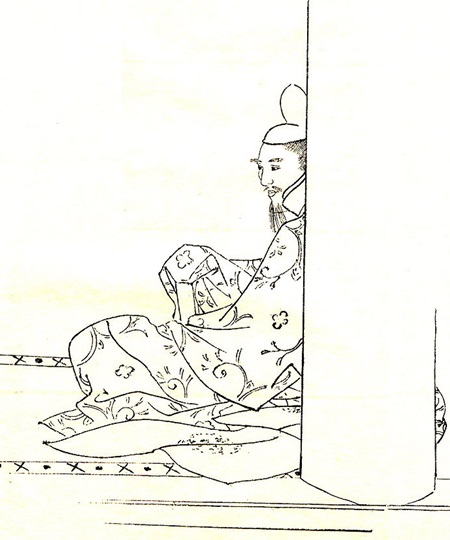
藤原基経/wikipediaより引用
また光孝天皇は、生活が苦しかった親王時代を忘れまいと、即位してからも昔焦がしてしまった台所をそのままにさせておいたとか。
ずっと後の時代ですが、肥後の鳳凰こと細川重賢にも似たエピソードがありますね。
重賢は台所じゃなく”若い頃にした借金の札をずっと持っていた”というものですけども。
※続きは【次のページへ】をclick!