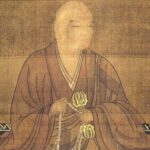こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【受領は倒るる所に土を掴め】
をクリックお願いします。
文人貴族として、その特技をフル活用する為時
長徳元年(995年)越前守として赴任していた為時のもとに、北宋の商船が上陸したという知らせが届きます。
北宋からの船は「10年か12年に一度は上陸してよい」というルールがあった。
しかし、その船はどうやら別物のようだ。
と、朝廷で協議のうえ、為時が応接することになったのです。
このときの為時の気持ちを想像すると、なかなか興味深いものがあります。
伝統的に日本でも漢籍が得意だと自認する者たちは、中国人を相手にテンションを上げていました。
たとえば江戸時代、長崎の唐人屋敷には自作漢詩をウキウキしながら持ち込む文人たちがいたものです。
『光る君へ』でも注目された人物がいましたね。
浩歌さんが演じる朱仁聡(ジュレンツォン)と、松下洸平さんが演じる周明(ヂョウミン)です。

画像はイメージです(五代南唐『 文苑図』周文矩作/wikipediaより引用)
宋の人々を歓迎した為時は、自作の漢詩をお披露目しました。
これがうまいか、下手か? というと、ちょっと答えが難しい。
時代を問わず、日本人作の漢詩あるある現象があります。
それは【押韻】はじめ、ルールを無視しがちなこと。
要するに漢詩は響きの同じ言葉で揃えなければならないのですが、本場と日本では発音も異なるため、おかしくなってしまうのです。
はじめこそ本場の教師を招聘して学ぶ機会はありましたし、紫式部の時代にも【韻塞ぎ】という【押韻】知識を活かしたゲームはあったものの、どこまで正確であったのでしょうか。
それ以外にもテーマがそぐわない。本場ではあり得ない表現を用いる。そんなズレはどうしたって生じました。
そんな日本人の漢詩を受け取る側の宋人たちも、そのあたりは心得ています。
「素晴らしいですねえ、詩を詠めるのですか!」
そうにこやかに対応して、『ありえん、なにコレ、日本人は仕方ないね』という本音は抑える。
彼らにとっては、自国文化を取り入れ、真面目に学んでいる姿が微笑ましいことは確かです。
要するに、現在でいうところの「町中華」ですね。
茹でるはずの餃子は焼いてあるし、片栗粉を使いすぎているし、スパイスは不足気味。
本場の人からすればどう考えても日本風――でも中国風だと相手が納得しているならば、それはそれでよいのです。
為時は、ちゃんと漢詩で相手をおもてなししたのだから任務達成ができた。それでよいのです。
朝廷の人々は、宋人の対応に神経を尖らせていたものの、この船は数年後には九州博多へ移動。
ここまで来れば、京都の人々も一安心です。
武力ではなく、優雅な文化交流でことを収める。為時は文人貴族としての面目を発揮し、役目を果たした。晴れがましかったことでしょう。
そしてこの父・為時由来の漢籍知識を、紫式部はフル活用しています。
宮仕えの同僚の前では、マウンティング女扱いを恐れていた紫式部は、陽キャの清少納言とは違う、陰キャであったのかもしれません。
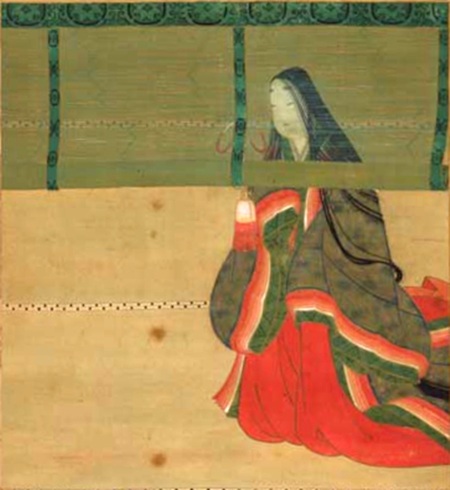
清少納言/wikipediaより引用
そんな紫式部が、ありのままの漢籍知識を発揮できたのが、『源氏物語』の世界です。
物語の中に織り込んだ漢籍はなんと13種!
『源氏物語』を読んだ一条天皇はこう言いました。
「この作者は歴史書をずいぶんと読み込んでいる。才能がある人だね」
一条天皇がこう漏らした時、紫式部のパトロンである藤原道長もほくそ笑んだことでしょう。
あれは冴えない受領の娘のようで、知識豊富なのだ。見抜いたのはこの私。あれの父親だって大したモノだったぞ、と。
ちなみに紫式部は『源氏物語』の中で、光源氏が我が子である夕霧を育てる教育方針が特異だと記しています。
あれほどの血筋ならば、勉強をしなくても出世はできるはず。
それなのに、四位からではなく、六位という低い位しか夕霧にあてがわず、大学に入学させたのです。
光源氏を誉めているようで、勉強もできないのに出世するボンボン上流貴族を遠回しに皮肉っているように思えるのは穿ちすぎでしょうか。
ちなみにこうした貴族代表として、藤原実資から「一文不通」と罵倒された藤原道綱がおります。
道長はこの道綱よりは多少マシであったものの、日記文法が崩壊しているうえに記述が雑。
同じ日記でもインテリの藤原実資、こまやかな藤原行成と比較すると、教養面で見劣りがします。彼もボンボン貴族なのです。
悪筆としても悪名高い。『光る君へ』では、道長の字が整いすぎていると、NGが出るそうですよ。
ともあれ、紫式部が厳しい教育をプラスの要素として見ていたことは確かなのでしょう。
そして「武者の世」へ……
こうした中級以下の貴族の不遇は、藤原為時一人だけのことではもちろんありません。
上からコキを使われる。
せっかく学んでも、科挙を採用しない日本では芽が出ない。
アホなボンボン上流貴族に好き放題され、もうやってられんわ……そうなる者が出てきてもおかしくはありません。
紫式部が生きていた時代から、国家のシステムには少しづつヒビが入っていてもおかしくなかったのです。
外戚の政治介入を軽減したい天皇は、上皇が権威を持つようになります。
この体制は天皇と上皇が対立するという構図が生じ、【保元の乱】へつながってゆく。
こうした対立の解決に武士を引き込んだことにより、平清盛が台頭。

月岡芳年が描いた平清盛/wikipediaより引用
さらに坂東では、在地武士たちの不満が高まっていました。
そもそもとして、受領はプライドが高く、がめつい。
それでも従うしかないと思っていたけれども、これが平氏の連中ともなると、いっそ倒してよいのではないかと思えてくる。
疫病の蔓延。
気候変動。
統治への不満。
そんな燃料が溜まってゆく伊豆の地へ、坂東武者からみれば貴公子である源頼朝が流されてくる。
それでも坂東武者が勝手に東国に割拠しているだけならば、翻弄できたかもしれない。
そこへ不満を抱いた貴族である大江広元らが加わり、行政の仕組みが出来上がってしまいます。
坂東から武者たちが京へと雪崩れ込み、【承久の乱】により、ついに「武者ノ世」が完成。
その過程が『鎌倉殿の13人』で描かれたのです。
確かに京都の朝廷や貴族の嘆きも、もっともなことではあります。
ただ、そうなるだけの歪みが見えているのが『光る君へ』の背景であるともいえるのでしょう。
あわせて読みたい関連記事
-

平安時代の国司と受領と遙任の違いは何なのか?伊周が飛ばされた大宰府とは?
続きを見る
-

藤原為時(紫式部の父)は融通の利かない堅物だった?中級貴族の生涯を振り返る
続きを見る
-

花山天皇の生涯|隆家との因縁バチバチな関係で喧嘩も辞さない破天荒
続きを見る
-

『光る君へ』宋の商人・朱仁聡(浩歌)は実在した?為時と紫式部の恩人と言える?
続きを見る
-

『光る君へ』宋の周明(松下洸平)とは何者?紫式部の知力を強化する存在となる?
続きを見る
【参考文献】
繁田信一『紫式部の父親たち』(→amazon)
大塚ひかり『源氏の男はみんなサイテー』(→amazon)
河添房江『源氏物語と東アジア世界』(→amazon)
小島毅『子どもたちに語る 日中二千年史』(→amazon)
他