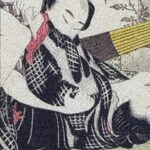こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第35回間違凧文武二道】
をクリックお願いします。
凧を上げれば天下泰平?
栗山が話していた「越中守様の文書」こと『鸚鵡言』とは?
その術様々なれど、紙鳶(たこ)を上ぐるに外ならぬ。活国の術はもとあるを知るべし……
春町がそう読みながら歩いています。横には蔦重と大田南畝。

鳥文斎栄之が描いた大田南畝/wikipediaより引用
「直参の間ではこれを写すのが流行っているのか?」と大田南畝に尋ねると、ふんどし(越中守こと松平定信)自らが記したものを書き写すという、しょうもねえ話になっているとか。
すると幼い武家の少年二人がこう言いながら歩いていきます。
「えっまことか? 凧をあげたら国が治まるのか?」
「鸚鵡の言葉にはそう書いてあると父上が仰せであった」
「鸚鵡の……言葉?」
「ありがたき教えだそうだ」
「鸚鵡の言葉かぁ」
これを聞き、春町、南畝、蔦重は何か閃いたようです。
蔦重はていに、この誤解を面白おかしく話していますが、いったい彼女はどう答えるのか?
「まことにそうならいいですね。凧をあげたら国が治まるなど朗らかで」
「ああ、確かにな」
蔦重がそう返答すると、母のつよが慌てて飛び込んできました。歌麿が来ているそうですが、何かいつもと違うようで……。
歌麿はきよと所帯を持ちたい
歌麿はきよを連れてきました。
ていが「誰か?」と尋ねると、はしゃぎながら「そうだよね?」と言い出すつよ。蔦重は「ババア、黙ってろ」とたしなめます。
歌麿はまず、石燕先生の話からします。
前月に亡くなっていました。どうして話さなかったのか?と蔦重がいうと、「急だったし、いろいろ後始末も多くてさ」と答える歌麿。
なんでも雷雨のあと、筆を握ったまま動かなくなっていたようです。
年も年だし大往生だとまとめ、歌麿はその遺作を持ってきていました。
「雷獣……雷を起こす妖(あやかし)」
蔦重は何か気づいています。
「なんとなくだけど、この辺が源内先生ぽいなって」
そう頭のあたりを指します。
「まァ、妖になってても不思議ではないお人ではあったよね」
そう歌麿と納得しています。
つよは、歌はこっちに戻ってくるのかと問いかけます。この人は歌麿が連れてきたいい人が気になってしょうがないんだな。
「そのことなんだけどさ、蔦重」
そうあらためる歌麿。
「俺、所帯を持とうと思って」
蔦重が「所帯?」と、どこか鈍いのに対し、ていはこう力強く言います。
「やはり、そういうことにございますよね」
すると歌麿が、隣にいた彼女のことを“おきよ”だと紹介し、聞こえないし喋れないと説明します。
蔦重はようやく、会ったことがあると思い出しました。歌麿が「絵を拾った人だ」と言うと、拳で床を叩きつけるきよ。
歌麿はたまたま再会し、絵を描かせてもらったと語ります。
なんとも幸せそうな歌麿。
言葉がないからきよは何を考えているのかよくわからない。だからこそ顔つきや動きから、何を考えているのか、考えるのが楽しい。それを絵にするのも楽しい。時が経つのも忘れてしまうのだそうです。
「蔦重、俺、ちゃんとしてえんだ」
「ちゃんと?」
「ちゃんと名をあげて、金も稼いで、おきよにいいもん着させて、いいもん食わせて。ちゃんと幸せにしてえんだ。で、石燕先生が借りてた仕事場をそのまま借りられねえかと思ってさ。手持ちだけじゃちょいと足りねえもんで、これ、買い取ってもらえねえかな?」
そう歌麿は言うと、絵を渡してきます。
「お前、これ……」
「前には描けなかった笑い絵さ」
そこにあるのは、幸せそうに肌を合わせる男女の姿。穏やかであたたかい世界があります。
ちなみに蔦重は「枕絵」として依頼し、歌麿は「笑い絵」と表現しています。
どちらも「春画」です。
-

『べらぼう』蔦重が歌麿に描かせようとした「枕絵」江戸土産にもなった春画の歴史とは
続きを見る
笑いながら描き、見る絵
ただ、わずかなようで、歌麿の心情の差があります。
「枕絵」は要するに閨の枕にある絵ととれる。「笑い絵」は、笑顔になってすることの絵と解釈できる。
歌麿は心の底から、花がほころぶように笑えるようになって、やっとこうした絵が描けるようになったのです。
「おきよのおかげなんだよ。おきよがいたから、幸せって何かってわかって……そしたら、幸せじゃなかったことも、絵にすることができた……」
そうしみじみと語る歌麿。
その絵をのぞきこむていも、つよも、蔦重も、感無量の顔をしています。
「あ……だめかい? 通しで見ると、全然全く、まとまりがねえんだよな」
歌麿がそういうと蔦重は立ち上がり、きよの前に座ります。
「おきよさん。まこと、ありがた山にございます。こいつにこんな絵を描かせてくれて、ありがた山です。こりゃ歌麿を当代一に押し上げる、この世でほかの誰にも描けねえ、こいつにしか描けねえ絵です! どうか、一生そばにいてやってくだせえ!」
歌麿が「俺は嬉しいんだけどさ」といい、つよも「全く伝わってないと思うよ」とフォロー。
きよは、すっかり怯えた顔じゃないですか。
歌麿は「身を引いてくれと頼まれたと誤解している」と言います。耳が聞こえないから仕方ないですよね。
その夜、蔦重はしみじみと酒を飲みつつ、歌麿の笑い絵を見ています。ていもジッと見ている。
「何だいおていさん、実は笑い絵、好きなのか?」
「歌さんの絵なら、虫の絵の方がよほど好きです。でも……ここに歌さんの心血が注がれているのが感じます。ならばちゃんと見なければと。私は蔦屋の“女将”にございますので」
実に江戸時代らしい場面っちゃそうですぜ。
これはおていさんだけの話でもなく、当時の春画は男女双方が見るものでした。
独身男がコソコソ見るしかないような、そんなエクストリーム系春画もあるっちゃそうですが、こうして軽くからかいつつ、ともに笑顔で楽しむのが基本ですね。
大河ドラマでここまで再現してくれるなんて、時代の進歩を感じるぜ。
「……出会った頃のあいつは、ただただ死ぬのを待ってるってなふうだったんだよ。生きる欲みてえなのがこれっぽっちもなくて。そんなあいつが、“ちゃんとしてえ”ですよ。“ちゃんとしてえ”って言ったんですよ。俺、嬉しくてさ」
そう涙を拭う蔦重。
ていは、そんな蔦重に静かに酒を注ぎます。
「では、こちらもちゃんと仕立てて、ちゃんと売らねばなりませんね。ちゃんと取り戻せますように。歌さんにお支払いした“百両”を」
きりっとした顔で蔦重に迫ります。ご祝儀も兼ねてるとはいえ、随分と気前よく出したもんだね。
「今、その話をしなくてもいいんじゃねえかい?」
「私は、蔦屋の“女将”にございますので」
ていはそう蔦重に迫り、メガネを押し上げます。
「……そうだな、わかりました」
そう認めざるを得ない蔦重です。
夫婦の関係も固まってきて、さながら水魚の交わりでやんす。
蔦重はおていさんの洞察力を認め、軍師役にしております。おていさんも、軍師として経営に目を光らせることを楽しんでいます。
おていさんは自分の望む立場を手に入れて、生き生きとしているように思えるのです。
ただ、こうなってくると、東洲斎写楽の売り出しにより、おていさんと蔦重の関係も悪化するのではないかという懸念もあります。
蔦重が負け戦に金と力を注いでしまう大失敗ですので……。
歌麿は、蔦重からの百両で購入したのか、美しい反物をきよに着せて、似合うと喜んでいます。
まるで絵が動き出したような二人。
歌麿の作品はこうして生まれたと言われると、そうだとしか言いようのない美しい場面でした。
からかいか? 諫言か?
そして秋、春町が草稿をしあげてきました。戯作者会議で確認をしています。
内容は、みんなが勘違いして凧揚げをしたら、鳳凰が勘違いして出てきてしまって、なんだか天下泰平の世になっちまうオチなんだとか。
「これで仕上げに進もう!」と蔦重が決断うると、おていさんが「あまりにからかいがすぎるのではないか」と懸念を表明します。
蔦重が現実に起きていることだと反論するも、だからこそ危ないとていは言うのです。
「凧をあげてめでたしなんだからよいのでは」と蔦重が言っても、やはり「ふざけすぎだ」と答えるてい。
すると今度は春町が、真剣になってふざけたつもりはないと説明します。
「ふんどしの思い描いたとおり、世は動かぬかもしれぬ。だが思うように動かぬものが、思わぬ動きを見せるかもしれぬ。故に躍起になって、己の思う通りにしなくてもよいのでは。少し肩の力を抜いてはいかがかと。俺としては、そういう思いも込めて描いたものだ」
「からかいではまく、諌めたいというところか」
大田南畝はこう言います。
「まあ、そういったところだ」
認める春町。ていはまだ不安そうです。
「それは、からかいよりも更に不遜無礼と受け止められませんでしょうか?」
「そもそも不遜で無礼なことをしようってわけで」
蔦重がそうまとめます。
ていは丁寧に「とにかく、私はこれは出せば危ないと存じます」と返すしかありません。
このやりとりは重要でしょう。
結果的に、これは妻、女の言い分が正しかったと判明するわけです。昨年の『光る君へ』でのまひろと道長にもそういう場面はありました。
ジェンダー観点からすると、これが大事です。
この手のフィクションでは、男が先を見抜いて正しいことを言っているにも関わらず、女のせいで失敗するというパターンが実に多く作られてきました。
例えば戦国ものでは、男たちは豊臣家は破滅しかねないとそのことを回避しようとするのに、短慮な淀の方と、北政所たち女同士の争いで滅びるという描き方がかつては多かった。
そうした状況をひっくり返すような描写を、今年の大河ドラマは投げかけてきて、実に良いではないですか。
すると次郎兵衛が、つよに迎えられつつ入ってきました。
なんでも気になる噂を聞きつけたそうで……実は、越中守は大の黄表紙好き、大ファンなんだそうで。
お屋敷で奉公した者から聞いた話とのことで、さすが吉原は耳が早いもんですね。
しかも『金々先生』以来の春町ファン。蔦重のことも大好きなんだとか。
次郎兵衛の話に皆が浮かれる中、ていだけがかえって警戒心を強めているようだ。言わんとするところは、わかる。
敵を知り、己を知れば百戦危うからず――なまじ手の内を知っている相手の方が危険ですからね。
ふんどしは黄表紙という「敵」の手の内はわかっている。
うがちなんて読解力が高い。
これまで見逃してきたのは、ファンだから目が曇っていたのかもしれぬと、おていさんなら身構えてもおかしくねえや。
※続きは【次のページへ】をclick!