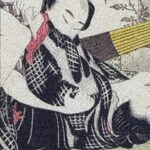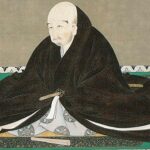こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第35回間違凧文武二道】
をクリックお願いします。
幕府を滅ぼす「大政委任論」の芽がみえる
かくして蔦重は本を作り、定信は心得をまとめ、家斉は『御心得之箇条』を手にしてやる気がなさそうに広げています。
この心得には恐ろしいことが書き記されています。
それこそ再来年の『逆賊の幕臣』の幕臣たちが知ったらため息をつきそうな話です。
「六十余州は禁廷より御預り遊ばされた候御大事に……」
要するに、日本は天子様から預かったものであり、決してご自身の自由にできるものではないという「大政委任論」となります。
定信は教育効果を期待して出してしまいますが、読んだ家斉は何を考えているのやら。それこそ幕府が滅びる綻びが生じる契機となります。
家斉の治世は尊王論が高まるターニングポイントです。
家斉はあの調子で子作りに励み続けました。そしてできた男子は官位を引き上げて箔付けし、大名家に送り込む。
この官位による箔付が実に厄介で、官位の背後にある天皇の権威を結果的にあげることとなります。
そして、尊王とセットになる攘夷の種も撒かれる。
田沼意次から松平定信に交代したことにより、ロシアとの交易構想も棚上げとなります。
しかし、ロシア側からすればそんなことは知ったことではない。
南下して貿易を求めてきます。
ロシアに由来する脅威を伴う西洋事情も、しぶとく知識人階級に広がってゆきます。幕府は禁じようとするものの、しぶとい版元や文人の奮闘もあり、なかなか止められないのです。
西洋の未知なる恐怖に困惑した者たちは、日本は神の国だからどうにかなるという、江戸の「日本人ファースト」思想に傾いてしまう。
かくして日本には尊王攘夷思想が撒かれ、育ち、そんな時代に直面した『逆賊の幕臣』の小栗忠順たちはその荒波に翻弄されることになるのです。
そしてこの「大政委任論」に乗っかった徳川慶喜は「大政奉還」をすることになり、幕府は滅びることになります。
『べらぼう』は、幕末史理解にも大変役立つドラマです。
そして寛政元年(1789年)――『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』が完成しました。
九郎助稲荷がこう語ります。
それは、蔦屋の運命の分かれ目となるのです。
ここで空に浮かんでいた凧の糸が切れ、墜落する姿が見えます。
MVP:きよと歌麿
歌麿が美人画へ近づく過程が、今回も見事に描かれました。
蔦重が主役ならば、彼が導いて描くのでもよいはず。ああしろこうしろと指示を出してもよい。それが蔦重は見守りつつ、歌麿が成長して描くように描かれました。
そのきっかけを導く妻として、きよが出てきます。
きよはまず、美しい。歌麿美人が動き出したように思えます。
洗濯物を干す腕の白さ、洗濯をするために傾けた顔、何もかもが絵そのものに見えてきます。
きよの場面は脚本も素晴らしいのですが、演出も、照明も、何もかもが素晴らしい。メイクにしてもそうです。
藤間爽子さんは、見れば見るほど歌麿の描く美人画そのもの。メイクにせよ、くどいパーツの誇張がありません。
ちょっと比較対象として引き合いに出してしまいますが、ディズニーの『SHOGUN』に登場する女性メイクは一体なんなのかと疑問を感じておりました。
それこそディズニーアニメに出てくるような、アイラインがくっきりと引かれ、頬骨を強調したメイクです。
伝統的な日本美人からかけ離れていて、現代アメリカ人が好きそうなメイクを重視し、日本の伝統は無視していると感じました。
あの作品には日本の美に対する理解が不足していたと思います。
あのヒロインがアメコミかディズニーアニメの世界観ならば、今年の大河ドラマは正統派浮世絵美人画の世界観を再現していて、実にこれまたありがた山でやんす。
きよと歌麿の境遇にも、このころの社会の歪みが反映されています。
二人とも最下層に生まれて、身を売ることで生きるしかない境遇でした。
このドラマは前半が吉原舞台であることから、性的搾取を美化すると打ち切りまで求められてきました。
しかし、そう単純なものでもない。
それどころか、歴史の中にこぼれて消えてしまった声まで拾ってくれます。
これも歌麿の描く絵の特徴のひとつ。
彼の作品には、最下層を生きざるを得なかった人々の姿も含まれているのです。
浮世絵を愛し、その世界観を再現するということは、こういうことなのだろうと思います。
新キャストが発表されました
ネタバレとなりますので嫌な方は読み飛ばしてください。
放映翌日、新キャストが発表されました。
◆重田貞一、のちの十返舎一九 → 井上芳雄さん
◆勝川春朗、のちの葛飾北斎 → くっきー!さん
◆滝沢瑣吉、のちの曲亭馬琴 → 津田健次郎さん
いったい誰が馬琴を演じるのか? 本当に楽しみに待っていました。
私は『八犬伝』は大好きです。そのうえで馬琴のことは性格が最悪だと思っています。
ともかく癖が強く、教えを願った山東京伝に「リア充爆発しろ」と攻撃を続け、就職先として紹介された耕書堂でも最悪の接客態度をとり続ける。
そのうえで蔦重のことも、山東京伝のことも、自分ほど教養がないと書き残す――地獄から這い出てきたような陰キャ大魔王です。
しかも、歌麿が所帯を持った放送日の翌日に発表するとは、なんということでしょう。
あれほど売れっ子絵師だった喜多川歌麿だが、死ぬ時はそばに妻も子もなく一人きりであり、彼を追悼する者すら絶えるだろう――馬琴がそう記した歌麿の最期が、信頼性のあるものとしてしばしば用いられます。
そんなことを書き記すことはないだろうと思ってしまいます。馬琴は悪意を込めた記録が多いためまるまる信じることもできませんが……。
ともかく放送とキャスト発表のタイミングが実に悪魔的で、この苦しさを分かち合いたくて、つい書いてしまいました。
イケボで山東京伝にネチネチと嫌味を言う、そんな馬琴に期待しましょう。
総評
松平定信の微笑ましいギャップ萌えとして描かれていたかのような、そんな黄表紙オタクという一面は、悪夢の前振りでしかありませんでした。
そんな嫌な予感しかない回です。
ドラマとして面白いだけでなく、歴史観まで素晴らしいのが本作。
今回見ていて、初登場や退場のタイミングまで、歴史観を揺さぶる仕掛けがあると再確認しました。
田沼意次は台詞だけでその死が処理されてしまいます。名もなき市井の人でしかないふくや新之助の死がしっかりと描かれたのに対して、実に象徴的に思えるのです。
しかもこの場面では、定信がガス抜きのために田沼意次の葬列すら利用しようとする。そんな浅ましい現実まで描かれています。
本作の恐ろしいところは、現実のニュースと重なってしまうところではありませんか。
つい先日、アメリカで政治インフルエンサーが、銃撃による不慮の死を遂げました。
犯人像は二転三転しつつ、そのたびに政治利用されてゆく様がSNSやニュースで展開されていました。
情報伝達の速度では現代社会ほどではないとはいえ、実は昔からこういうことはあった、普遍的なことだと思わされます。
歴史を学ぶ効能とはまさにこのことであり、過去を鏡として現代を移し、考えをまとめることだと思います。
劇中ではおていさんが漢籍を使用し、よくしていることですね。
戦国乱世は権力ゲームとしてみれば面白いかもしれませんが、人類の姿としては例外的な時期でもあるわけです。
社会が練られ、形成されていった時代こそ、学ぶヒントは実に多いと思わされます。
そして歴史を見て今後を占うとすれば、松平定信にはこの民衆心理の利用が己に跳ね返ってくると言えなくもありません。
ますます情報のバトルが先鋭化してゆく版元、絵師、戯作者の攻防は幕末まで続きます。
そんな江戸文化読解のためにも、今年の知識を今後にも使っていきたいものです。
あわせて読みたい関連記事
-

『べらぼう』蔦重が歌麿に描かせようとした「枕絵」江戸土産にもなった春画の歴史とは
続きを見る
-

『べらぼう』平賀源内を廃人にした薬物はアヘンか大麻か?黒幕・一橋治済と共に考察
続きを見る
-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗
続きを見る
-

寛政の改革|蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?
続きを見る
-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由
続きを見る
【参考】
べらぼう/公式サイト