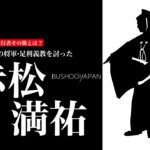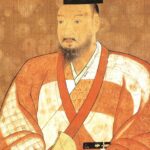今回から『信長公記』の巻一に入ります。
実は一番長いのが今まで紹介してきた首巻で、あとは割と細かく巻が分かれているため、今後は少し切り替わりが早く感じられるかもしれません。
なぜかというと、信長公記は首巻以外
【1つの巻=1年】
という区切りになっているからです。
全体として【首巻+15巻】なので、【前半生+15年分】ということになりますね。
前回「信長は入京時で34歳」と述べましたので、そこから15年だと49歳。
ちょうど没年になるというわけです。
巻一は本来、永禄十一年(1568年)に起きた信長の出来事を記す巻ですが、今回は信長本人ではなく、当時の京都事情を振り返るところから始まっています。
具体的には、永禄八年(1565年)5月に起きた「永禄の変」です。
以下に詳細記事もございますが、
-

永禄の変|三好勢に囲まれた13代将軍・義輝は自らの刀で応戦し力尽きる
続きを見る
ここでは『信長公記』の記述を補足する形で話を進めていきましょう。
三好一族と対立し暗雲立ち込め
当時は十三代将軍・足利義輝の時代。
信長の父・織田信秀や、織田信長本人も拝謁したことがあるあの人です。
応仁の乱以降、足利将軍家もあっちこっち右往左往しながら、実権と権威を取り返そうとしていました。
義輝はその傾向が特に強かった人で、当時の実力者だった三好長慶を次第に疎んじ始めます。
長慶本人は永禄七年(1564年)に病死したので、すぐに衝突とはいかなかったのですが……。
それまでの三好家に対する世間の評判は「将軍に謀反を企てているに違いない」というもので、ほぼ固定されてしまっておりました。
跡を継いだ長慶の甥・三好義継にも疑いの目が向いており、義継本人はのらりくらりとはぐらかしていた……と、信長公記では書かれています。
誠意があれば、もう少し違った評判になっていたのでしょう。
そうではないあたりがなんともきな臭いですね。

三好義継/wikipediaより引用
御所を襲撃され、薙刀や刀で抵抗した
永禄八年(1565年)、義継は清水寺参詣を名目として、早朝から兵を集めました。
そのまま「将軍への訴訟があるので、お取次ぎを」という名目で、義輝のいる将軍御所を襲撃。
このとき”義輝自ら薙刀や刀を取って抵抗した”というのは、今日でも有名なエピソードですね。
日頃から剣術に励んでいた”剣豪将軍”という二つ名を、際立たせている一因でもあります。

側近たちも武器を手に取り抵抗するも、所詮は多勢に無勢。
次々に味方が討ち死にしていき、覚悟を決めた義輝は御殿に火を放った後、自害した……といわれています。
ただし情報が錯綜していたようで、次の2つの史料では以下のように記されております。
◆ルイス・フロイス『日本史』→「義輝は討手に刺殺された」
◆山科言継『言継卿記』→「将軍は生害した」
”生害”という言葉は、当時は自害でも討死でも使う単語であり、このあたりは専門家の間でも意見が分かれています。
いずれにせよ討手に殺されたのであれば、三好軍は義輝の首を必ず持ち帰ったでしょう。
義輝の首は何処へ
家臣が将軍の首を取る――似たような事例に【嘉吉の乱】があります。
このとき下手人の赤松満祐は、六代将軍・足利義教の首を槍の穂先に掲げ、領国へ凱旋していきました。
-

将軍暗殺に成功しながら滅亡へ追い込まれた赤松満祐~嘉吉の乱後の末路とは?
続きを見る
永禄の変で「火災が起きて首を取れなかった」というならば、その時点で義輝は自害していたのでしょう。
こういうときに火を放つのは、自害後に首を取らせないためというのが主な理由です。
より正確にいえば、討手が首を取りに来たとしても、顔を判別できなくなるように……ですかね。
気になるのは、義輝が「実は逃げ延びていた」というような、いわゆる生存説がない点です。
”襲撃された被害者が自害&火を放った”ということが共通している事件といえば、本能寺の変における信長でしょうか。
このときも情報が錯綜しており、一時は信長の生存説が存在していました。
なぜかというと、明智方が信長の首を取れなかったからです。
しかし義輝にはその手の話が存在していなかった様子。
となると、義輝の首が三好方に取られていてもおかしくない気がするのですが……うーん、頭がこんがらがってきますね。
今後の新史料発見に期待するとして、話を先に進めましょう。
三好軍の手により関係者が次々に……
三好軍の念の入れようは凄まじく、相国寺鹿苑院で仏門に入っていた義輝の末弟・周暠にまで追手がかけられました。
このとき、周暠に日頃目をかけられていた”美濃屋小四郎”という15~6歳の少年が、追手の大将である平田和泉を討ち果たし、その後、周暠の後を追って腹を切った、と、信長公記には書かれています。
名前からして商家の出でしょうか。
よほど日頃から固い絆で結ばれた主従だったのでしょう。時代的に衆道関係でもおかしくはありません。
この他、信長公記には記載されていない被害者としては、義輝の側室で「小侍従」と呼ばれていた女性も三好軍に殺されています。
義輝らの母である慶寿院も自害しました。
足利家唯一の生き残りは、奈良の興福寺で出家していた義輝のすぐ下の弟・覚慶。
後に還俗して「足利義昭」となる人物です。
明智光秀や細川幽斎(細川藤孝)を使って織田信長に上洛をサポートさせるわけですが、義昭はまさに流浪の将軍でした。
次回は彼について触れましょう。
あわせて読みたい関連記事
-

刀を握ったまま敵勢に斃された剣豪将軍・足利義輝|室町幕府13代の壮絶な生涯
続きを見る
-

戦国大名・三好長慶の畿内制圧~信長より先に天下人となった43年の生涯とは?
続きを見る
-

永禄の変|三好勢に囲まれた13代将軍・義輝は自らの刀で応戦し力尽きる
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)
書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)
出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)
書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)
出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)
出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ