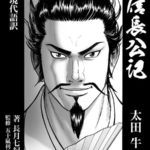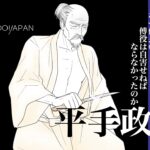永禄十一年(1568年)に足利義昭を奉じて上洛した織田信長。
実はこのとき、松永久秀を傘下に従えた――とは以下の記事に詳細がありますが、
-

松永久秀の生涯|三好や信長の下で出世を果たした智将は梟雄にあらず
続きを見る
その後、隣国・近江(滋賀県)の盟友・浅井長政に裏切られ、一時は絶体絶命の窮地に立たされました。
京都を経由して、命からがら岐阜へ戻った信長と織田軍は、すぐさま浅井征伐軍を挙兵!
「姉川の戦い」で激突する、その前夜について見ておきましょう。
長比砦の堀秀村&樋口直房を調略
前70話・落窪合戦(野洲河原の戦い)の後。
-

野洲河原の戦いと信長の愛刀「実休光忠」|信長公記第70話
続きを見る
浅井長政は越前から兵を呼び入れ、長比と苅安に砦を構えました。
どちらも現在の米原市にあたります。
地図で確認しておきますと……。
【黄色い拠点】
・岐阜城
【赤色の拠点】
・小谷城(浅井氏本拠地・左上)
・刈安砦(左中)
・長比砦(左下)
※刈安砦は、詳細位置が検索不能なため同砦があった米原市弥高地区を表示しております
これでは岐阜城から西へ軍を動かすのは不可能。
とにかく長比砦と刈安砦を何とかしなければ、どうにもなりません。
信長はどうしたか?
攻撃にとりかかったのか?
否。
守将だった浅井方の武将【堀秀村&樋口直房】を調略して味方につけたのです。
堀秀村は、近江坂田郡(現・米原市)の国人で、樋口直房はその家老でした。
秀村は父の早世によって幼いうちに家を継いだのですが、智謀に長けた直房がよく支え、家を保たせることができたといいます。
また、直房は人望も厚く、茶道や連歌などを愛する風流な人物だったとか。
信長の家老だった平手政秀と、なんとなく似ていますね。
-

平手政秀の生涯|自害した信長の傅役 その原因は息子と信長が不仲だったから?
続きを見る
周囲の町や村を焼き払い
元亀元年(1570年)6月19日に信長が出陣。
堀・樋口の離反を知った長比・苅安の砦は戦わずして撤退します。
地図で見ると以下のように勢力の色が変わったんですね。
【黄色い拠点】
・岐阜城(右)
・刈安砦(左上)
・長比砦(左下)
【赤色の拠点】
・小谷城(浅井氏本拠地)
織田軍の進行を足止めしていた2つの砦が、逆に、浅井家本拠地・小谷城を攻める前線基地になったのです。
織田軍は長比に一両日駐留し、6月21日に浅井氏の本拠・小谷城(長浜市)へ攻めかかることにします。
まず信長は、森可成や不破光治らを手前の雲雀山へ上らせ、町を焼くよう命じました。
ほぼ同時に柴田勝家・佐久間信盛・蜂屋頼隆・木下藤吉郎・丹羽長秀らにも、周囲の村や山を焼かせています。
信長自身は雲雀山に隣接する虎御前山に登り、一夜を過ごしました。
22日、織田軍はいったん後退することになります。
『信長公記』に後退の理由までは書かれていませんが、徳川家康が援軍として来ることになっていたため、合流しやすさや野戦時の布陣を考えてのことでしょうか。
このときの殿は梁田広正・中条家忠・佐々成政が務めました。
徳川軍も合流し、浅井朝倉と正面対峙
梁田広正は少なくとも、父である梁田政綱の代から織田家に仕えていた人です(この二人は親子でないとする説もあります)。
中条家忠も早くから信長に仕えていた家臣の一人で、萱津の戦いなどに参加しておりました。
-

萱津の戦いで勝家も活躍|信長公記第11話
続きを見る
彼らはそれぞれ兵を率いて、追撃してくる敵を引いては戦い、戦っては引き、見事に撤退を成功させました。
無事後退した織田軍は、この日の夜は八島(長浜市)に野営しています。
そして24日、横山の城に立てこもっていた浅井方を攻めるため、信長は龍ヶ鼻に陣取りました。
横山・龍ヶ鼻ともに現在の長浜市です。
本多忠勝や榊原康政などを率いた徳川家康とも、ここで合流しました。
それぞれの兵力については諸説あるものの、織田・徳川軍と浅井・朝倉軍でほぼ同規模だったと考えられています。
次回は姉川の戦いそのものについてみていきましょう。
あわせて読みたい関連記事
-

本多忠勝の生涯|家康を天下人にした“戦国最強武将”注目エピソード5選とは?
続きを見る
【参考】
国史大辞典
『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon link)
『信長研究の最前線 (歴史新書y 49)』(→amazon link)
『織田信長合戦全録―桶狭間から本能寺まで (中公新書)』(→amazon link)
『信長と消えた家臣たち』(→amazon link)
『織田信長家臣人名辞典』(→amazon link)
『戦国武将合戦事典』(→amazon link)