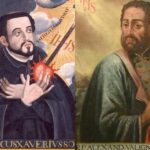ケーキやポテチもよいけれど、“和菓子”は腹持ちも日持ちもよく、何といってもお茶との相性が抜群です。
「男が甘い和菓子を食べるってちょっとなぁ」
そんな風に思っている皆さまは、ちょっとお待ちください。
天下人である織田信長・豊臣秀吉・徳川家康、そして多くの武将たちも愛したのが和菓子です。
女性的とか男性的とか気にしているのはもったいない。
6月16日は和菓子の日――そこで本稿では、権力者を虜にし、庶民に愛された和菓子の歴史をたどってみましょう

お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
甘味料は凄まじく貴重なものだった
天正10年(1582年)、本能寺の変直前。
日頃の苦労をねぎらおうと、織田信長が徳川家康に食事を振る舞い、ズラリと並んだ豪華絢爛な料理の中には、大量の菓子もありました。
当時は砂糖が高級品であり、信長がここぞというおもてなしのときに振る舞っていたものです。
※以下の記事は信長御膳の関連記事となります
-

信長が安土城で家康に振る舞った豪華な食事の中身とは?現代に蘇る信長御膳
続きを見る
信長が生きた時代は、日本の歴史において甘味の転換点でした。
古代の人々にとって、食事以外に食べる「菓子」とは、果物や木の実など。
奈良時代になると、仏教伝来とともに中国から餅や穀物の加工品である食べ物が伝わり、これらを「菓子」と呼ぶようになったわけです。
甘味料は、当時、むちゃくちゃ貴重なものでした。
餅や饅頭にしても、塩や味噌で味をつけるのが一般的で、たしかに飴や蜂蜜、甘葛といった甘味料もありましたが、大量に使われることはありません。
状況が変わるのは、まさに信長の時代で、キッカケは宣教師たちの日本上陸であります。
-

戦国時代の外国人宣教師たちは「日本すごい!」と思っていた?その本音を探る
続きを見る
食の鉄砲伝来
このころヨーロッパでは、砂糖が権力者の味として普及しておりました。
かの英国女王・エリザベス一世は、砂糖の取りすぎで歯がボロボロになっていたとか。
はるばる海を越え、欧州から日本へ上陸した宣教師たちは、祖国で流行していた「南蛮菓子」を布教の際に配布したのです。
「甘い菓子に釣られて日本人がキリスト教に興味を持たないかな?」
そんな風に考えたのでしょう。宣教師たちは、布教の許可を求めるために面会した信長にも、土産として菓子を持参します。
その衝撃たるや……。
砂糖や卵をたっぷりと使った味わいは完全に未知の世界。
カステラ、金平糖、カルメラ、有平糖……と口内に広がる強烈な甘みは、信長にとっても甘美なものだったのです。
例えて言うなら「食の鉄砲伝来」でしょうか。
長篠の戦いで鉄砲3千丁! ならぬ、大量の砂糖を菓子に投下!
この南蛮渡来の技術を信長が取り入れたのは当然のことでした。
それまでは味噌や塩味であった饅頭のあんが甘くなるのも、この頃からだったのです。
-

織田信長の天下統一はやはりケタ違い!生誕から本能寺までの生涯49年を振り返る
続きを見る
安土での饗応で、信長が家康にふるまった甘い菓子を列挙しておきましょう。
・羊羹
・薄皮饅頭
・羊皮餅(詳細は不明)
・まめあめ(大豆をいり飴で固めたもの)
・おこし米(餅米を入り飴で練ったもの)
いかがでしょう?
現代人の我々から見れば
「いかにも甘そう」
「歯に粘りつきそう」
「なにもこんなに……」
と不思議がられるかもしれません。
クドいようですが、当時の砂糖は最高の珍味であり、高級品です。
歯を飴でねばつかせながら、家康は「こんなに甘い菓子をたくさん用意できる信長さんって……( ゚д゚)」と驚愕したことでしょう。
甘いは凄い。
そういう時代だったのです。
※続きは【次のページへ】をclick!