こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【高山右近】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
信長の怒りを増さず人質を助ける方法は?
信長に取り囲まれた高槻城。
直ちに攻撃が始まり……ませんでした。
旧知のイタリア人宣教師オルガンティーノたち、つまりキリスト教関係者を使って高山右近の説得を試みます。

絵・小久ヒロ
摂津どころか、京都にいた宣教師達を全員集めたといいますから、できるだけ殺さずに事を収めたいと思っていたのではないでしょうか。
うまくいけば自軍の兵として使えるわけですしね。
とはいえ「できなかったらどうなるかわかってんだろうな?」(超訳)なことも言っていますが。
以前から右近を見知っていたオルガンティーノは、右近が「名誉のためにも、人情としても、人質を見捨てられないだろう」と理解していました。
それも含めてよく考えるよう伝えるのが精一杯で、結局、彼の力だけでは事の解決に至りません。
高山家の中でも、徹底抗戦派と降伏派で真っ二つに割れていたからです。
そこで右近は、信長の怒りを駆り立てることなく人質を助ける方法を考え出します。
たった一人、紙衣(和紙の着物・下着によく使われていたもの)に丸腰という無防備な姿で、信長の下へ向かったのです。
これならば、城兵ごと信長の元へ行ったわけではないので村重を裏切ったことにはならず、信長へは反抗する意思がないことを示せる――頭いいですね。
信長は右近の意思を汲み取り喜びました。

織田信長/wikipediaより引用
自らが着ていた服や馬、そして改めて高槻城主の地位を与え、降伏を認めたのです。
当時エライ人が着ていた服をもらうというのは名誉なことでした。
この話は旧暦11月=だいたい新暦12月のことですので「それだけじゃ寒いだろ、許してやるからとりあえずこれでも着とけ」というちょっとした優しさもあったかもしれませんね。
高槻周辺の寺社は衰退との記録も残る
村重も、右近の予測通り人質を殺すことはせず、高山家は本領の4万石を安堵されるなど、穏便に済ませてもらうことができました。
一方、村重はどうしたか?
という、信長の気に障るフルコンボをキメています。
結果、有岡城に残された村重の一族や妻子は、信長の指示によってかなり残酷な処刑をされてしまいました。

荒木村重の籠もった有岡城(伊丹城)
松永久秀などもそうですが、信長は裏切られた場合にも一度は説得を試みます。しかしそれでも戻ってこないとなった場合には容赦しません。
しかもこれまで何度も裏切りにあっていますから「締めるべきところは締めておかないと、この先、信忠の代になっても似たようなことが起きかねない」とも思ったでしょう。
この頃には織田家の当主は嫡男の織田信忠に譲っていましたので、後年への禍根を断つ意味もあったと思われます。
武田征伐を見る限り、信忠も決して甘いタイプではありませんが……信長は、信忠の果断な面が強まって恐怖政治一辺倒になり、かえって裏切りを多発させることを懸念したのかもしれません。
しかし、それもあまり意味はなかったのかもしれません。
天正10年(1582年)6月、本能寺の変が起き、他ならぬ信長が明智光秀に討たれてしまうのです。
秀吉時代
本能寺の変の後、高屋右近はどうしたか?
秀吉軍に加わり、山崎の戦いで先陣を務め、その後は秀吉派として動きました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
天正十一年(1583年)4月には【賤ヶ岳の戦い】にも参加。
秀吉も右近を評価して、天正十三年(1585年)に明石6万石へ転封させました。
その後は根来衆征伐や四国征伐など、秀吉による天下統一事業に参加し続けます。
ただし、父の友照と同じく、キリスト教以外には厳しい態度で臨んだようで、高槻周辺では「高山右近の時代に衰退しました」とする寺社の記録も多いとのこと。
右近は多くの大名がキリシタンになるきっかけになる程の影響力を有していたため、民衆もそれにならった結果、寺社が廃れたのかもしれません。
九州のキリシタン大名として有名な大友宗麟については「寺社を徹底的に破壊しました」という記録があります。その点、右近のほうがまだ優しかったかもしれません。
右近はセミナリオ(キリスト教の神学校)を建てる他、慈善活動もしていたので、ベースが優しい人だったのでしょう。
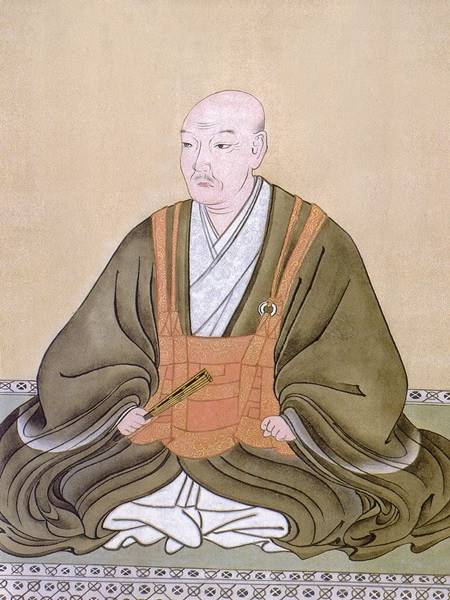
大友宗麟こと大友義鎮/wikipediaより引用
領地も財産も全て投げ出して信仰を貫く
人付き合いのよさで知られていた高山右近は、キリシタン以外にも細川忠興や前田利家との親交がありました。
「忠興の妻・細川ガラシャ(旧・明智玉子)は右近の話を夫から聞いてキリシタンになった」
そんな説もあるぐらいですから、右近はかなり話し上手なタイプだったのかもしれませんね。
しかし、時代は少しずつキリシタンに厳しい方向へ進んでいきます。
特に秀吉が九州征伐の後、バテレン追放令を発布すると、キリシタン大名の中には棄教を選ぶ人も出始めました。
そうなっても右近は信仰を貫きます。
それどころか、秀吉に対し
「領地も財産も全て差し出しますので、信仰を守ることをお許しください」
と、自ら願い出たので、秀吉も世間もビックリ仰天。
思い切りの良さでこの願いは聞き届けられました。
そしてその後は小西行長の領地だった小豆島や天草に隠れ住んだ後、前田利家に客将として招かれ、

前田利家/wikipediaより引用
1万5000石をもらって家政や建築・修繕などに取り組んでいます。
この時期が右近の人生で一番穏やかな頃だったかもしれません。
※続きは【次のページへ】をclick!
