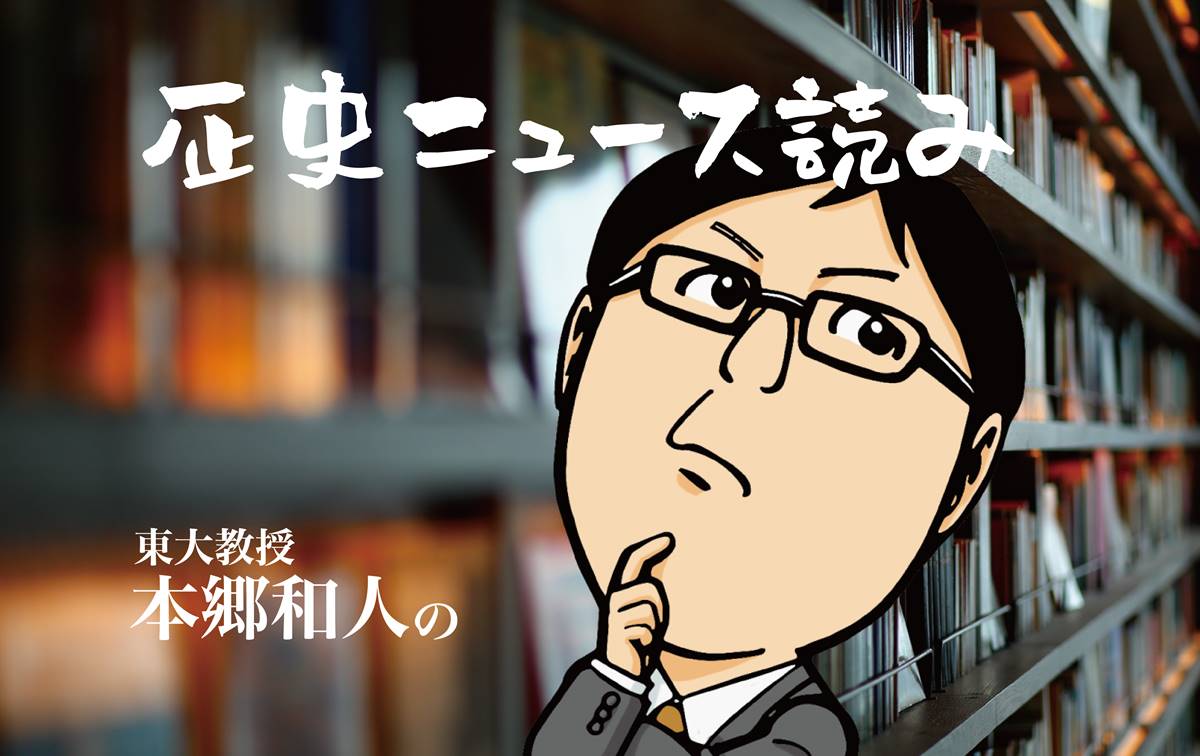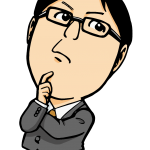日本中世史の本郷和人・東大史料編纂所教授が歴史ニュースに注目する「歴史ニュースキュレーション」。
今週のメインテーマは「大大名から転落した織田信雄が、現代まで織田信長の系譜を残す」です!

織田信雄/wikipediaより引用
織田信雄が秀吉に焦りの書状
◆織田信雄、秀吉宛てに焦りの書状 清洲会議3日前、中京大2教授発表/読売新聞 2016年06月19日 ※現在はリンク切れ
姫「へー。こういう文書が古本屋さんで売っていることがあるのね-」
本郷「そうだねー。お二人の先生はよく見つけたな-」
姫「ぱっと見て、本物かどうかを見抜かないといけないから、たいへんよね」
本郷「まちがって偽物を買ってしまったら大損だものね。まあ、長年研究してると、偽物はすぐにわかるんだけれどね。ただ、巧妙なものもあるので、要注意だなー」
姫「そうかー。で、この織田信雄の書状なんだけれど・・・、あ、そもそも信雄ってなんて読むの?よくいわれる『のぶかつ』でいいの?それとも『のぶお』なの?」
本郷「彼は信雄を称する直前に『信勝』を名前にしていたんだね。だから、のぶかつ、と読んでもいいんじゃないかな」
姫「ああ、そうなんだ。でも、もう一声、ほしいわね」
本郷「三重県に菰野っていう町があるでしょう?」
姫「こもの? 小物? 小物といえば、あなたじゃないの」
本郷「その小物じゃなくて、菰野ね。湯の山温泉の山麓にある町だ。大ヒットを記録したコミック『高杉さんちのお弁当』の最終巻にも出てきたでしょ、湯の山温泉」
姫「ああ、昔はとても賑わっていたけれど、最近は観光客がだいぶ減ったという温泉ね」
本郷「うん。ざんねんな話なんだけれどね。がんばって復活してほしいね。で、その山麓にある菰野は江戸時代を通じて土方氏1万2,000石の城下町だったんだ」
姫「規模は小さいけれど、江戸時代を生き抜いたのね。継続は力なり。立派ね」
本郷「そうだねー。それで、藩祖が雄氏で、代々のお殿様は、みんな名前に『雄』の字がつく。『雄◯』という名前なんだ。それで、雄氏のお父さんが雄久。この人は織田信雄に仕えていた」
姫「なるほどねー。あなたの言いたいことは、分かったわ。雄久は信雄から一字を拝領したのね。それで、江戸時代を通じて菰野のお殿様は『かつ◯』を諱とした。すると、信雄は『のぶお』ではなく、『のぶかつ』と読んだのだろう、と」
本郷「大当たりー。どう、これなら、実証的でしょう?」
姫「うん。私は納得した。織田信雄は、おだのぶかつ、か。なるほど。じゃあ、忠臣蔵の大石内蔵助もよしお、じゃなくて、よしかつ、かな?」※編集部注:大石良雄
本郷「うーむ。それは違うかな。内蔵助はよしお、もしくは、よしたか、と読んでるよ」
姫「人の名前は難しいわねー。まあ、そればっかりやっていても仕方がないので、次いきましょう。信雄は織田信長の次男になるのよね」
本郷「うん、そうだね。お母さんは、長男で信長の後継者の信忠と同じ。信忠、信雄、徳姫が同母の兄弟と言われているね」
姫「徳姫は徳川家康の長男の松平信康と結婚した女性よね。それから、三男の信孝の方が実は年長という話を聞いたことがあるけれど」
本郷「うん。そういう説はあるけれど、本当はどうなのかな。まあ、お母さんの格として、信孝よりも信雄の方が上だったというのは確かみたいだね。織田家の序列は、まず信長がいて『1.信忠、2.信雄、3.信包、4.信孝』の順だったらしいよ」
姫「3席の信包というのはどんな人?」※編集部注:信包(のぶかね)
本郷「信長の弟。同母弟といわれている。小谷城が落ちたあと、お市の方と後の淀殿以下三人の姫の面倒を見たのがこの信包さんだ。秀吉の時に伊勢の津15万石を領する有力大名だったんだけれど、文禄年間に秀吉の怒りを買い、所領を没収された。それからしばらくして秀吉の御伽衆になり、丹波柏原(かいばら)3万6,000石を与えられた」
姫「へー、そんな人がいたんだ。そうそう。柏原は、かしわばら、じゃなくて、かいばら、って読むのよね。ええと、なになに、かつては氷上郡柏原町だったけれど、2004(平成16年)に氷上郡6町が合併し丹波市が誕生したことにより消滅、旧町域は丹波市柏原町となった、ですって」
本郷「そうなんだ。いまは丹波市の一部か。あとで出てくるから、覚えておいて。で、話を元に戻すと、三男の信孝は相当に優秀だったらしい(ルイス=フロイス)けれど、信雄は凡庸だったみたい。彼の才能をほめている資料は見当たらないな」
姫「あらま。だけど、本能寺の変の後、彼が織田家をつぐという可能性はあったのよね。だって、同母の嫡男の信忠は二条城で討ち死にしているし。信孝はだいぶ信雄より格が下なわけだし」
本郷「そうだね。だけど、信孝には謀反人の明智光秀を討った功績がある。天下分け目の天王山、山崎の戦いも、秀吉軍の名目上の大将は織田信孝なんだ」
姫「そうか、それで柴田勝家は清洲会議で信孝が跡継ぎに、と訴えたのね」
本郷「そうそう。信雄を後継者に、と主張する人は誰もいなかった。そんな空気を事前に察していたから、信雄は秀吉によしみを通じようとしたわけでしょうな」
姫「清洲会議の結果、信雄はどういう処遇を受けたの?」
本郷「信孝に美濃が譲られた一方で、信雄は尾張と、伊賀と、南伊勢をもらった。石高にすると100万石近いよね」
姫「居城はどこ?」
本郷「うーん、しばらく後だと伊勢長島なんだけどね。当時は長島には滝川一益がいるでしょ。あ、そもそも北伊勢は彼の所領じゃないしね。北畠の養子だった頃には田丸城を居城にしていて、そのあと松阪の松ヶ島城に移ったというから、この時点では松ヶ島城なのかな。ごめん、よく知らない」
姫「それで、賤ヶ岳の戦いまでに織田信孝、柴田勝家、滝川一益が没落する。そのあとはどうなったの?」
本郷「北伊勢を所領に加えられてね。さっき言ったように、長島に移る。さらには清洲に移ってるみたいだね」
姫「大きな所領を持っていたわけねー。でも秀吉と対立してしまって、徳川家康と結んで、小牧・長久手の戦いを引き起こすわけね」
本郷「そういうこと。それで、伊勢の多くと伊賀を秀吉に割譲した。でも、尾張はしっかり確保していたわけだ。まだまだ大大名だね」
姫「でも、所領をきれいさっぱり失うのよね、たしか。いつだっけ? 家康が関東に移されるのにつれて、駿府などの家康の旧領に移れと言われたのを拒否。秀吉の怒りを買って所領没収、という流れだったかしら」
本郷「そのとおり。家康は唯々諾々と関東に移って、実力を蓄えたのにね。もったいないことをしたねー。」
姫「その後の織田信雄、あるいは織田家はどうなるの?あんまり知られてないわよね」
本郷「そうだね。まあいろいろあったのだけれど、それは別の機会にお話ししよう。信雄は結局、御伽衆に加わって1万8,000石かな。それから、幕末まで大名として残る織田家は2系統4家。信雄の子孫が2家と、信長の弟の長益(有楽斎)の子孫が2家なんだ」
姫「長益という人は茶人として有名よね。有楽町という呼称の元になった人でしょ」
本郷「そうだね。信雄の方は、彼の四男・信良の系統が出羽天童藩主となった。将棋の駒作りで有名だね。五男・高長の系統は、当初、大和宇陀松山藩主で、やがて先に言及した丹波柏原藩主となった。信包の子孫が絶えた後に入るんだ。石高は天童も柏原も、ともに2万石くらい」
姫「あなた、この前、旧華族の織田家の方とテレビに出てたわよね」
本郷「うん。それは信雄の子孫に当たる、信孝さん。柏原の織田家の方なんだ。とても気さくな方だったよ。お子さんには『信』の字をあえてつけなかった、とおっしゃってた」
姫「旧家の方も、新しい歩みを始めていらっしゃるのね」