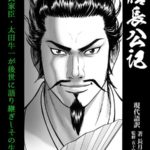こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【比叡山焼き討ち】
をクリックお願いします。
言継卿記も信長公記も全て鵜呑みにはできず
この説には二つ根拠があります。
一つは記録について。
延暦寺焼き討ちの悲惨さを記録した資料を書いた人は、ほぼ全員その場にいない人なのです。
『言継卿記(ときつぐきょうき)』を書いた公家の山科言継(やましなときつぐ)も、『御湯殿上日記』を代々書いてきた朝廷の女官達も皆、伝聞を書いたにすぎません。
伝言ゲームで話が誇張・脱線するのは今も昔も変わらないでしょう。
一応、信頼度はあるとされている『信長公記』でもこの事件のあらましが書かれていますが、作者の大田牛一は「文才がありすぎて誇張が激しいのでは?」という傾向があります。
要は「盛る傾向がある」んですね。
なんせ、その場にいなかったのに【本能寺の変】についてもかなりリアルに書かれていたりします。
-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは
続きを見る
だからといって延暦寺焼き討ちの記述が丸ごと嘘っぱちとは言えませんが、ここでは、更にもう一つの根拠を考えてみたいと思います。
信長が残虐であればあるほど得をするのは誰か
それは、延暦寺が朝廷と深い繋がりがあったということです。
信長が焼き討ちを行ったとされる頃、延暦寺のトップは天皇の弟さんでした。
いくら信長が「神をも恐れぬ」とはいえ、そんな人のいるところを丸焼きにしていたら、当然朝廷からお咎めがあるはずです。
朝敵にされていてもおかしくありません。
信長は既に周辺の大名達から包囲されていたので、朝廷がその大名たちに「信長は朝敵だから協力して討つように!」と命令すれば、すぐに何らかのダメージは与えられたでしょう。
にも関わらずそうしておりません。
果たして“全山焼き討ち”などあったのか、非常に疑わしくなってきます。
信長を信奉していた太田牛一が、信長の非道を大きく書くワケがない――というツッコミもあるかもしれませんが、すでに軍事拠点として当たり前のように存在していた集団はもはや軍であり、その敵をド派手にやっつけた、さすが信長様!という風に書いたのなら合点がいきます。
やっぱり「盛ったのかなぁ」と。
なお、この一戦で最も武功があったとして、明智光秀が近江志賀郡を与えられ、坂本城の築城を始めました。
ここが非常に重要な拠点だということは以下の地図を見ていただければおわかりかと思います。
・赤が岐阜城
・紫が1579年に完成する安土城
・黄が坂本城 ※1571年頃に完成します
要は、岐阜から京都へ続くルートの喉元にあたる位置なんですね。
琵琶湖の水上交通も利用しており、後に長浜エリアを与えられる豊臣秀吉より、光秀の方が先に出世を果たしていたことがわかります。
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
つまりは、比叡山と麓の坂本を攻略したという軍事的意義が大きな戦いでした。
比叡山そのものを焼き尽くすことより、拠点を押さえるという観点で考えた方が自然なんですね。
なお、明智光秀の生涯については以下の記事を併せてご覧いただければと存じます。
あわせて読みたい関連記事
-

明智光秀の生涯|ドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多き一生を振り返る
続きを見る
-

興福寺・延暦寺・本願寺はなぜ武力を有していた? 中世における大寺院の存在感
続きを見る
-

志賀の陣と宇佐山城の戦いで信長再び窮地|信長公記第74話
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
【参考】
国史大辞典
峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)
谷口克広『織田信長合戦全録 桶狭間から本能寺まで』(→amazon)