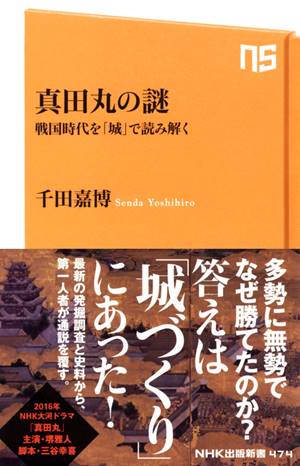こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【信玄と城】
をクリックお願いします。
大坂城の「真田丸」も丸馬出しの発展形だった
丸馬出しとは?
簡単に説明すると、城内を隠すようにして門の前面に張り出した半円状の防御施設で、半円状の脇から将兵たちが城の内外へと出入りできるようになっています。
半円状の堡塁の前面は堀にしておき「三日月堀」と呼ばれます。

こちらは掛川城の三日月堀になりますがご参考にどうぞ
「丸馬出し」は城の最大の弱点である門を防御すると同時に、城内の様子も半円状の堡塁で見えなくして、さらに出撃する兵士がどれだけの数で出てくるのかを分からなくする効果があるんですね。
城門の最終形態である「枡形虎口」も同様の機能を持ちます。
が、枡形虎口は誘い込んで殲滅させる威力を持っていて、より防御に徹しています。
ちなみに「丸馬出し」の最終形態は大坂城の真田丸です。
城郭研究第一人者の千田嘉博先生によって【真田丸が独立した城砦】であると目される以前、真田丸は大坂城にくっついた巨大な丸馬出しだと考えられておりました。
防御によし、攻撃によし――。
ということで、武田の流れを汲む真田信繁(真田幸村)が作り上げたと思われたんですね。
千田先生のご著書を拝読しますと、確かに独立した城砦のように思えてきますが、それまで丸馬出しだと思われていたのは、さほどに強固な防御施設だったからとも言えるでしょう。
このように、戦国武将の戦略を考えると、何がしたくて目の前の城を建てたのか、何が狙いだったのかを理解できて、よりお城を楽しめることができます。
お城の大原則はこうです。
「すべての城にはそこに建てられた意味がある!」
存在した意味を知ろうとすれば、どんなにちっぽけで現代では埋もれてしまった城跡でも、時空を超えて甦ります(脳内で)。
そしてそれはもうマニアの境地です。
こちらの世界へようこそ。
北信濃へ進出!ついに生涯の仇敵と
さて、信濃地方をどんどん北上して行った武田信玄は途中、村上義清の砥石城で惨敗を喫したりしながらも(惨敗しても帰るべき支城と本拠地があるので、立て直しが利く)、ついに北信濃に進出。
ところが、そこに越後から上杉謙信がやって来ます。
武田信玄は、そこでほぼ初めて、大国を相手にするわけです。
ここでどのような戦略を構想したのか。
前線基地を築城したのか。
後には、信濃の山を越えて上野(こうずけ・群馬県)や、はたまた南の駿河、西の美濃にも進出し、城の数もますます増えていきます。
時代と共に丸馬出しや他の城の機能も洗練されていきました。
「武田信玄の城」は一体どのような最終形態になっていったのでしょうか。
以降は【川中島の戦い】と密接に関わってくるため、以下の別記事にてご報告させていただきます。
実は、これらの超有名な合戦も城と密接にリンクした詰将棋のような展開だったりして、二人の軍神の思慮深さに驚かされます。
あわせて読みたい関連記事
-

第一次川中島の戦い ポイントは塩田城~信玄も謙信も城を中心に動いていた
続きを見る
-

たった1つの山城(旭山城)が戦の趨勢を左右した 第二次川中島の戦いを振り返る
続きを見る
-

第三次川中島の戦いは「真田の調略」と「信玄の緻密な攻城戦術」に注目だ!
続きを見る
-

第四次川中島の戦い~信玄vs謙信の一騎打ちがなくても最大の激戦になった理由
続きを見る
-

第五次川中島の戦いは地味じゃない 関東から越中までを巻き込む大構想だった?
続きを見る