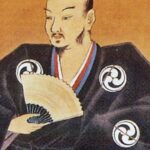こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【中村一氏の生涯】
をクリックお願いします。
秀吉の関白就任に伴い従五位下
防戦に成功した中村一氏の働きは報われました。
天正十三年(1585年)7月、秀吉が関白就任を果たすと、一氏には従五位下・式部少輔の官位が与えられます。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
さらには近江と伊賀に6万石を与えられて水口岡山城(滋賀県甲賀市)の主となり、豊臣秀次付きの「年寄衆」も任されました。
この場合の年寄とは、老人ではなく、家老に近いニュアンスです。
秀次は、まだ跡継ぎとはなっていませんが、秀吉から見た一氏は、
「豊臣政権の次世代を補佐するに足る人物」
という評価になっていたのでしょう。
小牧・長久手の戦いにおいて秀次が失態を犯したため、実戦経験が豊富な一氏の補佐を期待したとも考えられます。
天正十八年(1590年)の小田原征伐では、秀次に従って小田原城の支城である山中城(静岡県三島市)攻めに加わっています。
この城は、改修が間に合わなかったことも影響してか、スンナリ落ちたため、秀次や一氏も胸をなで下ろしたことでしょう。
なんせ“障子堀”のインパクトなどは凄まじいものがあり、その眼前に立てば攻める気を削がれそうで……。

山中城跡の障子堀

山中城障子堀を別の角度から
小田原城が落ちると、同年7月には駿河で14万5000石を与えられ、駿府城主となりました。
その後は伏見城や大和多聞城の工事に携わったり、駿河にあった秀吉直轄領の代官を兼任したり、引き続き重要な仕事を任されています。
一方で、豊臣秀次の家老については、どこかのタイミングで離れていたと考えられます。
文禄四年(1595年)に秀次が自害して、残された妻子らが軒並み処刑された事件の際、一氏はいっさい問われていないのです。
むしろ一氏は、秀次に連座したとして前野長康・景定の親子を預かる立場にいました。
先に景定へ命令が下ると、その後、長康も切腹という哀しい結末を迎えています。
※長康は命令が出る前に息子の後を追ったという説も
一氏にとっては旧知の仲ですので、こんな最期を見るのは非常に辛いものだったでしょう。
関ヶ原には不参戦
慶長五年(1600年)、関ヶ原の戦いでは、どうなったのか?
普通に考えれば西軍サイド……かと思いきや、徳川家康を中心とする東軍に加わるつもりでいたようです。
しかし、家康が上方から会津へ出陣した同年6月、中村一氏は重い病に臥せっていました。
そのため弟の中村一栄を名代として従軍させています。息子の中村一忠はまだ13歳だったので、その代理を弟に任せたのでした。
二重の代理ですので、一栄としてもプレッシャーだったでしょう。
しかし、それ以上に一氏の病がかなり重篤なものだったらしく、いざ関ヶ原の戦い(1600年10月21日/慶長5年9月15日)が始まる約2ヶ月前の、1600年8月25日(慶長5年7月17日)に亡くなっています。

関ヶ原合戦図屏風/wikipediaより引用
この日は西軍方が家康の違反行為を弾劾する『内府ちがひの条々』という手紙を諸大名に送った日でもありました。
おそらくこの手紙は、受け取った大名が後に処分したと思われるため、誰に送られていたのか不明ですが、一氏のもとへ届いていた可能性は高いでしょう。
息子の中村一忠は東軍についたことを評価され、伯耆米子で17万5000石に加増。
その後、徳川秀忠から偏諱を受けたとして「忠一」に改名し、首尾よく徳川家との接近を進めてゆきます。
忠一は慶長十四年(1609年)に20歳の若さで亡くなってしまいますが、側室の生んだ子の家系が江戸時代を通して存続、現代にも血筋が続いているとか。
生き延びることが勝利だとするならば、彼と中村家もその一員ですね。
あわせて読みたい関連記事
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

別所長治の生涯|織田を裏切り戦国一凄惨な籠城戦へ追い込まれた播磨の名門武将
続きを見る
-

森長可の生涯|信長に期待され「人間無骨」を操る鬼武蔵は蘭丸の兄だった
続きを見る
-

小田原征伐で秀吉相手に退かず!北条家の小田原城はどれだけ堅強だったのか?
続きを見る
参考文献
- 菊地浩之『豊臣家臣団の系図(角川新書)』(KADOKAWA, 2019年11月10日, ISBN-13: 978-4-04-082325-6)
出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 滝沢弘康『秀吉家臣団の内幕―天下人をめぐる群像劇(SB新書)』(SBクリエイティブ, 2013年9月18日, ISBN-13: 978-4-7973-7425-4)
出版社: SBクリエイティブ(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊)
出版社: 吉川弘文館/JapanKnowledge(公式案内)