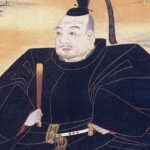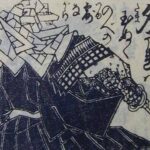こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【戦国大名は合戦前の占いを重要視していた?】
をクリックお願いします。
占いよりも好機を優先した秀吉
明智光秀と対峙するため毛利家と和睦し、京都へ向かっていた秀吉。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
一般的にその進軍は【中国大返し】とされ、最近では「普通の進軍だった」とも指摘されますが、『川角太閤記』にこんな話が載っています。
秀吉は旅の途中で一日だけ休息を取らせた。
そして6月9日に再度出陣を命じたところ、そこへ普段から祈祷を頼んでいた僧侶が現れた。
「明日は出発するには縁起が悪く、二度と帰れなくなります」
僧侶の占いに対し、秀吉の回答はこうだ。
「それならむしろ吉日である。わしは殿のために討死する覚悟で行くのだから、この城に戻ろうなどとは考えていない」
秀吉はそう言って、予定通りに出発。
結果的には大正解という行動となった。
『川角太閤記』は秀吉家臣・田中吉政の配下の者がまとめたもので、素朴な書き方からして、無茶な作り話を載せているものではない、とされます。

秀吉ほど回転の速い頭脳の持ち主でしたら、普段から
「なんでもかんでも否定せず、自分に有利なように解釈を持っていこう」
と考えても不思議ではありませんよね。
天下人になった後のイメージ作りにも余念がなかった人物ですし、占いによって士気や行軍速度が下がることを懸念しての言動という可能性はいかにもありそうです。
リーダーが堂々としていないと、部下のやる気が雲散霧消してしまいますものね。
他にも、鍋島直茂が家訓『直茂様御教訓ヶ条覚書』で
「くじや占いは大きく外れることもある」
と書いており、盲信を戒めています。
肯定派
本人が占いのことをアタマから信じているのかどうか――それは置いといて、とにかく最大限に活用した人もいます。
代表が徳川家康でしょう。

徳川家康/wikipediaより引用
家康は、江戸の街作りにおいて、占いや縁起などをかなり気にしていたことがよく知られています。
例えば江戸城の鬼門・裏鬼門には街を代表する徳川の寺が設置されています。
鬼門=北東に寛永寺
裏鬼門=南西に増上寺
江戸を本拠地にしたのも、占いからきたものと考えることもできます。
これまた中国由来の考えを発展させた「四神相応」という験担ぎの方法があります。
東=青龍→川
西=白虎→道
南=朱雀→池
北=玄武→山
東西南北をそれぞれの地形に見立て、これらの中心に都を築くのが望ましいというものです。
平安京など古代の都はこの考えに基づいて土地を選んだとされています(否定する説もあります)。
これを江戸(関東)に見立てると、どうなるか?
江戸の場合
東:江戸川
西:中山道
南:東京湾(当時は江戸湾)
となり、北はかなり離れて日光山あたりですかね。
南も少々無理矢理感がありますが、かつて京都にあった巨椋池(おぐらいけ)は度重なる工事でどんどん小さくなってしまったことを考えると、干拓が行われない海を見立てたのは正解だったかもしれません。
どんどんオカルトめいた話になっていきますが、家康の行動には
「何が何でもウチの政権を長く保たせる。そのためにはありとあらゆる手を使う」
といった強い意志が感じられますし、おそらく占いもその”手”のひとつだったのではないかと思われます。
神仏への信仰と占いは別派が多い
戦国大名の多くは、寺社への援助や修繕などを積極的に行っています。
例えば織田信長も、桶狭間の前には熱田神宮に詣でて戦勝祈願をしましたし、そのお礼のような形で”信長塀(のぶながべい)”という塀を造りました。
信長の場合「家臣や兵たちの信仰を利用し、神社で団結を図る」狙いだったことが浮かんできますね。
後にキリスト教vs法華宗の対決や、安土宗論などもさせているあたり、
「神仏など全てくだらん!両方黙れ!!」
という決めつけはしていません。
周囲の者たちの信仰心は尊重していたのでしょう。
しかし皇室や大きな寺社が絡むと、さすがの信長も占いを無視できなかったようなケースもあります。
天正七年(1579年)石清水八幡宮における修繕工事の起工式
天正八年(1580年)二条御新造を東宮(当時は誠仁親王)に献上した際の引っ越しの日取り
上記は、皇室が陰陽博士に占わせて決めたものであり、信長が「さっさと決めろ!」とゴリ押しした気配はありません。
「占いを信じない」=「否定していた」
というより、
「当事者が重視しているものを優先すべき」
と考えていたように見えます。
寺社の庇護はインフラ整備や雇用創出、民衆のメンタル安定、治安維持などに役立ちます。
ゆえに占いの結果とか信頼などとは関係なく、為政者としては日頃から手をかけておくことが重要なのでしょう。
現代ではまとめて「迷信」「スピリチュアル」と扱われやすい事柄ですから、興味深いですね。
盲信すると全く動けなくなってしまいますし、信じている人を頭ごなしに否定すると不和を生んで、違うところに悪影響が出たりもしますしね。
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

なぜ阿野全成の占いは頼朝に重宝されるのか?鎌倉殿の13人新納慎也
続きを見る
-

安倍晴明の生涯|史実の陰陽師はどんな仕事をしていた?天皇や道長にも祈祷
続きを見る
【参考】
小和田哲男『家訓で読む戦国 組織論から人生哲学まで NHK出版新書』(→amazon)
太田 牛一・中川 太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)
ほか