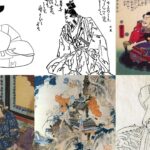こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【平為賢】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
オラオラ系ストーカー「大夫監」
若き光源氏が情けを交わすも、頓死を遂げてしまった夕顔。
彼女と頭中将の間にいた幼い姫は、夕顔の乳母が養うことになりました。
その乳母の夫が太宰少弐(だざいのしょうに・太宰府の次官)に任命されため、乳母は姫を連れて筑前国に住むことになります。
しかし――あの太宰少弐のもとに、なにやら高貴な姫がいるらしい――そんな噂がいつの間にか知れ渡ってしまい、現地の男たちから様々な恋文が届くようになります。
困り果てた乳母は「姫は体が悪く、人の妻になれる身とも思えぬため、尼になるつもりだ」と求愛者たちを遠ざけようとしました。
ところが肥後国の豪族である大夫監(たゆうのげん)は強引でした。
歳のころは三十すぎ。
色が黒く健康的。
現代人ならば、むしろ好ましい健康的な肉体は、当時の貴族からは野蛮でおぞましいもの扱いされてしまいます。

画像はイメージです/wikipediaより引用
美女と聞けば自分のものにせねば気が済まない好色の彼は、噂を聞きつけるや激烈なアプローチを開始。
夜は更けてからそっと忍んでくるからこそ「夜這い」なのに、日の高いうちから姫のもとへやってきて、ひとりよがりな歌を詠んでくる様は実に鬱陶しいものでした。
後に姫は「あの鼻息や気配を思い出すだけで気分が悪くなる」と回想します。
距離感の詰め方がいかに強引だったか、わかろうものです。
しかも、大夫監は地元において絶大な権力があります。
あれほど姫を思う乳母の家族ですら、長男以外の息子は「ここで生きていくうえには彼と持ちつ持たれつの方がよいから」と、大夫監にあっさり協力するようになってしまう。
彼らの関係性からは、朝廷に派遣された官吏より、それを取り込む地元豪族の方が権力を持つことも伝わってきます。
また、都にいる限り、強引な男君からのアプローチも、あしらい方があります。
光源氏にしても、高貴な血筋と権力で強引な迫り方をしているものの、それでも振られたことはあったものです。
しかし、大夫監は甘くありません。
「あの男に逆らったら何をされるかわかったものではない……」
乳母たちはそう怯え切っていました。なにせ我が子ですら権力に籠絡されていて、もはや猶予はないのです。
結局、乳母は姫と信頼できる者を引き連れて、高速船に乗り込み、全速力で都へ逃走。
彼女たち一行は、船の速度に危険を覚え、海賊に襲撃されないか気を揉み、さらには「大夫監が逃亡に気づいて追いかけてきたらどうしよう……」と怯え切っていました。
『源氏物語』の中にも、こんなスリリングな展開があるんですね。
この一行は、何のツテもなく、後先考えない逃亡であり、偶然、顔を見知った光源氏の女房と再会しなければ、どうなっていたかもわかりません。
しかし、そうまでして逃げるしかない、大夫監とは一体何者なのか?
物語に登場する他の男君とは明らかに異質。
彼個人の個性だけでなく、背後には権力と暴力が垣間見えていて、彼は何か思い上がっている。
なんせ「姫はお体が悪く、誰であれ、到底お相手できない」と乳母が断っても、この調子です。
「なぁに、国中の神も仏も拙者の思うがまま! 姫の目が潰れていようが足が折れていようが治してみせますぞ、ガハハハ!」
なんなのでしょう。
ラブコメディに反社会勢力の男が入り込んでいるような場違い感と申しましょうか。ヤクザ映画の親分のような印象すら受けます。
従五位という都では小馬鹿にされる程度の官位でありながら、現地ではそれこそやりたい放題の大夫監。
姫が都に辿り着き、光源氏の庇護を受け、「玉鬘」と呼ばれるようになると、物語からは自然と消えて行きます。
しかし、実際の歴史はそうではない。
不穏な要素は、消え去ることなく連綿と続いてゆくのです。
大夫監の示す危険性
大夫監は、物語のキャラクターとしてお笑い枠であっても、実におそろしい存在です。
低い官位であろうと、地元では好き勝手に振る舞うことのできる豪族。
治安が保たれておらず、道ゆくだけで海賊や山賊の襲撃を受ける状況。
しかし、その賊の襲撃に反撃することができれば、好きなだけ国境をまたいで移動できる機動力を持てる。
太夫監は肥後国在住で、太宰府は筑前国にあります。それを国境などないように平然と移動して、あろうことか姫君の居場所にまでノコノコ入り込んでくる。
一行の怯え方から察するに、本気を出せば都へ向かう道筋まで追いかけてこられます。
当時の政権は、正常な国家としての機能は、あくまで都周辺に限定されていました。
そんな状況で、もしも武力行使できる集団が地方で力を持てばどうなるか?
こうしたリスクを朝廷はどう考えていたのか?
『源氏物語』「桐壺」では、桐壺帝が桐壺更衣を深く寵愛することが、白居易の『長恨歌』を引きながら不吉なこととして語られます。
しかし、歴史を鑑みるうえで、その読み解きだけでは不十分。
唐玄宗が楊貴妃を寵愛し、政務を怠った結果、惨憺たる事件が起きてしまいます。
【安史の乱】です。
その最中に楊貴妃は命を落とす。一体なぜこんなことになってしまったのか?
理由は簡単、武力です。
節度使であった安禄山が、朝廷の目の届かぬ地方で強大な権力と武力を有し、戦乱が巻き起こったのです。

安禄山/wikipediaより引用
大夫監のように武力を持つ地方豪族は、いわばミニ安禄山です。
姫君に迫るだけならまだ可愛いもので、もしも何らかの野心を抱いたらどうなることか。
「玉鬘十帖」は、来たる時代を予見しているようにすら思えます。
光源氏と紫の上の愛を中心としたプロットとは異なり、当時の貴族を突き放したようにすら見えるのです。
地方にいけば都の流儀など通じない。
玉鬘からみた都の貴公子たちは、光源氏を筆頭にしてどこか頼りなく、偽善的であった。
結局、玉鬘は、都の貴族の中でも一風変わった、黒々とした髭が特徴的な「髭黒」と結ばれます。
紫式部が武士の世の到来まで予見していたとは思いません。
しかし、地方で武士が勢力を伸ばしつつあることを聞きとめ、何らかの変化は感じ取っていたのかもしれません。
大河ドラマ『光る君へ』では『源氏物語』が生み出された時代背景が描かれますので、物語後半になって武士が台頭してゆくことは当然の帰結と言える。
そこで登場するのが、武士として大きく紹介される平為賢。
彼が玉鬘のような美女に鼻息荒く言い寄っていたかどうか、そこはわかりませんし、描かれることもないでしょうが、大夫監と共通する点が多い人物像ではあります。
東国から流れ、九州に居座り、その名を聞くだけで皆が震え上がってしまう。
都の貴族とは違い、無骨で健康的――彼もまた、実は『源氏物語』の世界と通じる人物なのです。
「文官上位」の脆弱性
平為賢はじめ、この時代の武士の記録は曖昧です。
生没年がわからない。
別人の活躍と混同される。
ルーツすら不明瞭。
そういうことが往々にしてあると念頭に置いておくとよいと思います。
東アジアの伝統として【文官上位】があります。
不祥の器(ふしょうのき)である“兵”を司る武官に、強い権限を持たせると災いになる。
軍事増強にばかり資産を用いては国が発展しない。
ゆえに文官が上に立って統制する仕組みであり、シビリアンコントロールという概念と通底するものがあります。
ただし、それが極端になり、かつ外交政策を怠ると弊害がでます。
平安時代、有力な地方武士の記録すら曖昧だった朝廷は、大変危険な状態にありました。
そんな武士の一人である平為賢も、不明点ばかりです。
生没年も不明。確たる素性がわかっているのは父が平維幹であること。官位が従五位下であること。そして【刀伊の入寇】で活躍したことくらいです。
生年は不明であっても、功績があり、国土防衛を担うにふさわしい人物であれば、死の年代や状況はわかっていてもおかしくはありません。
それすらわかっていない。
平為賢自身の問題ではなく、当時の朝廷や公卿が武士を軽んじていた意識の表れといえるでしょう。
『光る君へ』は当時の政治状況も描いています。
そこから見えてくるのは、当時の政治が機能不全であったことや、外交意識がほぼなかったことです。
都での政治闘争にかまけている危険性は随所に感じられます。
日本史では、外敵の侵攻が決定打となはりません。文官側が武官を権力闘争に用いた結果、なし崩し的に政権交代へ向かってゆきます。
玉鬘は、地方武士である大夫監から逃げおおせました。
しかし時代がくだると、都からくだり、田舎武士に過ぎない夫の妻に収まる姫が出てきます。
伊豆で北条時政の妻となり、妖艶な笑みを見せていた『鎌倉殿の13人』の“りく”(牧の方)は、まさしくその典型例です。
都でつつましやかな女君として生きるよりも、地方で崇められ、女王のように生きる方がよい――そう考えた女と、彼女たちから都のやり方を学んでいく男たちが、歴史を変えてゆくのです。
そうした歴史のうねりの端緒に、平為賢はいるのです。
あわせて読みたい関連記事
-

双寿丸が『光る君へ』のラストに欠かせない理由 オリキャラが果たす重要な役割
続きを見る
-

「刀伊の入寇」いったい誰が何のため対馬や博多を襲撃したのか?日本側の被害は?
続きを見る
-

藤原隆家は当代一の戦闘貴族だった「天下のさがな者」と呼ばれ刀伊の入寇で大活躍
続きを見る
-

関東に拠点を築いた坂東八平氏~なぜ清盛に従ったり源氏についたりしていた?
続きを見る
-

モヤッとする位階と官位の仕組み 正一位とか従四位ってどんな意味?
続きを見る
-

喧嘩上等な貴公子もわんさかいた? 軟弱だけじゃない平安貴族の暴力事情とは
続きを見る
-

本当は怖い「平安京のリアル」疫病 干ばつ 洪水で死体が転がり孤児がウロつく
続きを見る
文:小檜山青
※著者の関連noteはこちらから!(→link)
【参考文献】
野口実『増補改訂 中世東国武士団の研究』(→amazon)
他