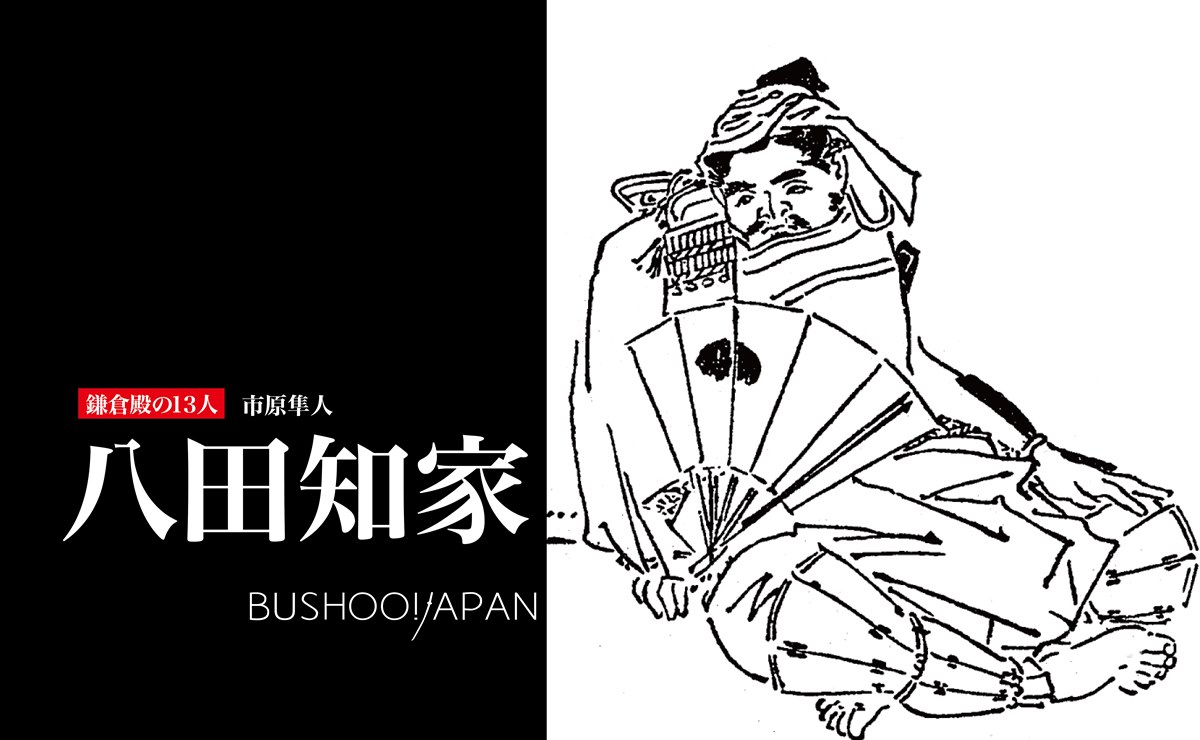大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の中盤から要所要所で存在感を発揮していた八田知家。
市原隼人さんが演じ、いかにもワイルドでありながら、実は老将の三善康信と同年代だったとも告白(康信は1140年生まれで知家は不明)。
源実朝から依頼された大船を建造した後、物語からは静かに去ることになりましたが、いったい史実ではどんな人物だったのか?
というと、これが少々判断に困る方で、13人のメンバーにも選ばれながら、いまいち掴みどころがありません。
建久元年(1190年)10月3日、頼朝の大切な上洛日に大遅刻というエピソードが目を引いたり、頼朝の弟・阿野全成を処刑した記録も残されたり……。
本記事で、八田知家の生涯を振り返ってみましょう。
藤原北家・道兼流の血を引く八田知家
八田知家は、藤原北家・道兼流の血を引く宇都宮氏の出身。
道兼とは、大河ドラマ『光る君へ』で主人公まひろの母を刺殺して、一躍悪名を轟かせたあの“ミチカネ(藤原道兼)”のことですね。
-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか
続きを見る
殺害したというのはあくまで劇中の話で、道兼流が横暴だから武士になったとかそういうことではありません。
そもそも東国との縁については、知家の祖父にあたる藤原宗円が下野守護になったことで始まりました。
常陸国新治郡八田(現・茨城県筑西市八田)を本拠としたため、八田氏を名乗るようになったとされています。
また、源義朝の落胤(十男)という説、頼朝の乳母・寒河尼の兄弟だという説などもありますが、知家の生没年がハッキリしてないためそうした説が存在するのかもしれません。
知家の前半生についてもほぼ謎です。
保元元年(1156年)【保元の乱】では源義朝側について戦っていた……とされています。
-

坂東のカリスマ・源義朝が鎌倉の礎を築く! 頼朝や義経の父 その実力とは?
続きを見る
-

保元の乱をスッキリ解説!平安時代の関ヶ原の戦いとして対立関係を把握すべし
続きを見る
これが事実だとすると、この時点で少なくとも元服していたことになりますね。
後の【平治の乱】に源頼朝が参加したのは13歳のときですから、仮に知家が同じくらいの年で保元の乱に参加していたとすると、1143年前後の生まれとなります。
-

伊豆に流された源頼朝が武士の棟梁として鎌倉幕府を成立できたのはなぜなのか
続きを見る
野木宮合戦
以降しばらくの間、八田知家は記録に登場しません。
特に治承四年(1180年)に頼朝が挙兵したときにはどうしていたのか。
『吾妻鏡』にも記載が無く、同年10月に頼朝が初めて所領安堵をした際にも、知家の名は出てきていません。
ただし、養和元年(1181年)4月に頼朝が寝所の警護役を選んだ際、知家の息子・友重が入っているため、この間に知家は頼朝の信頼に足る言動をしていたのでしょう。
合戦に参加したことが明確なのは、寿永二年(1183年)2月の【野木宮合戦】です。
この戦いは、頼朝叔父の志田義広が、知家ら北関東の武士たちと下野の野木宮(栃木県下都賀郡野木町)で衝突したもの。
叔父というと、一瞬、志田義広が頼朝サイドかと思ってしまいますが、実際は逆です。
八田知家や北関東武士(頼朝派)
vs
志田義広(反頼朝)
なぜこのような戦いが勃発したのか。
志田義広は若い頃は都にいたのですが、常陸に下って土地を開墾し勢力を築いた……という、なかなか独立心にあふれた人です。
保元・平治の乱には参加していたのかどうかよくわかっておらず、それでいて平家に逆らった様子もなく、史料上にあまり登場しないため、イメージしにくいところがあります。
『吾妻鏡』によると、志田義広は頼朝の挙兵後に一度面会していたようで……その後、積極的に関わろうとはしていなかったようです。
必要に迫られて開墾したのではなく、自ら東国に下って土地を開いたくらいですから、
「自分の勢力圏を侵されなければ、誰が上に立っていても構わない」
というような考えの持ち主だったのかもしれません。
政治的にうまくやれれば、鎌倉幕府ができてからも生き残る道もあったでしょう。
しかし、義広が鹿島神社の土地に手を付けてしまったことで頼朝の反発を買い、野木宮で頼朝方の武士たちと衝突することになったのです。
※頼朝が関与していなかった説もあり
この頃は「平家が東国へ兵を進めようとしている」という噂が立った時期であり、実際に美濃・尾張までが平家の勢力圏に入っていました。
頼朝は有力な御家人を西へ向かわせており、自分も直接動けなかった。
ゆえに北関東の武士たちが応戦したのです。
中心となったのは小山朝政という人で、吾妻鏡の記述も彼が中心になっています。
知家も彼らの側について戦っていたようですが、大きな戦功は上げていなかったようで、あまり行数は割かれていません。
京都に慣れた人
その後も、基本的には「何かに参加していたことはわかるが、具体的な活躍はあまり記載がない」という状態が続きます。
例えば、元暦元年(1184年)6月に行われた平頼盛「餞別の宴」で、濡れ縁に控えていたとされます。
吾妻鏡では「京都に慣れている人々」と記載されていますので、八田知家も保元の乱やそれ以前での経験を評価されたのかもしれません。
同年8月には、頼朝の弟・源範頼に従って、平家討伐のため西へ向かいました。
-

源範頼が殺害されるまでの哀しい経緯 “頼朝が討たれた”の誤報が最悪の結末へ
続きを見る
道中の言動は伝わっていないので、頼朝や源氏への反抗心はなかったと思われますが……頼朝を通さずに朝廷から右衛門尉の官職をもらっていたため、元暦二年(1185年)4月に書面でお叱りを受けていいます。
この叱責の手紙は非常に長く、知家以外にも多くの御家人が事細かに咎められています。
細かさでいえば、織田信長が足利義昭に出した”十七条の意見書”と張り合えるほど。
-

信長が義昭に本気でダメ出し「殿中御掟」「十七箇条意見書」には何が書かれている?
続きを見る
義昭の言動を咎めていた信長に対し、頼朝は相手によっては人相まで悪く言っているので、少々ヒステリックな気もしますが……。
「顔つきがその人の能力や運と関係している」という価値観の時代でもありますので、頼朝の記憶力を評価すべきでしょうか。
その中で、知家は兵衛尉を受けていた小山朝政と並んで叱りつけられています。
意訳しますと、
「西国を鎮めに行く途中に京都で官職を受けるなどということは、どんくさい馬が道草を食っているのと同じだ」
という感じです。
しかし、疑い深い割に怒りが持続しない……というのも頼朝の特徴。
このとき叱責された人物も、問題なく仕え続けています。
もちろん八田知家もその一人でした。
叱責から半年後の文治元年10月、勝長寿院の完成式典が行われ、このとき知家らも参加しています。
僧侶たちへのお布施として反物や衣類、馬など数種類の物品が収められており、知家は比企能員とともに馬を引いていました。
また、文治元年(1185年)には常陸守護に任命されたともされ、このとき常陸での本拠・小田城を造ったとされています。
文治二年(1186年)1月には、頼朝が従二位用の直衣を初めて着る儀式に参加。
他には、
・藤原秀衡から一旦鎌倉に届けられた京都への税を朝廷へ届けるよう命じられたり
・京都から下ってきた検非違使の宿所が知家の家に指定されたり
・さまざまな儀式の供の一人として登場したり
大きな活躍や重大な役目ではないものの、細かなところで頼朝に信頼されていたらしきことがうかがえます。
※続きは【次のページへ】をclick!