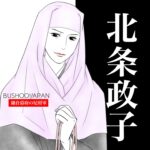こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【鎌倉殿の13人感想あらすじレビュー第4回】
をクリックお願いします。
一本の矢が放たれ 4年7ヶ月の源平合戦へ
いざ山木邸へ。
坂東武者たちは臨戦体制です。
宗時は義時に「怖いのか?」と聞いている。何かと熱血暴走気味とはいえ、宗時はよい兄です。弟としては、この兄が大好きだし、頼りにもなります。
宗時は弟を安心させるように、俺も怖いと言います。そして父上を見るように言います。堂々たるものだと。
「馬鹿野郎! 俺だって怖いよ」
「父上もですか」
しょんべんちびったと言い出し、笑わせる時政。ふざけているようで、大事な場面だと思います。彼にはムードを作る才能があるんですね。
そのころ頼朝は政子の膝に寝ていました。
二人は離れない。それに政子が何もしなくても、こうしているだけで頼朝の力になっています。
山木邸で配置についた一団。弓を引く音が入ります。SEも抜群に綺麗なこのドラマ。弓を引く音が実によい。
そして佐々木定綱が放った一本の矢が、4年7ヶ月に及ぶ源平合戦を始めるものとなるのでした。
「かかれー!」
喚声があがり、次回へ。
MVP:八重
八重は本当に駄目な女です。
後世つくられていった「婦徳」(女性が守る徳目)をことごとく破っている。
自分の恋心に流されて、実家を裏切っていること。
今の夫である江間次郎を利用していること。
この二点だけでも許されません。こういうことをする女がいると困るからこそ、婦徳という概念が作られました。
やはり婦徳を破っている政子や、りくと比較すると、無害なようでそうでもないようにも見えてしまう。
政子とりくは際立った賢さがあるけれども、八重はそうではない。持てる知性は全て頼朝への恋のために使われ、政治力や野心はありません。
と、ダメ出しをしていますが、だからこそ八重は魅力があります。
打算がまるでないひたむきな愛情。平凡で染まりやすい自分に愛を教えてくれた頼朝が自分にとって全てだから、そのために尽くそうとする。
矢のように向かっていく思いがあまりに美しい。
重たいし面倒だし洗練されていないけど、ここまで純粋ならもうどうでもいいじゃないか! そう思えてきます。
それもきっとテレビの中にいるからなのだろうとは思います。
自分が決めた妄想シナリオ以外は無視する頑固さには哀れみを感じますし、勝手だし、夫の江間次郎は気の毒だとも思える。
これほど欠点だらけなのに、それでも魅力がある。
すごい人物像ではないでしょうか。
総評
テレビで縄文土偶について説明する番組を見ていて、ふと思ってしまったことがあります。
縄文時代の人々と『鎌倉殿の13人』の人々。
現代人と『鎌倉殿の13人』の人々。
断然、前者(縄文と鎌倉)のほうが距離が近いのではないか?と考え、同時にこのドラマを作る難しさを想像してしまいます。
語彙力。知識の量。そういうものが戦国時代とは大幅に違い、注意せねばなりません。
『麒麟がくる』ではバンバンと漢籍を引用し、故事成語を使っていて素晴らしかったけれども、それが本作ではできない。
いったん難しい言葉を使って、それを落とすようなことを本作はしています。相当厳しいはずなのに、そこをうまく高度にこなしている。
三谷さんの脚本は笑えるな〜……と、おさめているけれども、笑えるだけではない仕組みや伏線があって毎週すごいと思うばかりなのです。
語彙力だけでもありません。
源平合戦って、わけがわからないんですよ。
戦国時代となると戦術戦略に納得できるものがあるけれども、源平時代はもう無茶苦茶。
その理由はわかってきました。
源平合戦の時点では、兵法はじめ様々な思想研究がまだまだ未熟すぎるのでしょう。もちろん、皆無ではないだろうし、本能的に察知できている人はいても、敵味方にコンセンサスが無ければめちゃくちゃになって当たり前です。
たとえば、義時のこのセリフです。
「坂東は平家に与する奴らの思うがまま。飢饉が来れば、多くの民が死にます。だから、我らは立つのです!」
一見いいことを言っているようで、ものすごいダメ出しをしたくなるセリフです。
隣国・宋の士大夫だったら? と、考えると、こうツッコミたくなるのです。
「あのさあ、飢饉が来そうな時こそ、戦なんてもってのほかでしょ! 兵糧確保できないで戦を始めてどうするの? 兵法の基本的なこととして、兵糧の確保が難しい時はそもそも戦争を始めない。そういう基礎知識が通じないんですか!」
「それよりもね、まず、飢饉になったら権力闘争より民を救いなさい! 仁政ってどういうことかあなた方理解できます?」
こういう脳内ツッコミをしてしまう。
もちろん後世からのツッコミであって、義時たちが悪いわけじゃない。彼らは、戦に勝利するだけではなく、国を統治することまで考えるようになります。
努力、鍛錬、学習を重ねてゆきます。
法を整備し、御恩は何かを武士に教え、道徳心を醸成してゆく。
そうすることで日本の歴史をより強く実りあるものへと変えてゆく。
そういう後半があるからこそ、序盤は無茶苦茶なのだと思います。
伏線として何本も矢を放たれたこのドラマ。義時たちの運命をきっちり見届けましょう。
あわせて読みたい関連記事
-

鎌倉幕府を支えた北条義時62年の生涯~殺伐とした武家社会を乗り切った手腕とは
続きを見る
-

頼朝と義時の鎌倉幕府を支えた北条政子69年の生涯~知られざる尼将軍の功績に注目
続きを見る
-

伊豆に流された源頼朝が武士の棟梁として鎌倉幕府を成立できたのはなぜなのか
続きを見る
-

なぜ北条時政は権力欲と牧の方に溺れてしまったのか 最期は政子や義時に見限られ
続きを見る
-

戦の天才だった源義経 31年の生涯~自ら破滅の道を突き進み奥州の地に果てる
続きを見る
【参考】
鎌倉殿の13人/公式サイト