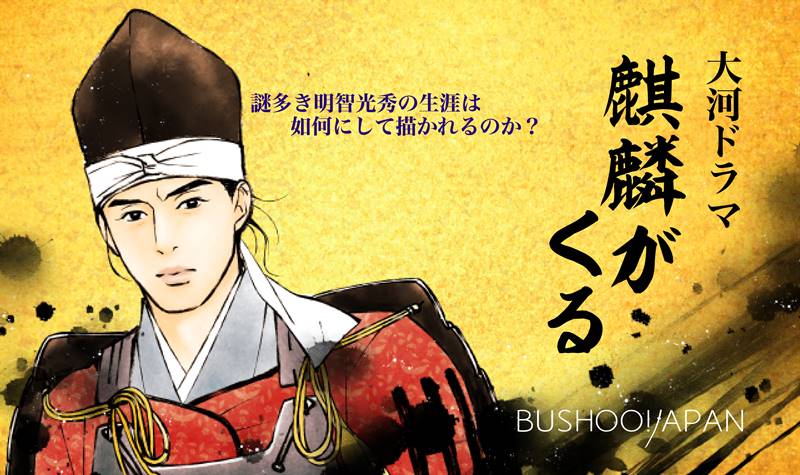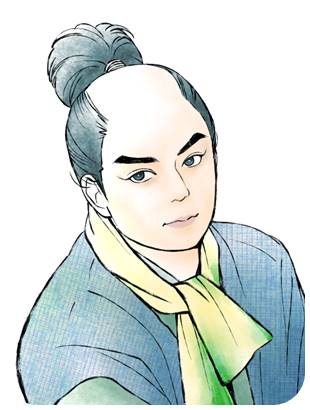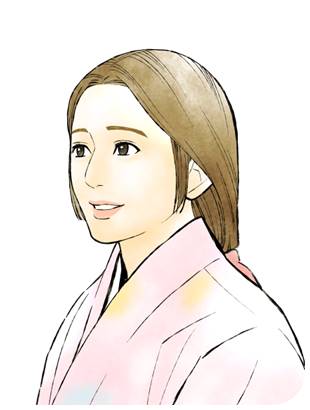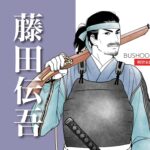こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【麒麟がくる第30回感想あらすじ】
をクリックお願いします。
御所の塀を直していた
信長は庭で鷹と向き合っています。
そして背中を向けたまま、朝倉相手に一人では勝てぬ、良い手はないか?と光秀に問いかけます。
信長さぁ……。そんなに悩んでいるのであれば、くるっと振り向いて笑顔になってもよいでしょうに。秀吉ならできるはずなんだよなぁ。そういう言動だから仲間ができないんですよ!
光秀はめげない性格であるがゆえに、話を始めます。
帰蝶といい、光秀といい、信長のぶっ飛んだ言動にめげないから貴重なのですね。
光秀はこちらへ参る日、京の御所の前を通りました。
崩れていた塀が、いつの間にか見事に修繕されている。聞けば信長が命じて、塀と南門を直したのだとか。
ここで信長は、思うところがあったのでしょうか。
父・織田信秀が御所の塀を直した。その塀が見る影もないと公家たちが嘆くのを聞き、父上の供養と思って直したのだそうです。
-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名
続きを見る
そうゆっくりと振り返りつつ、語るわけですが、信長の面倒臭さが出ちゃってる。
すねた信長は、心の琴線に触れる話題を持ち込まないと、これなんですよ。
信長を上司にできる勇気があるかどうか?
そういう問題提起も感じてしまいます。
叩けば門を開くかもしれませぬ――
光秀は昔読んだ書物のことを持ち出します。
8歳の子が、父に尊い仏は誰から道を聞いたのかと尋ねる。
一番尊い仏から。ではその一番尊い仏は誰から教わったのか?
父は答えられず、空から降ってきたと答えたのだと。
何かに迷うと、光秀はいつもその書物のことを思い出すのです。空から降ってきた者から道を聞いてみたいと――。
信長は、以前話した父の話と似ていると嬉しそうな顔をします。帰蝶には母、光秀には父を見出しているのでしょうか。
一番偉いのはお天道様。次は帝。将軍はその帝の門を守るもの。その将軍が帝の門を守る役目を放り出したから、世は乱れた。
その帝がこの戦をどう思うのかお聞きしたい!と、興味津々になります。
こういう好奇心が燃える信長は、本当に幼い子どものように見える。それをこなす染谷将太さんがよいのです。
無邪気な子どもらしさあっての、この信長です。
光秀は、帝が認めれば大名が納得すると言います。そうでできなければ、大名は納得しないのだと。
「賭けだな。帝は拝謁を許されると思うか?」
そう問われ、光秀はこう言います。南の御門を直した、叩けば門を開くかもしれませぬ――。
信長は納得しているようです。ここで誰か来客があり、あとの話は酒の席で話すことになったのでした。
そしてこうだ。
「まずは裏門へ行け。そなたの妻子が来ておるぞ」
光秀は驚きます。
この場面も、みどころぎっしりではある。帝の権威で大名を納得させるということは、幕末でもありました。
当時の幕閣が、開国をめぐり揉めに揉めていた折、帝の決裁を仰ぐことにしたのです。
これがとんでもない痛恨事となり、幕末の政局は無茶苦茶になってゆくのですが……帝という賭けは、そう簡単に使ってよいものではないのです。
-

幕府と朝廷の板挟みで苦しんだ堀田正睦~優秀な開明派 55年の生涯を振り返る
続きを見る
そしてもうひとつ、信長がよりにもよって最後に光秀妻子のことを出すあたり、藤吉郎のねね弁当と比べたくなります。
藤吉郎は話の枕として、愛妻弁当を持ち出している。
こういう【情】に訴えることをされると、人間は心の壁が崩れて、相手の要求に屈してしまいやすくなるものです。お試しキャンペーン、営業のトーク、奢り飯には注意が必要ですな。
信長はそれを使わず、最後に持ってくる。“人たらし”こと営業部の秀吉さんとは真逆です。
いきなり本音トークをする。
大抵の人は、秀吉タイプに参ると思う。けれども、信長と光秀はタイプが異なる。ゆえに一致するところがあるのでしょう。
危険に巻き込んでもよいものか
光秀はいそいそと裏門へ向かいます。
そこには煕子、お岸、たまがおりました。
光秀は娘たちの名前を呼び、感極まった様子で我が子の成長を喜んでおります。
煕子の背後には伝吾もいました。
このあと、大人たちが話す隣で独楽を回す子供たち。光秀は明日早朝へは京へ戻ると告げます。
また戦、だが案ずるなというヤリトリのあと、煕子が意を決したように言います。
お岸やたまの願いでもござますし、私の願いでもある。
そう前おきして言います。
「私どもを京へお呼びいただけませぬか。お岸が申しました。お父上のご苦労をしのぶのではなく、目の当たりにしたいと。戦へおいでになるのなら、お見送りしたいと。それが美濃ではかなわぬと。私も十兵衛様のご出陣をお見送りしとうございます」
光秀は考え、迷う顔になります。
妻子を愛すればこそ、危険に巻き込みたくない。とはいえ無下にもできない。
そんな感情を長谷川博己さんが表情で見せるのです。
「京へ……騒がしき都へ……伝吾を守りにつければ、来られるか。来るか京へ!」
「はい!」
かくして妻子が再会できることとなりました。
これも伝吾あってこそ。伝吾、ここでほぼ見守るだけなのに、存在感があります。煕子の意思の強さもお見事でした。
-

藤田伝吾の生涯|光秀に託された筒井順慶との交渉が明智の命運を握っていた
続きを見る
囲碁をうつ東庵と……
このあと、碁盤が映し出されます。
誰かがこう言います。
「織田信長が上洛の折、参内したいと申しておる。会うべきか、どうであろうか?」
囲碁の相手は、なんと東庵でした。
先生は囲碁がお上手なのでしょう。松平元康にも連戦連勝していましたっけ。
「お会いになってみればよろしいかと」
「どのような武将であろうか?」
ここで東庵がまた只者でもないことを言い出す。
越後の上杉輝虎は、上洛して天下に平安と静謐をもたらして見せると胸を張りながら、今日まで音沙汰なし。信長は曲がりなりにもそれを果たした。
「う〜ん、うん、見るべきところはあるかと……」
囲碁を打つ誰かの口元だけが見える……何がすごいって、この口の動きだけで、何かすごいものが伝わってくるあたりでしょう。
昔、この帝を演じる坂東玉三郎丈の舞踏公演を見たことがあります。
チケットを買ったわけではなく、学校の芸術鑑賞教室。歌舞伎? よく知らねえし。親や先生は名前を聞いてびっくりしていたけど、眠くなるかもね。
そう舐め腐ったことを思いつつ、見始めたわけですが。
あれは一体何だったのか?
ありきたりで陳腐な表現で申し訳ないのですが、鶴か白鷺か何かが人間に化けて舞い降りたような……細かいことは覚えていない。されど、人間ではない何かが目の前で動いていたことは思い出せる。
そういうトンデモナイものを見て、目を離せなくなった記憶があります。思い出すと今でも不思議な気持ちになります。
そういう不思議な何かを見た気持ちが、受信料で蘇るのだから、払った甲斐があるなぁ。
居るだけで尊く、存在そのものがとらえかねる光のような……帝だ……そこに帝がいました。
-

過酷な戦国時代を生き抜いた正親町天皇~信長や秀吉とはどんな関係を築いた?
続きを見る
※続きは【次のページへ】をclick!