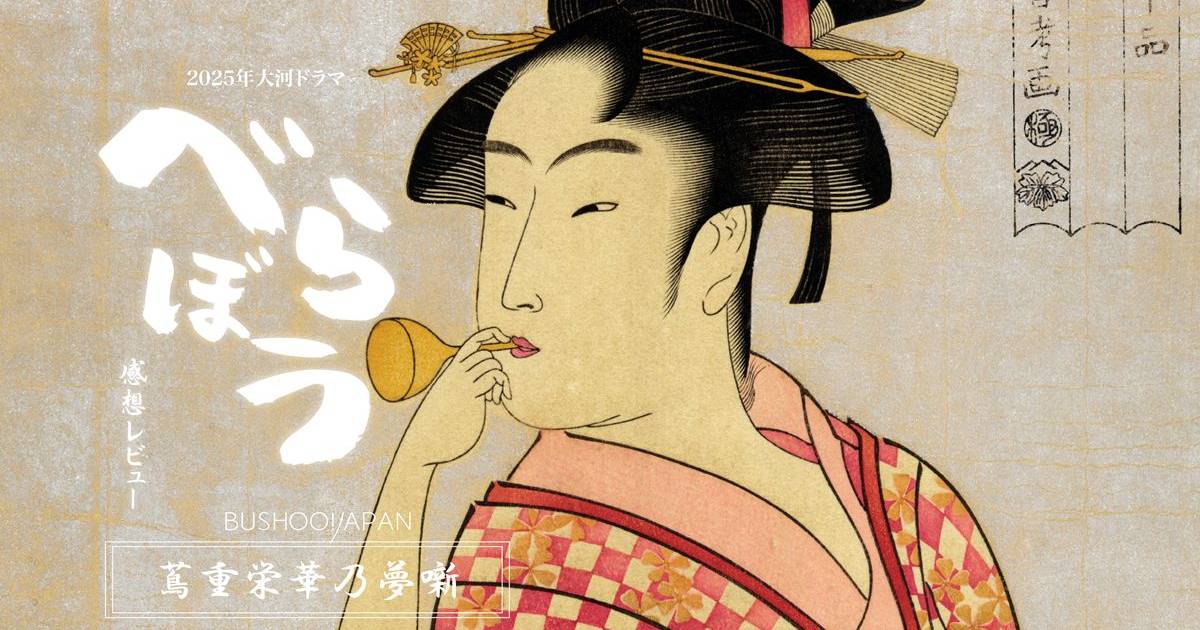本多忠籌は松平定信に言い聞かせます。
「人は正しく生きたいのではないのでございます。楽しく生きたいのでございます」
松平信明も続きます。
「倹約令を取りやめ、風紀の取り締まりを緩めていただけませぬか?」
それに対し、果たして定信は?
松平定信の独裁強化
「世が乱れ、悪党がはびこるのは、武士の“義気“が衰えているからだ。武士が”義気“に満ち満ちれば、民はそれに倣い、正しい行いをしようとする。”欲“に流されず”分“をまっとうしようとするはずである! 率先垂範! これよりはますます倹約につとめ、”義気“を高めるべく、文武に励むべし!」
こう叫ぶ定信の前で、長谷川平蔵の顔が萎れてゆきます。
改革を緩めようとせず、黒ごまむすびの会以来の「信友」らを遠ざけ、イエスマンばかりを重用する定信。
さらなる独裁へと突き進んでしまう。
本作ではあまり触れられませんが、定信は風紀取り締まりだけに奔走していたわけでもありません。
外交政策もターニングポイントに直面しており、常に過労状態でした。
外交については再来年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』の時代にまで影響は及びます。
私は『べらぼう』を全面肯定するわけでもなく、もうちょっと言及して欲しい要素はあります。
その一つが仙台藩です。
伊達重村も一橋治済と親しい外様大名であるとか。その重村と親しい高岳とか。工藤平助と、その娘である只野真葛が江戸期を代表するフェミニストであるとか。

伊達重村/wikipediaより引用
仙台藩は大変面白いですし、江戸後期の対外情報網を踏まえる上でも重要な存在でした。
むろん、仕方ないとは思います。そこまでやるとキリがない。
治済と親しい外様大名枠として松前道廣や島津重豪を優先するならばそこは致し方なし。
やればできるけれども、ドラマ制約上やらない点についてはどうこう言わんでもいい。せいぜいがここで補足すればよいかもしれません。
私が許せないのは「やればできる、大河チームならやってやれんわけがない!」要素をやらない時ですね。そこは切り分けて欲しいものです。
この場面で気になったのは”義気“ということ。
前回おていさんが「義を見てせざるは勇無きなり」と言ったことを思い出させますぜ。柴野栗山から問答を聞いたかどうかはわかりませんが。
そして本多忠籌と松平信明が、一橋治済の前にいます。
治済の手には、葵小僧が持っていたものと同じ葵の御紋入り提灯。
どうやらこの男は、定信の迷走を面白がっているようですね。
蔦重も京伝も、処罰がじわじわ効いてきている
一方、蔦屋重三郎は、真面目な口上付きの本を出しているんだとか。
京伝先生に頭を下げてやっと筆をとってもらったそうですぜ。
なんでも身上半減の宣伝効果で売上が伸びたのも一瞬のみ。じわじわボディブローのように経営に響き、煙草も倹約させられていると、蔦重が鶴屋喜右衛門相手にぼやいています。
倹約をしているとふんどしの苦労がわかっちまうってよ。
蔦重が、田沼意次時代から幕府の金蔵(財政)再建に取り組んでいると語るところは重要でしょう。
定信にしても「倹約だ」と触れ回る一方で、実は田沼政策を継承している要素は多いのです。

松平定信/wikipediaより引用
すると鶴喜が、ふんどしの深慮遠謀を解き明かします。
蔦重の店を潰したら倹約しようがない。半減ならば潰すには惜しいから、倹約に励むことになる。そうやってふんどしの苦労がわかるってことでさ。
江戸一の本屋が倹約してくれるなら効果も絶大。率先垂範ですわな。
蔦重は「しゃらくせえ!」と言うものの、鶴喜は稼ぐ手立てがあるのか?と聞いてきます。
「再印本」を出すと答える蔦重。
売り物がなくなったときに蔵出しをしたら結構売れたようで、古い板木から黄表紙を刷り直して再販することにしたようです。
名作黄表紙揃いものにもなるって寸法でさ。
鶴喜はそのアイデアに感心し「うちもやってみようかな」とまで言い出す。蔦重は勘弁してくれと止めております。
鶴喜が冗談だと答えながら、昔のでよければ京伝本の古い板木も譲ってくれるそうですぜ。
ただ、交換条件はある。
京伝の新作を鶴屋が取ることが条件だそうです。
その山東京伝は障子張りをしながら「真人間になる」と蔦重と鶴喜に宣言しています。
手鎖で手首を痛めて筆も持てないと語っていますが、それが大袈裟なことは、障子張りをしてたらバレますわな。
「心学」みたいなものでもよい。そう譲歩する蔦重に対し、それでも京伝は渋っています。
すると鶴喜は、お抱え料金三十両の返金を迫ってきました。
これが近代的な契約ってやつよ。京伝は困惑しだし、鶴喜は念押しします。
補足しておきますと、京伝がフラフラできるのは、しっかり者の弟である京山がいるということもあります。経営センスは弟の方があったのでしょう。
ここで妻の菊が、唄うように「この方どうです?」と言いつつ、雲を踏むように茶を運んで歩いてきます。
江戸の家がまるで宮殿のように思えるほど美しいのが、京伝の愛妻である菊でやんす。
滝沢瑣吉を耕書堂に置いていく山東京伝
するとその背後から、何か陰湿そうな男が来ました。
乱世の世界観ならば、こいつの謀略のせいで何人も破滅させられる。そういう面構えですね。
「俺の代わりに、この人書けます! 書けますよ、へへっ」
京伝はそう言いながら、謎の男を紹介してきます。一体なんなんだ、こいつは。戸惑っている蔦重と鶴喜に、京伝は「門人のようなもの」とゴニョゴニョ言い出しました。
「門人ではない! 友人だ!」
ド迫力のイケボでそう返す男の名は滝沢瑣吉(たきざわ さきち)。後の曲亭馬琴ですね。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵
ここではわかりやすさを踏まえ、劇中の人物としては「滝沢」と呼びましょう。
なんでも彼は入門しようとやってきたのに、京伝は「門人ではなく友人で頼む」と言ったそうです。で、滝沢は深川の大水で家をやられて友人宅に厄介になっていると笑い飛ばす。
京伝と菊は早く出ていって欲しいんでしょうね。
なにせ、こいつは後に、京伝夫妻のあることないことを記した暴露本を執筆する。そんな暴露系の元祖は夫婦生活にとって最悪の存在でしょう。さっさと塩でも撒きてえんじゃねえかな。
しかもこいつ、こうですからね。
「困っておるなら書いてやってもいいぞ、本屋ども! ガハハハハハ!」
なんなんでしょう。横山光輝漫画でしか見たことのないような笑い方をしていますね。
「よかったじゃないですか蔦屋さん、作者が見つかって」
鶴喜はそう言いながら立ち上がり、伯母に会う約束があるからと尻に帆を掛けサッサと出て行きました。
これはどうなんでえ。確かに滝沢はのちに売れっ子となりますが、同時に版元を泣かせることになります。
完璧主義者で修正がやたらと多いので、何度も何度もそれをやらせるんですね。鶴喜はそうした危険性を察知したのでしょう。
京伝の家に潜り込むまで滝沢瑣吉は何をしていたのか?その補足をしておきますと……。
滝沢は若くして家を出奔すると、医者やら狂歌師やら目指して職業を転々としました。
そして戯作者になろうと一念発起し、酒一樽を持って京伝の家に押しかけた。京伝は「絵師と違って戯作者はそもそも門人制度がない」と断り、酒食を共にすると帰ってもらいました。はなから面倒くせえ奴ですね。
ただし京伝は何かを感じたのか。それとも戯作者を休みたかったのか。
弟の京山に「あいつは見どころがある。また来たら居留守を使わず、二階にあげなよ」と言い含めたのだとか。
この時の経緯が後々まで祟りまして。
滝沢が何かあるたびに京山は「兄貴に弟子入り頼んできておいてお前はなんだ!」と怒り、「門人じゃねえ!」と返される。京伝は相手をかわすものの京山は正面からぶつかりまして、いい歳こいても延々と争うことになるのです。
なんせ京山の本に挿絵をつけた歌川国芳に対してまで「アイツの駄作にかわいい猫の挿絵つけて、売り上げに貢献してんじゃねえぞ!」と言いたげなノリで馬琴はケチをつけますからね。
『北越雪譜』の作者である鈴木牧之は、よりにもよってこの二人に「江戸で出版できないか?」と頼んでしまったため、揉めに揉めて恐ろしいことになっています。
教科書ではさらりと流され、名前が並んでいるだけの江戸文人。
実はドロドロとしたバトルを繰り広げていたんですね。
平安時代の上流文人同士のほうが、精神的に成熟しているぶんマシに思えます。『光る君へ』よりも『べらぼう』の方がややこしい世界だってのは正しい歴史認識ですぜ。
そしてこれが重要なのですが、彼はあくまで戯作者としての名乗りが「曲亭馬琴」になります。
世間によく知られている「滝沢馬琴」というのは、武家の姓と戯作者の名乗りを組み合わせたもの。本人も使ったことはあるものの不自然なのに、それがどういうわけか明治後期から定着してしまった。
本人からすると武家を継ぐ重圧と戯作者としての名乗りが混ざっているため罪悪感を刺激され、他人に使われると不快な名乗りになる。
というわけで我々は「曲亭馬琴」と表記するのが正解ですね。
ちなみに、本人たちが嫌がっていたにも関わらず定着したものとして、「滝沢馬琴」以外の有名なものが「新選組の浅葱色羽織」だと思います。
センスが悪いし目立ってしまう。ということで早々と廃止になったのに、現代のフィクションではもはやシンボル。彼らが見たら「あのダサい制服が定番だなんてそんな……」と涙ぐみそうな話でやんす。
※続きは【次のページへ】をclick!