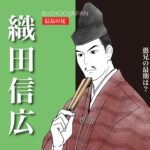武田信玄の戦略よりも、足利義昭の包囲網よりも、織田信長を苦しめたとされる一向一揆。
特に尾張&美濃という本拠地にほど近い伊勢長島の一揆勢たちは、織田家全体にも関わる懸念事項でありました。
なんせ元亀元年(1570年)に攻撃を仕掛けられてから、解決する天正二年(1574年)まで、実に4年も織田家の膝元で悩まされてきたのです。
その全体像については以下の記事にお譲りするとして、
-

長島一向一揆|三度に渡って信長と激突 なぜ宗徒2万人は殲滅されたのか
続きを見る
今回は、最終決戦となった戦い。
『信長公記』巻七の最終節を見ていきましょう。
長島・屋長島・中江の一揆勢を兵糧攻め
天正二年(1574年)7月13日から信長は長島攻略を始め、一揆勢を追い込みました。
途中で逃げ出した者や移動した者などもいましたが、信徒の多くは長島・屋長島・中江にあった城へ籠城。
しかし、大所帯であればあるほど厳しくなるのが籠城戦です。言わずもがな、食料や水、衛生関連などの諸問題が発生するからです。
当然、信長はそれを知っています。
一揆勢が三つの城に逃げ込んだのを見計らうように織田軍が兵糧攻めを開始すると、一ヶ月半ほどで、多くの一揆勢が餓死し始めました。
おそらく城内は悲惨なことになっていたでしょう。幸か不幸か『信長公記』にその描写ははありません。
一揆の最終日となった、9月29日の記述に留められています。それは次のような内容でした。
激高した一揆勢により信長の親族も多数討死
9月29日、飢えに耐えきれなくなった一揆勢が降参して、長島から退去することにします。
周囲は川に囲まれた中州ですので、多数の舟で渡る一揆勢。すかさず織田軍は鉄砲で狙撃したり、直接斬り伏せたりして、逃げ出した信徒たちを次々に始末していきました。
これに対し、激高した一揆勢のうち7~800人が舟から飛び降り、裸に刀だけを持ち、文字通り死にものぐるいで防備の手薄だった織田軍部隊へ決死の切込みを仕掛けます。
このときの白兵戦は凄まじいもので、織田軍の被害も甚大。信長の親族も複数人が討ち死にしてしまいました。
ポイント
・織田信広(庶兄)
・織田信次(叔父)
・織田秀成(弟)
・織田信成(従兄弟)
・佐治信方(信長妹・お犬の方の夫)
かつて長島一向一揆との対立が本格化した頃にも信長の弟・織田信興が敗死しており、信長は、計六人もの身内を長島相手に失っているのです。
注目は、織田信広でしょうか。
かつて今川軍の太原雪斎に敗れて捕縛され(1549年)、竹千代(徳川家康)と人質交換をしたことがある信長の庶兄(側室の子)です。
-

織田信広の生涯|なぜ謀反を画策した信長の庶兄は織田家で重用されたのか
続きを見る
人質交換で尾張に戻ってきた信広は、その後、斎藤義龍と組んで信長に敵対することもありました。
が、それに赦されると外交などで重要な役を担ったり、あるいは信広の娘が丹羽長秀(信長の腹心)に嫁いで嫡男・丹羽長重を産むなど、織田家の中でもかなり重要な存在になっていきます。
-

兄の裏切り、瞬時に見抜いて|信長公記第26話
続きを見る
-

美濃の戦国大名・斎藤義龍の生涯~父は蝮の道三 信長の攻撃を退け続けたその実力
続きを見る
少年時代の苦境を乗り越え、やっとまとめ上げてきた肉親たちをこれほど一度に失えば、信長でなくても激高することでしょう。
さらには家臣の中にも、ここで討死した者は少なくありませんでした。
重臣の親類たちも戦死した
討ち取られた家臣は主に次のようなラインナップです。
犠牲になった家臣たち
・佐々松千代丸(佐々成政の長男)
・和田貞利(和田惟政の弟)
・平手久秀(信長の傅役だった平手政秀の長男)
・山田勝盛(馬廻衆)
この時点での死=名前が残りにくい、ということで馴染みの薄い武将ばかりですよね。しかし……。
しかし( )内の注釈をご覧の通り、いずれも織田家重臣の近親者や、親衛隊(馬廻衆)であり、信長にとってはかけがえのない人物ばかりとも言えます。
最初に攻撃を仕掛けられてから数年にわたって邪魔をされ続け、最後の最後でも甚大な被害を受けた怒りは、余人には推し量ることもできないでしょう。
信徒を逃せば再び敵となって立ちはだかる
こうした壮絶な戦いがありながら、中江・屋長島にはまだ2万人ほどの一揆衆が立てこもっていました。
織田軍も柵を巡らせて包囲。この日(9/29)に焼き討ちし、ほぼ全員を焼き殺した――とだけ書かれています。しかし……。
この焼き討ちだけが取り沙汰され「信長はこの上なく残虐だ」と受け取る方も多いのですが、それ以前に深い因縁があったことを考えれば単に残虐と断じることも難しいのではないでしょうか。
逃げ出した信徒の中には、石山本願寺へ駆け込んだ者もおりました。つまり、中江・屋長島の一揆勢のうち、リーダー格だけの首を取っても、生き残った者たちが再び戦う可能性は決して低くありません。
中江・屋長島の者を助ければ、石山本願寺の兵力が増す可能性が高くなるのです。
見せしめのため焼き討ちを徹底したのでは?
この先は私見ですが……。
おそらく信長が「長島一揆勢を焼き殺す」という判断をしたのは、比叡山焼き討ちの際の人的被害が、現在、語られているほど多くなかったからではないでしょうか。
-

信長の比叡山焼き討ち事件|数千人もの老若男女を“虐殺大炎上”は盛り過ぎ?
続きを見る
既に触れている通り、比叡山焼き討ちの直後こそ、世間は信長を恐れたものの、さほど間を置かずに一向宗徒が浅井方についたり、それこそ長島一揆勢によって織田家臣の複数名が討死しています。
「都の鎮守」として重要なイメージを持っていた比叡山という「箱」を焼いただけでは、イメージ戦略には足りない。ならば非道と謗られようと、人的被害を増やすしかない……という結論に至ったような気がしてなりません。
なんせ信長は、これまでの戦いでも、温情をかけた相手に再び裏切られたりして、手こずらされてきたのです。
今後の戦を有利にする、あるいは相手が怯えて自ら臣従を選んでくれれば、信長は真の天下人に近づきやすくなります。
既にこの時点で、信長は40歳。「人間五十年」の終盤にあたり、焦る気持ちもあったでしょう。
こうして信長は29日のうちに岐阜へ帰還し、長島一向一揆との戦いと、『信長公記』巻七はここで終わります。
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

長島一向一揆|三度に渡って信長と激突 なぜ宗徒2万人は殲滅されたのか
続きを見る
【参考】
国史大辞典
『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)
『信長研究の最前線 (歴史新書y 49)』(→amazon)
『織田信長合戦全録―桶狭間から本能寺まで (中公新書)』(→amazon)
『信長と消えた家臣たち』(→amazon)
『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)
『戦国武将合戦事典』(→amazon)