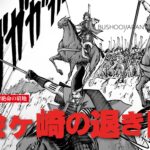こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【浅井長政】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
織田家を選んだ長政に信長も大喜び
近江は琵琶湖を抱えているものの、地勢的には内陸国に近い状態ですから、四方八方を敵に回すわけには行きません。
六角氏を攻略するため、そして斎藤氏の侵攻を防ぐため織田氏と同盟を結ぶこと自体は問題ありません。
しかし、それによって付き合いの長い朝倉氏の意向を無視するようなことになれば、結果として敵を増やしかねない状況です。
最終的に、長政は信長と手を組む道を選びます。
明確な時期は不明ながら、信長の妹・お市を正室に迎えることによって、この同盟は堅固なものとなりました。
-

信長の妹・お市の方の生涯~浅井に嫁ぎ勝家と共に自害した波乱の一生を振り返る
続きを見る
信長は同盟成立を大いに喜び、婿側が負担するはずの婚姻費用を全て出したといわれています。
無茶振りを飲んでくれた礼だったのでしょうかね。
また、”長政”の”長”の字は、信長から取ったものだという説もあります。花押も、この時期から”長”の字を崩したものに変えていました。
-

尾張の戦国大名・織田信長49年の生涯~数多の難敵と対峙し天下人になるまでの道
続きを見る
これによって義兄弟となった長政と信長。
しばらくは協力し合います。
例えば永禄十一年(1568年)、足利義昭が朝倉氏から織田氏の下へ移る際、長政は本拠・小谷城で義昭をもてなしていました。
さらにその2ヶ月ほど後、信長が義昭を奉じて上洛する際も、途中から長政が参戦しています。
-

なぜ足利義昭は信長と共に上洛しながら一人京を追い出されたのか 流浪の生涯を辿る
続きを見る
-

信長は京都までどんな敵と戦ったのか? 義昭を将軍就任させるための上洛戦
続きを見る
しかしこの蜜月も程なくして終了します。
元亀元年(1570年)のことでした。
織田家か朝倉家か?狭間で苦悩する浅井長政
元亀元年(1570年)初め。
信長は諸大名に向けて書状を出しました。
「皇居修理や将軍の御用を片付けるため、自分は2月に上洛する。各々方も上洛し、協力するように」
一見すると殊勝にも取れる文章ですが、上から目線と取る者も多かったようです。
上洛のときでさえ、京都の人々は「信長って誰?将軍様のお付きの人?」程度の認識だったそうですから、各地の大名からすれば「田舎者」「下賤な血筋の成り上がり者」と思っていたでしょう。
そんな相手から命令じみた書状が届けば、良い気分になるわけがない。
信長も、それは見越しています。
同書状では「天下のため」という名目で相手が従うかどうかを見極め、場合によっては武力行使をするためのものだったと思われます。大義名分もあるでしょう。
実際この年4月、書状に従わなかった朝倉氏へ攻め込んだのです。
困ったのが長政。
いや、困ったレベルとかそんなもんじゃなかったでしょう。
織田氏も朝倉氏も同盟相手ではありますが、より付き合いが深く長いのは後者であります。
しかも上記の書状が将軍の名で出されているならともかく、ついこの前まで無名に等しかった信長から出されていては、体面と血筋を重んじる朝倉義景が信長の命令に従わないのは理屈としては間違っていません。
-

なぜ朝倉義景は二度も信長を包囲しながら逆に滅ぼされたのか?41年の生涯まとめ
続きを見る
常識的に考えれば朝倉氏の方が正しく、周囲の国衆たちも朝倉派でした。
しかし、”将軍”という強力なカードを持ち、勢い盛んな信長に逆らうのは得策ではありません。
妻・お市も信長の妹。
体面とか血筋とかノンキなことを言っている朝倉より、はるかに将来性もある――というのは歴史を知る我々のバイアスもかかった考え方ですね。
ともかく長政は……。
突然の裏切りに信長は呆然
長政が選んだのは朝倉氏でした。
浅井長政は、朝倉氏との同盟を選び、織田家を見限ることを決定。
スグさま信長を討つべく出兵し、越前へ侵攻していた織田・徳川連合軍の背後を突こうとします。
主導したのは長政ではなく、父の久政だとも言われています。
-

信長が浅井長政に裏切られた理由がスッキリわかる~近江の複雑な国家運営に注目
続きを見る
一方の織田信長は、当初「浅井挙兵(裏切り)」の報を信じなかったとか。
なにせ信長にとって朝倉討伐は理にかなったものでした。
浅井長政についても、同盟を組んでから一貫して信長に協力しており、裏切られる心配は微塵もなかったのでしょう。
さらに信長は、越前出陣に際して参内し、天皇や皇太子に挨拶をしていました。
おそらく長政も義景も、そこまでは知らなかったでしょうが、信長は”朝廷”と”幕府”という、日本における最高権力者たちを味方につけていたともいえます。
この点に関して言うと
信長は”旧来の権威を重んじ利用する傾向があった”
のに対し、
長政は”世間的な権威よりも、実際に長く付き合っている相手を重くみた”
という違いかと思われます。
長政のほうが、戦国武将らしいといえばらしいですね。
そして熾烈な【浅井朝倉vs織田】が始まった
さて、浅井氏の裏切りによって窮地に追い込まれた信長。
【金ヶ崎の退き口】と呼ばれる壮絶な撤退戦を、豊臣秀吉や明智光秀らに任せ、見事、浅井や朝倉の追撃を振り切ります。
-

信長が絶体絶命の窮地に陥った「金ヶ崎の退き口」無事に帰還できたのはなぜ?
続きを見る
そしていったん帰国すると、すぐさま浅井朝倉に対して軍を起こし、ここから長きに渡る
【浅井朝倉vs織田】
という戦いが始まります。
織田家との全面戦争。
その第一ラウンドは元亀六年(1570年)6月【姉川の戦い】でした。
実際に戦った構図としてはこんな感じですね。
【浅井vs織田】
【朝倉vs徳川】
浅井軍は、先鋒・磯野員昌が織田軍の13段構えを11段まで突破し、あと一歩で信長の首――という健闘を見せています。
しかし、徳川軍が朝倉軍を押し切って撤退させ、織田軍に合流しようとしたため、浅井軍も小谷城へ引きました。
織田軍は浅井軍を追撃しましたが、小谷城を一気に攻略することは難しいため、手前の横山城を落とすにとどめています。
-

織田と浅井が激突した姉川の戦い 勝敗は? 信長も長政も互いに絶対引けない理由
続きを見る
横山城には木下秀吉(後の豊臣秀吉)が城番として入り、小谷城を監視することになりました。
浅井氏と秀吉の関係も、このときから始まったといえるかもしれません。
※続きは【次のページへ】をclick!