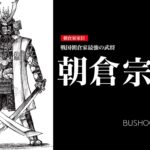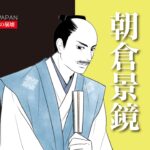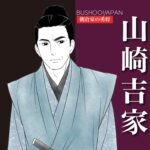こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【相模朝倉氏】
をクリックお願いします。
その後の相模朝倉氏
以降、相模朝倉氏は、後北条氏の家臣として存続し、大永四年(1524年)1月、北条氏綱による江戸城攻めにも参加。
享禄四年(1531年)頃からは、若き玉縄城主・北条為昌の補佐役が相模朝倉氏と血縁のある福島綱成になりました。
これを受けて、相模朝倉氏は綱成や玉縄衆と行動をともにする機会が増えたようで。
例えば
・天文七年(1538年)第一次国府台合戦
・天文十五年(1546年)河越夜戦
などにも参加していたと思われます。
豊臣秀吉による天正十八年(1590年)の【小田原征伐】では、

豊臣秀吉/wikipediaより引用
相模朝倉氏を含めた玉縄衆が小田原城の支城・山中城の守備に送られました。
しかし羽柴秀次・徳川家康などの大軍が攻め寄せたこと、元々、修繕が間に合っていなかったことなどもあって、あえなく落城。
当時の玉縄城主・北条氏勝はいったん玉縄まで戻ったものの、本多忠勝の家臣の縁者だった僧侶に説得され、秀吉軍へ降伏しました。
相模朝倉氏の当主だった朝倉景隆は、この措置に納得できず、浪人した後に出家したようです。
越前朝倉氏の当主・義景とは違い、骨のある人ですよね。
しばらく流浪した朝倉景隆を拾ったのが、結城家に養子入りしたばかりの家康次男・結城秀康でした。
どうやら朝倉景隆が出家した後「犬也」と名乗っていたのが、秀康は気に入ったとか。
景隆が、単に卑下してつけたのだと思いますが、三河武士の忠義を「犬のような」と表現するくらいですから、徳川家出身の秀康にとっては
「忠義者の証ではないか、結構結構」
と思えたのかもしれません。

結城秀康/wikipediaより引用
秀康は家臣たちの前で景隆(当時70代)に馬術を披露させたこともあり、なかなか良い待遇をしてくれていたようです。
この他に相模朝倉氏の本筋とされる朝倉政元が、別ルートで家を存続させています。
後北条氏滅亡の後、政元は豊臣秀次に仕え、秀次事件の後一時的に蟄居。
しばらく後に徳川家康に召し出され、家康の子・徳川頼宣、次いで徳川頼房に仕えたといいます。
政元の息子の代で男系は絶えてしまいますが、女系が結城秀康に仕え、こちらも代々越前で存続したようです。
また、玄景以外にも駿河へ向かった朝倉氏がいました。
貞景の次男・景高が孝景と不和となり、永正年間(1504~1521年)の間に今川氏親のもとへ走り、定着したとされます。
現在の静岡市葵区柿島城山にある「朝倉氏屋敷跡」はこの二人の屋敷だったと伝えられており、地名を取ってこの一族を”柿島朝倉氏”と読んでいるのだとか。
この一族は時代の趨勢に合わせて武田氏や徳川氏に仕え、江戸時代には徳川忠長(三代将軍・徳川家光の弟で後に処断される)の附家老と掛川城主を任されています。

徳川忠長/wikipediaより引用
なぜか大人気な駿河
まとめると
・駿河に行き着いた複数の越前朝倉氏の血縁者がいた
・彼らの血縁関係は不明
・宗家である越前朝倉氏よりも血筋を繋げた一族が多い
ということになるでしょうか。
これは想像でしかありませんが、雪に閉ざされる地域にいた朝倉一族にとって、温暖な東海道エリアは気候的にも魅力が強かったのかもしれません。
江戸時代には越前に戻った一族もいるんですけどね。
他にも各地に朝倉を名乗る家や地名があり、越前・相模朝倉氏との関係や起源が気になるところです。
北条早雲も長い間、大河ドラマ化の運動が行われていますので、もし実現したら相模朝倉氏にもスポットライトが当たるかもしれませんね。
あわせて読みたい関連記事
-

北条早雲の生涯|幕府の奉公衆・伊勢宗瑞が戦乱激しい関東へ進出を果たす
続きを見る
-

戦国越前の最強武将・朝倉宗滴が存在感ありすぎて後の義景滅亡に繋がった?
続きを見る
-

朝倉義景の生涯|信長を二度も包囲しながら逆に追い詰められた
続きを見る
-

越前の戦国武将・朝倉景鏡が朝倉氏滅亡の戦犯か? 義景を裏切り信長の傘下へ
続きを見る
-

朝倉家の戦国武将・山崎吉家の生涯~信玄との交渉も務めた勇将は最期に敵陣へ突撃
続きを見る
【参考】
志村平治『相模朝倉一族―戦国北条氏を支えた越前浅倉氏の支流 (戎光祥郷土史叢書 02)』(→amazon)
小和田哲男『地域別 × 武将だからおもしろい 戦国史 (だからわかるシリーズ)』(→amazon)
国史大辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)
世界大百科事典