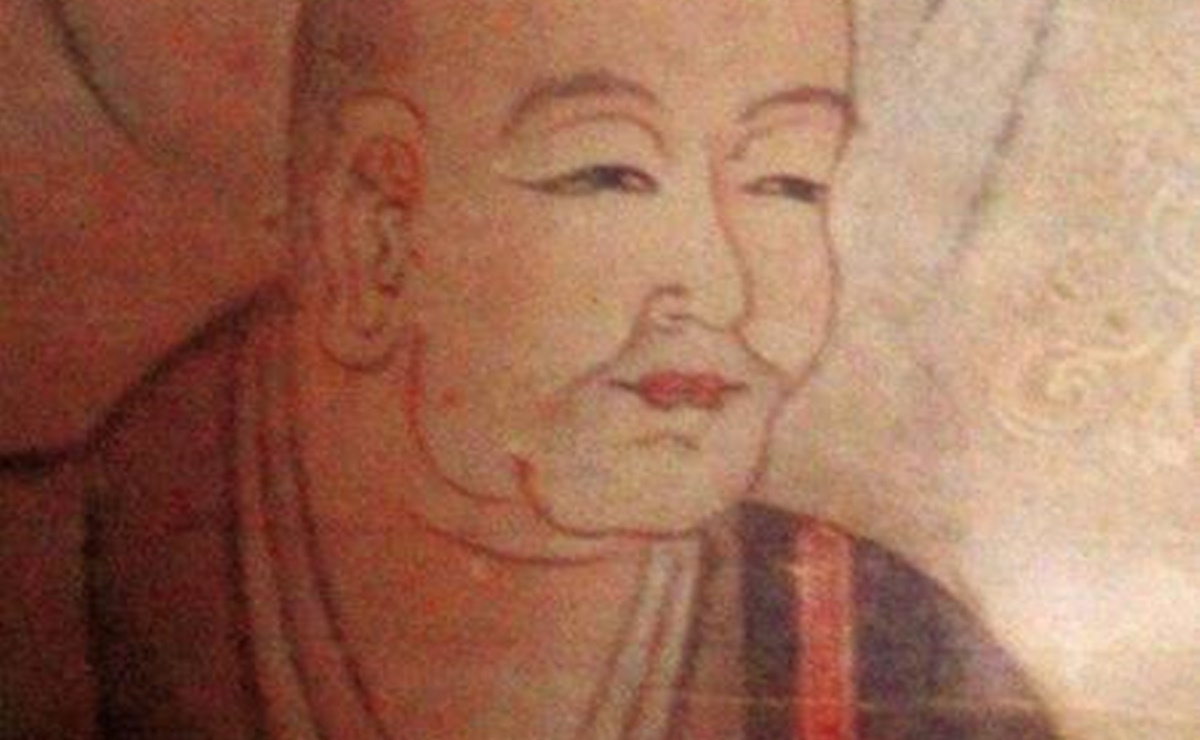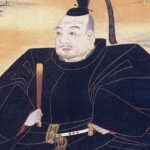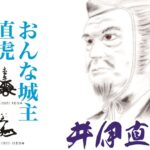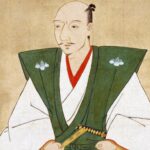こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【南渓瑞聞(南渓和尚)の生涯】
をクリックお願いします。
直親が殺され直平も急死 跡継ぎは?
支配者たる義元が亡くなっても、井伊家と南渓にとってその将来は苦闘の連続であった。
1562年12月14日に井伊直親(虎松の父)が掛川で誅殺されると、翌1563年9月18日には井伊家を支えてきた直平(南渓の父)も急死。
これにより同家の男は、幼い虎松だけとなってしまう。
本来ならば井伊直平の子である南渓が還俗して井伊家を継げばいい理屈だが、おそらく彼が養子であったため、まずは候補から外されたのであろう。
そこで、直平に後を託された南渓和尚がとった策略が、次郎法師(おとわ)を還俗させて「井伊直虎」を名乗らせ、虎松の後見人(虎松が元服するまでの宗主)とするというものであった。
尼は還俗できないが「次郎法師」という僧名の人物は還俗できる。先にも記した通りの詭弁である。
-

井伊直虎の生涯|今川家や武田家などの強国に翻弄された女城主の生き様
続きを見る
井伊“次郎法師”直虎は、地頭として9月15日に南渓和尚に黒印状を発布しているが、ここの署名は「井伊直虎」ではなく「次郎法師」だったため、彼女は還俗しないまま地頭になった――とする説もある。
一方、井伊家の勢力を完全に取り込みたい今川氏真は、井伊家・家老の小野政次にこんな提案を持ちかける。
「今川で虎松を殺害し、井伊家が滅亡したら、井伊領を小野政次に渡そう」
これまでの井伊家頭領のように、今川に反乱する可能性のない人物を宗主に据えようとしたワケだ。
-

今川氏真は愚将か名将か?仇敵だった家康や信長とその後も友好的でいられた理由
続きを見る
(松下常慶の知らせで?)この事を知った南渓は、すぐに虎松を龍潭寺へ呼び、法衣を着せ、寺に兵士が来ても「虎松は出家した」として偽った。
南渓和尚の威圧に、兵士たちもいったんは引き下がったものの、虎松が剃髪していなかったので怪しまれてしまう。
そこで南渓は、虎松に奥山六左衛門を付き添わせて、まずは柿本城
このとき、直虎、直虎の母、虎松の母(ドラマでは「しの」)の女性たちも危険な状態にあったため、直虎は出家して祐圓尼(ゆうえんに)と名乗り、母(祐椿尼・ゆうちんに)と共に龍潭寺へ入った。
-

新野千賀(祐椿尼)直虎を産んだのは敵対一族の娘だった
続きを見る
虎松の母は、徳川家臣・松下源太郎(常慶の兄)と再婚することになった。
徳川家臣の養子としてから家康の前に出す
1568年冬。三河の徳川家康が遠江へ攻め込んだ。
井伊谷城は早朝に襲われ、城兵たちは戦わずに逃亡。
城主・小野政次も洞窟に逃げ隠れ、城はもちろん井伊領も家康のものとなった。
-

直虎のライバル 小野政次が奪い取った天下 わずか34日間で終了したのはなぜか
続きを見る
徳川の遠江侵攻に対しては、他に抵抗勢力もあった。
たとえば気賀の住民は堀川城に立て篭って家康軍(井伊衆を含む)と戦い、多くの死者を出している【堀川城の戦い】。
-

家康が1000人の住民を殺した堀川城の戦い~逃げた700人は生首並べて獄門畷
続きを見る
この戦いには僧侶も参加していたことから、戦後の葬儀を執り行う僧侶の数が足りなくなり、南渓和尚が祐圓尼(井伊直虎)を連れて各地を回り、葬儀を行ったという。
季節は更に先へ進み1574年12月14日、この日は井伊直親の13回忌。父の魂を弔うため、虎松が鳳来寺から龍潭寺へやって来た。
南渓和尚と3人の女性(祐椿尼、祐圓尼、しの)は相談して、虎松を鳳来寺に帰さず、徳川家康に仕官させることに決めた。
その後、「虎松を返すべし」と鳳来寺から何度も使者が来て、色々と難題を持ち込まれるたびに南渓和尚が跳ねのけたという。
虎松は、実母の再婚相手である松下源太郎清景の養子となり、「松下虎松」が誕生、実質的に井伊家は絶えた。
その翌春のことだ。
鷹狩に行くため浜松城を出た徳川家康が松下虎松に会い、一目で気に入ると「井伊」への復姓を許し、「万千代」という名と300石を与えた。
「井伊万千代」が誕生し、井伊家は再興したのである。
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
弓や長刀に長けた弟子を直政のもとへ
南渓はその後も井伊直政の活躍を背景から支えている。
小牧・長久手の戦いで、徳川家康は直政に武田の旧臣を預け、合戦で使用する全ての装備品を赤で統一させた。
徳川最強部隊「井伊の赤備え」の誕生であり、直政が「井伊の赤鬼」と呼ばれるようになった由縁でもある。
この合戦に際し、南渓和尚は以下のように対応している。
①徳川家康に先祖累代の旗について聞かれたときには、ご紋は「『井』の字」、吹流しは「『正八幡大菩薩』の文字」と答えるようにと教えた
②軍扇に「日月松の扇」(龍潭寺蔵)を与えた
③弟子の中から、弓の名人・傑山宗俊 (龍潭寺三世)、長刀の名人・昊天宗建 (龍潭寺五世)を付けた
まるで父親か、あるいは祖父みたいなものか。
わが子、あるいは、わが孫同然の虎松初陣が気になって仕方なかったのであろう。
1585年8月6日には、直政の実母・松下ひよ(ドラマでは“しの”)が亡くなり、南渓が龍潭寺に葬った。
このとき井伊直政は上田合戦の最中で、井伊谷での葬儀に参列することが出来なかった。
その罪滅ぼしではないだろうが、直政から家康への働きかけにより、龍潭寺はかつての寺領を取り戻
直政にとって龍潭寺は、ただ単に「菩提寺だから」大切なのではなく、「大恩人・南渓が住職だから」という認識もあったと思われる。
そして天正17年(1589年)9月28日、示寂。
享年不明(80歳くらいか)。
★
井伊家35代の宗主・直亮は、南渓和尚を偲び、次の歌を詠んでいる。
君なくハ 栄へんものか すぎし世の にほひも深き 橘のはな
あわせて読みたい関連記事
-

子・孫・ひ孫の死を見届けた井伊直平~今川家に翻弄され続けた国衆の生涯に注目
続きを見る
-

今川家に誅殺された井伊直満(直政の祖父)最期の言葉は「呪い殺す」だった?
続きを見る
-

徳川四天王・直政の父「井伊直親」が今川家に狙われ 歩んだ流浪の道とは
続きを見る
-

井伊直政の生涯|武田の赤備えを継いだ井伊家の跡取り 四天王までの過酷な道のり
続きを見る
-

桶狭間の戦い|なぜ信長は勝てたのか『信長公記』の流れを振り返る
続きを見る
おまけエピソード 南渓と直政の禅問答
『井伊家伝記』に「直政公、南渓和尚え禅法を御問候事」なる段がある。
南渓と井伊直政が禅問答をしたという内容で、中身は直政からの質問で始まっている。
「武士は、『常在戦場』(常に戦場にいるつもりで、戦のことばかり考えている)で、仏法(菩提寺である龍潭寺の臨済禅)の事など考える時間がない。いったい禅法とは、どのような道理ですか?」
直政は、鳳来寺(真言宗)や浄土寺(曹洞宗)で学んだので、臨済宗の道理も参禅の方法も未知の理(ことわり)。この時とばかりに質問したのであろう。
南渓和尚はかく答えた。
「禅法は、仏教の他の宗派と変わりはない。禅の世界では『生死事大。無常迅速』(最重要課題は「生死」であるが、時は無常にも迅速に過ぎ去っていく。出典は『六祖壇経』)と心得て、昼夜を問わず、公案についてあれこれと考えていれば、自然と道理を得られるのである」
南渓は、極力専門用語を使わず、生活語で参禅の方法を丁寧に優しく教えると、「『無門関』『碧眼録』は読んでいなくても、鳳来寺でも浄土寺でも“杜甫”であれば読んだであろう」と考え、
───作麼生。夜深経戦場。寒月照白骨。
と直政へ公案を与えた。
直政の頭には、杜甫の「北征」全文が瞬時に思い浮かんだであろう。
───死して屍拾う者無し。
などとあれこれ考えた上で次のように悟る。
「武士とは、常に領民のことを考え、戦いに生き、戦いに死ぬ人間である。これが、自分に与えられた運命であり、天命である」(禅法の事を考える隙も無く合戦について考えている今の自分は正しい。自分の判断ミスで秦のように民の半数を失うことになってはならないからだ)
直政は答えた。
───説破。我もかくありたい。
南渓は、直政がこの公案を解けたと認めた。
「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」(領民のために、死を恐れずに戦う)というのは、平和な江戸時代に考えられた美学である。
戦国時代は、「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」(武士は、卑怯な方法をとってでも、生き延びることが再優先)という時代である。この南渓和尚との禅問答により、死を恐れず領民のために戦う「井伊の赤鬼」が誕生したのかもしれない。
「北征」 杜甫
(前略)
鴟鳥鳴黄桑 鴟鳥(しちょう)は黄桑(こうそう)に鳴き、
野鼠拱乱穴 野鼠(やそ)は乱穴(らんけつ)に拱(きょう)す。
夜深経戦場 夜深けて戦場を経れば、
寒月照白骨 寒月、白骨を照らす。
潼關百万師 潼關(どうかん)百万の師は、
往者散何卒 往者散ずること何ぞ卒(すみやか)なる。
遂令半秦民 遂に半秦の民をして、
殘害為异物 殘害せられて异物(いぶつ)と為らしむ。
(後略)
梟は葉が黄葉して枯れかけた桑の木で鳴き、
野鼠はあちこちの巣穴で出入りしている。
夜更けに戦場を通ると、
寒々とした月の光が白骨を照らしている。
「潼関の戦い」で百万人もいた師将が、
なぜかあっという間に敗れた。
最終的には、秦の民の半分が、
殺害されて屍となった。