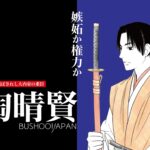こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【大内義隆の生涯】
をクリックお願いします。
跡継ぎがいなくなりゲッソリ(ヽ´ω`)
征伐の失敗は痛いことです。
合戦に参加した家臣や国人たちの不満が溜まるだけでなく、当人の精神にも影響するケースがあります。
大内義隆は、将来を期待していた晴持が水死してしまい、すっかり戦がイヤになって文芸に傾いてしまいました。
どこの家でも跡継ぎが偶発的な事故で当主より先に亡くなると、だいたい激変しますよね……。
例えば仙石秀久の采配ミスで長男・長宗我部信親を失い、すっかり落ち込んでしまった長宗我部元親などが有名です。

長宗我部元親/wikipediaより引用
晴持は、土佐一条氏から大内氏に来た人で、見目麗しく文武両道、蹴鞠や管弦も得意で利発という、まさに義隆が好むタイプでした。
なんせ義隆は、晴持の死後、幕府に願い出て「義」の字を賜り、「義房」という名前を贈っているほどです。
義隆がどれほど晴持に期待し、父として愛していたかがうかがえますね……。
「義」の字は大内氏の通字のようにも見えますが、元々は義隆の父・義興が将軍家からもらったものだったので、義隆もそれに倣おうとしたのでしょう。こういうのはトラブルになりやすいですから。
当主がこんな感じで落胆モードであれば、当然、家臣たちにも動揺は広がります。
この頃の大内氏内では、いわゆる武断派と文治派の対立が極まっていました。
義隆は基本的には文治派で、その中核となっていたのは義隆の寵臣・相良武任(さがらたけとう)です。
これに対し、武断派の中心は陶隆房(後の陶晴賢・すえはるかた/以降はこちらで統一)です。
家中の文官・武官の対立が湧き上がり……
実は陶晴賢は、若いころ義隆の衆道の相手でもありました。
この頃はいい年なのでそういう関係ではなかったと思われますが、感情だけは残っていたと思われます。
まぁ「恋愛と友情は紙一重」「恋の火は、時として友情の灰を残す」なんてことも言われますし……主従間における忠誠心も、似たようなものなのかもしれません。
-

なぜ戦国時代の大内家重臣・陶晴賢は下剋上を起こし最終的に毛利に滅ぼされたのか
続きを見る
また、武任の娘は美女だったと伝わっているので、父親も見た目はいいほうだったのではないでしょうか。
武任のほうが陶晴賢よりも二回り近く年上なので、現代風にいうなら「ナイスミドル」とか「ロマンスグレー」みたいな、いい感じのおじさまだったのかもしれません。
そんなこんなで、陶晴賢の中では武任に対して
「日頃からお前のことは気に食わなかったんだよ!」
みたいな感情がじりじりと燃え上がっていきます。
ついでにいうと、武任は陶晴賢が自分を嫌っていることに気付いていたようで、自分の娘を陶晴賢の息子に嫁がせて懐柔しようとしたことがありました……が、完全拒否されてしまいます。
陶晴賢は優秀な武将だと思うのですが、これではあまりに大人げないですよね。
ただし、この時点ではそこまで致命的な状況には至っていません。
毛利氏が東側を固め、九州からは肥前の龍造寺氏が「仲良くしましょう」(超訳)と言ってきたこともあり、大内氏の領地自体は拡大していました。
京風文化の華開き、位階も上級貴族並に高く
領地の大きさだけではありません。
大内氏の勢力下では、貿易によってもたらされた富と、大内義隆自身が学問・芸術を好む質だったため、山口を中心に京風の文化が強まっていました。
仏教についても、武士の多くが好んだ禅宗だけではなく、より歴史の長い天台宗や真言宗の僧侶を招いたりしています。
他にも、儒学や神道、雅楽、有職故実も自ら学んでおり、それらを教える公卿らの下向も歓迎、知行を与えたり経費をかけて厚遇しています。
そのおかげか、義隆の官位もガンガン上がり、天文十七年(1548年)には従二位にまで上っていました。
従二位は、位階ランキングで上位四番目であり、親王や内親王であれば【二品の宮】と呼ばれるほどの高さです。
【位階ランキング】
①正一位 ← 最上位
②従一位
③正二位
④従二位 ← ココ
つまり、義隆は戦国大名でありながら、天皇の子女と同格になったということです。
これは将軍以外では前例がないほどのことでした。
また、義隆は日明貿易を重視したこともあり、外国文化への理解もあるほうでした。
信仰こそしなかったものの、山口を訪れた宣教師フランシスコ・ザビエルに領内での布教を許しています。

フランシスコ・ザビエル/Wikipediaより引用
当時の大内氏の領地が日本のおおよそ1/10あたることを考えると、かなり多くの国民がキリシタンになってしまう可能性もあり、地味に危ないことでした。
実際には、その後の宣教師たちが
「日本人に説教しても、質問し返してくるからなかなか布教が進まない」
というような話を書き残しているので、そう簡単にはいかないんでしょうけど。
※続きは【次のページへ】をclick!