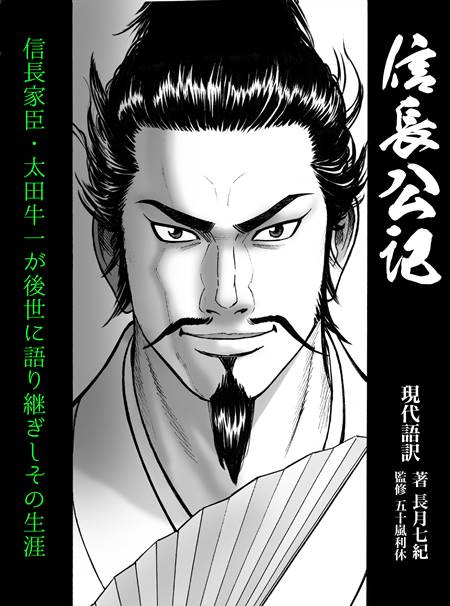斎藤氏(当主は斎藤龍興)の支配する美濃へ攻め込むため、清州城から小牧山城へと引っ越した織田信長。
その効果はすぐさま現れ、丹羽長秀が犬山城の攻略に成功します(前回43話)。
しかし、美濃の本拠地・稲葉山城(後に岐阜城)までは、まだ距離があります。
さらなるプレッシャーをかける織田信長たち。
今回は、本格的な美濃攻めの前に起きた、支城攻略のお話です。
加治田城の佐藤紀伊守と嫡男・右近右衛門
犬山城を労せずして手に入れた織田方。
すぐさま攻め込めるワケではなく、木曽川を挟んだ向かい側に、宇留摩城(うるまじょう)と猿啄城(さるばみじょう)という二つの城が立ちはだかっておりました。
どちらも斎藤氏の城なので、美濃から見ると対織田氏の最前線といえるでしょう。
宇留摩城と書かれているのは信長公記などの史料上のみで、現代の地図では「鵜沼城(うぬまじょう)」と表記されています。
この二つの城から、さらに20kmほど北方の山側へ離れたところに、加治田城という別の斎藤方の城があり、城主の佐藤紀伊守と、嫡男の右近右衛門という父子が守っていました。
※赤色(左から岐阜城・宇留摩城=鵜沼城・猿啄城)
※黄色(左下から清州城・小牧山城・犬山城)
※紫色(加治田城)
彼ら美濃佐藤氏は、藤原秀郷の末裔とされる一族です。
藤原秀郷は平将門を討ち取った平安時代中期の武将。
「俵藤太(たわらのとうた)」という呼び名も有名ですね。
戦国時代当時でも、秀郷の時代からは600年近く経っているので、紀伊守父子が本当に秀郷の血を引いていたかどうかはわかりません。
しかし、少なくとも武門の誇りは持っていたでしょう。
味方につくか徹底して対抗するか 二つに一つ
佐藤氏のような歴史と誇りを持つ家の場合、信長のような新興勢力への対応は、大きく分けて二つです。
「どこの馬の骨ともわからん奴が偉そうに!」と徹底的に対抗するか。
あるいは「これはただ者ではない、家を残すためには従うほうがいい」と、自ら従属を選ぶか。
信長関連でいえば、前者は越前の朝倉氏が代表的でしょうか。
あまりにも戦のイメージが多いので目立ちませんが、実は後者を選んだ家もいくつかあります。このときの紀伊守父子もそうでした。
彼らは岸良沢(きし りょうたく)という者を使者に立て、丹羽長秀の下へ送ります。
「これからは信長公にお味方します」
ちょうど信長も犬山衆の件が片付き、美濃に足がかりが欲しい考えていたタイミング。そのため、長秀からこのことを聞くと大いに喜びました。
良沢を帰すときには「これで兵糧を蓄えておくように」と、黄金五十枚という大金を渡しています。
黄金五十枚はどの程度の価値か?
この”黄金五十枚”がいくらぐらいの価値だったのか。気になる方も多いでしょう。
まだ貨幣の統一がされていない時代です。
「このとき信長が渡した金額が、現代の貨幣価値でどのくらいだったのか?」と断言するのはなかなか難しいところがあります。
ここでは、加治田城や美濃佐藤氏の規模から、おおまかに目安をつけてみましょう。
別途取り上げますが、加治田城は後日、織田氏と斎藤氏の戦の舞台になります。
そのときの城方の兵力が、おおよそ1,000~1,200程度と推測されています。
この兵数を養えるだけの兵糧を用意できそうな金額=黄金五十枚という仮定にして、計算の便宜上1000人で計算しましょう。
信長はおそらく、
「斎藤龍興は、加治田城が寝返ったと知れば攻め込むに違いない。場合によっては籠城戦もありうる」
と考えていたでしょうから、念を入れて一ヶ月程度の兵糧が必要と見ていた……と、これも仮定で話を進めます。
すると【1000人で一ヶ月に消費する米を買える金額=黄金五十枚】となりますね。
「お金で城一つを買える」なら安いもん
次に、領国の広さを表す「石(こく)」でさらに細かく見てみましょう。
一石=「大人一人が約一年間に消費する米の量」となります。
この目安だと、一日あたり三合で計算しますので、実際には少々ズレますが……。
1000人×一年分の米=千石。一ヶ月なら1/12になりますから、約83.3石=黄金五十枚という計算になります。
約83.3石がどのくらいかというと、これまたわかりやすい表現をするのが難しいのですが。
貨幣価値の差を無視すると、江戸時代の御家人(将軍に直接仕える身分が低めの武士)の収入の1/3くらいです。
これらの仮定と当時の信長の立場を踏まえて、現代に置き換えるとすれば、こんな感じでしょうか。
「一地方の新興企業の社長が、隣接地域の同業他社から人材を引き抜くために、中堅社員の給料の1/3程度にあたる金額を出した」
いぶ乱暴でわかりにくい話ですが、当時の信長としてはそこそこの出費だった、と考えていいかと。
しかし、戦で人を死なせず「お金で城一つを買える」と考えれば、かなり安いでしょう。
いざ城攻めとなれば、お金に加えて物資や人命の損失もバカになりません。
”信長の買い物上手な一面”といえるかもしれません。
あわせて読みたい関連記事
-

斎藤龍興の生涯|美濃を追われ信長へ執拗に反撃を繰り返した道三の孫
続きを見る
-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請
続きを見る
-

稲葉山城の戦い|信長の“美濃攻略” 実は信玄に気遣いながらの大戦略だった
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

天下統一より過酷だった信長の尾張支配|14年に及ぶ苦難の道を年表で振り返る
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)
書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)
出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)
書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)
出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)
出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ