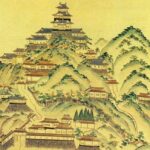こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【斎藤龍興の生涯】
をクリックお願いします。
半兵衛に稲葉山城を乗っ取られ!
永禄四年(1561年)、織田家との間に【森辺の戦い】が勃発。
このときは斎藤方が勝利をおさめるも、複数名の重臣を失っています。
また、翌永禄五年(1562年)にも、越前方面の守備をしていた郡上八幡城主・遠藤盛数が亡くなり、まさにジリジリと龍興は追い詰められていきます。
それでも竹中半兵衛らの活躍もあり、永禄六年(1563年)の【新加納の戦い】では勝利を収めました。しかし……。
翌永禄七年(1564年)には、かの有名な稲葉山城乗っ取り事件が起きています。
「竹中半兵衛が主君を諌めるため、わざと少人数で稲葉山城を奪い、反省を促した」という話です。

竹中半兵衛/wikipediaより引用
このとき美濃三人衆の一人であり、半兵衛の舅でもある安藤守就が、先の評判悪い斎藤飛騨守を殺害したとも。
城を乗っ取られた龍興は一目散に逃げ出しましたが、半兵衛と守就はすぐに稲葉山城を返したため、大名としてはまだ滅びていませんでした。
命がけの忠告をしてくれた半兵衛に対し、龍興は表面上の反省ばかり。
そもそもこんな事件が起きる時点で、先は決まったようなもので、自ら滅びていったも同然です。
なお、この乗っ取り事件はあまりにも出来すぎた話ゆえ、真偽の程は不明ながら、国内が乱れていたことに間違いはないでしょう。
事件の詳細については、以下の記事をご覧いただければと存じます。
-

稲葉山城乗っ取り事件|半兵衛がわずかな手勢で成功させた 真偽怪しい伝説の中身
続きを見る
櫛の歯が欠けるように配下の武将が織田家に降り……
こうして徐々に体制が揺らいでいく龍興率いる斎藤一族。
永禄八年(1565年)、織田信長がついに本格的な美濃攻略を始めます。
ここに至るまでの経緯が経緯ですから、斎藤氏の家臣の中には、龍興を見限って織田氏につく人が日に日に増えておりました。
例えば加治田城の佐藤親子や、安藤守就を含めた美濃三人衆(他の二人は稲葉一鉄・氏家卜全)などです。
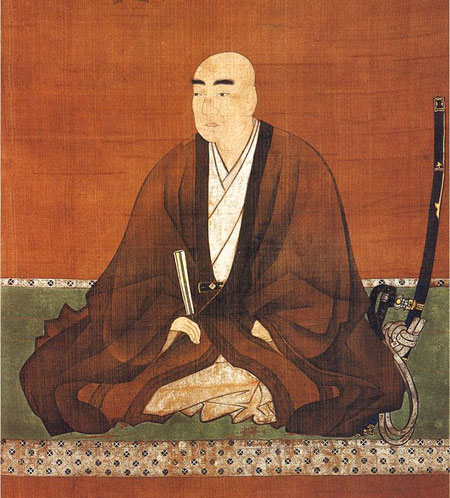
西美濃三人衆の一人・稲葉一鉄(稲葉良通)/wikipediaより引用
永禄十年(1567年)にはついに本拠・稲葉山城まで攻め込まれ、龍興の命も……と思われました。
しかし、なぜか信長は命までは奪いません。
こういう場合、攻め込まれた大名は降伏して攻め手に仕えるか、首を取られるか、出家するかのいずれかです。
龍興は、そのどれでもありませんでした。
一度、伊勢の長島本願寺に行っていますので、当初は出家する予定だったのかもしれません。
しかし、今度は摂津に行ったり、三好三人衆や一向一揆衆とコンタクトを取って、密かに反信長の同志と連携しようとしたり、事ここに及んで渋とさを見せ始めるのです。
本圀寺の変(六条合戦)
永禄十二年(1569年)1月には三好三人衆と共に、上洛と将軍就任を済ませた足利義昭に襲いかかってます。

足利義昭/wikipediaより引用
【本圀寺の変】とか【六条合戦】と呼ばれる事件ですね。
このとき、信長は京都を留守にしていて、京都のことは明智光秀らに任せていたため、その隙を狙ったと思われます。
そして、これ以降、信長に対する攻撃を積極的に行っていくのです。
まず翌元亀元年(1570年)8月、三好三人衆の対信長籠城戦【野田城・福島城の戦い】を支援。
石山本願寺法主・顕如などと共に働いたとされます。

顕如上人/wikipediaより引用
この戦は、織田信長vs石山本願寺戦の初戦とも呼べるものであり、それから約10年にも及ぶ激しいものでした。
そこに龍興が関与していたというのは、なかなか因果を感じる話ですし、織田家の西国進出を遅らせるという大きな出来事でもありました。
それだけに不思議に感じます。
なぜこういった謀略を、美濃の国主だった頃に発揮できなかったのか?
※続きは【次のページへ】をclick!