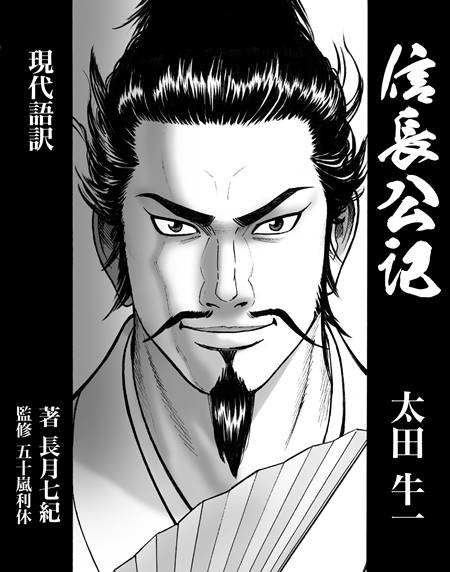天正三年(1575年)秋の上洛は、織田信長にとって非常に大切な用事がありました。
実は10月初めから官位昇進のため宮中に儀式場(陣座)を作っていたのです。
なぜ、そんなものを作ったのか?
というと【右近衛大将】という官職に就くためです。
かつては源頼朝や足利義満ら各時代の将軍が就任したことでも知られ、武家政権にとっては非常に重要なポジションですが、そもそも信長はこうした「官位など眼中ナシ!」というイメージもあります。
実際のところ、信長は官位に無頓着だったのか。
それとも何かメリットがあったのか?
右近衛大将の就任と共に、信長の官位への取り組み方を見てみましょう。
なお「官位」の意味や理屈がイマイチわかっていない……という方は
・官職(おしごと)
・位階(ランキング)
とお考えください。
頭の文字をタテ読みすると「官位」になりますよね。
要は「官職」と「位階」を組み合わせた言葉になるのですが、説明し始めると止まらなくなりますので、これより詳しくは以下の記事をご覧ください。
-

モヤッとする位階と官位の仕組み 正一位とか従四位にはどんな意味がある?
続きを見る
-

官職と二官八省を知れば『光る君へ』も戦国作品も楽しくなる!基礎知識まとめ
続きを見る
-

関白・検非違使・中納言など「令外官」を知れば日本史全体の解像度が上がる
続きを見る
日本史には欠かせない要素ですので、知っておくと楽しくなりますよ。
では本編へ。
まずは権大納言に就き右近衛大将を兼任
天正三年(1575年)11月4日。
かねてから上洛していた信長は清涼殿に参上し、まず従三位権大納言に就きました(右近衛大将については後述)。
信長はこの時点まで無位無官だったと考えられていますので、初めて公卿の仲間入りをしたことになります。
その前の天正二年に「形式上の官位を得ていた可能性がある」という指摘もありますが、実質上は今回が初と思われます。
では、大納言とはどういう職か?
「左大臣・右大臣に次ぐ天皇の側近」という要職ですね。
大臣になれる公家は摂関家や清華家に限定されておりましたが、大納言はそれ以外の家の者でも就くことができるという特徴があります。
信長の出自やこれまでの朝廷への働き、他の公家への体面などを加味すると、妥当というところでしょう。
11月7日にはこの就任の御礼を述べるため、改めて宮中に参内しました。
そこで信長は三条西実枝を通して正親町天皇に御礼を申し上げ、天皇からは盃を頂戴したようです。
-

過酷な戦国時代を生き抜いた正親町天皇~信長や秀吉とはどんな関係を築いた?
続きを見る
そしてこの日、信長は右近衛大将も兼任することになりました。
では、近衛大将とは?
武家の棟梁として認められた?
近衛大将は、宮中の警護を司る「近衛府」という役所の長官を指します。
近衛府自体が左右の二つに分かれていたため、それぞれの長官を
「左近衛大将」
「右近衛大将」
と呼びます。
基本的には、摂関家や皇族に連なる家の人が任じられる“名誉職”でしたが、平安末期に平重盛(平重盛の子)が就任し、鎌倉時代以降は将軍が任じられることも増えました。
源頼朝の他に足利将軍では
・足利義満
・足利義持
・足利義教
・足利義政
・足利義尚
・足利義晴
が右近衛大将に就任しております。
「幕府」という言葉自体、近衛大将の唐名(中国の官職名)に相当にしますので、整合性もあるんですね。
戦国武将にとって当時の官職は“カタチだけ”でしたが、源頼朝以来、武家の棟梁という意味合いもあり、一方で少し穿って見ますと、
「これからは守護者になってな、よろしく頼むぞ」
という朝廷からの意思表示にも取れたりします。
早い話、お金と武力を援助してくださいね、ということです。
信長の父・織田信秀も朝廷への保護策に取り組んでおり、従五位下備後守という官位を得ています。
-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名
続きを見る
信長も、そうした父の姿を見て、参考にしていたでしょう。
謙信では務まらない? 京都の守り
実際のところ信長は、朝廷に対し相応の貢献をしてきました。
永禄十一年(1568年)に足利義昭を奉じて上洛してから、皇居の修繕や公家領への徳政令など、他の大名や武将と比べてかなりのものです。
-

紫宸殿や清涼殿などの内裏を修繕|信長公記第80話
続きを見る
-

信長の徳政令で皇室だけでなく公家も救おう|信長公記第119話
続きを見る
義昭との対立で京都を戦場にしたこともありますが、トータルで考えれば、朝廷の人々が信長を「最も頼れる存在」と判断してもおかしくはないでしょう。
他には上杉謙信なども朝廷から好意的に見られていたと思われながら、地元や道中の問題が山積みすぎて、頻繁に上洛することはできていません。
謙信の人柄や行動を信頼できたとしても、京都を実効支配できないのでは不安が残ります。
その点、信長は地理的にもラッキーでした。というのも……。
※続きは【次のページへ】をclick!