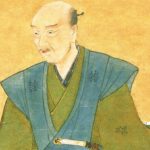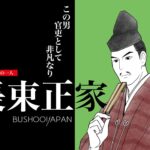こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【戦国廃城紀行】
をクリックお願いします。
城は変化する、そして人の意識も
本書は初版から十年を経て、文庫化されました。
その間の変化が、追記されています。
自治体による調査が始まったこと。
訪問者が増えて、案内板が増えたこと。
市民講座があること。
城主がゆるキャラになったこと。
例えば小西行長をモデルとした
◆うとん行長しゃん(→link)
なんかもその一人。
戦国ファンからしてみれば「どうせひこにゃんあたりの二番煎じだろ……」と受け流しそうになる場面です。
ところが本書を読んだあとですと、これがだいぶ変わってくる。印象が違ってきます。
小西行長がキリシタンであることから、どれだけ悲運の目にあったか。
銅像すら破壊されそうになったかを考えると、感慨深いものがあるのです。
同時に、小西行長の宇土城の章からは【人の意識はそうそう変わるものではない】ということを痛感させられました。

宇土城石垣
キリスト教の禁止から時代がくだっても、銅像建立の際には脅迫事件があったほど。ぞっとするような思いすらあります。
敗者というだけではなく、宗教ゆえに憎まれてきた小西行長。
その憎悪のなまなましさには、本当に驚かされます。
幻のようであったそんな行長が、ゆるキャラになって愛嬌を振りまくーーこれはなかなかすごいことではないかと感じてしまうのです。
戦国大河のお供にも
本書は『どうする家康』の予習にもぴったり、かつ『麒麟がくる』や『真田丸』の復習にも最適。
石田三成や大谷吉継、豊臣秀次といった人物も扱われています。
『真田丸』は最新の学説を積極的に取り入れており、中でも秀次の死は印象深い描写でした。
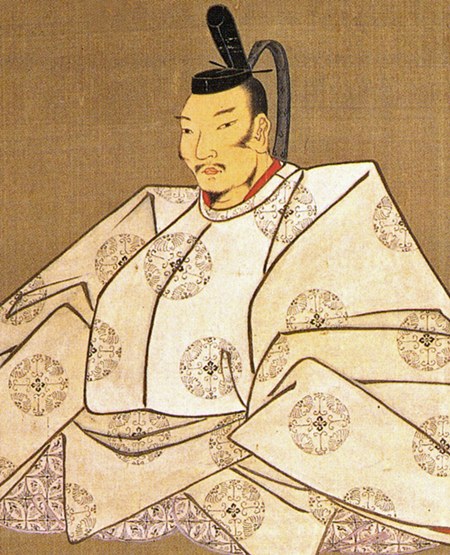
豊臣秀次/wikipediaより引用
あの描写をふまえてから本書を読むと、秀次像がより身近に迫ってきます。ドラマでは、人は良いのだけれども武将としての器量はそこまででもない、そんな好青年像が窺えたものです。
彼の残した城からも、その像と近い青年が浮かび上がってくることが、本書からはわかるのです。
最新の学説や研究成果、発掘からわかってきた史実をふまえつつ、フィクションにも寄り添うような本書は、まさしく戦国大河のお供に最適な一冊。
たしかに文庫だけあって、写真は全て白黒、かつ小さいし、実用的なお城ガイドならば、他にオススメできるものはあります。
※スマホですぐ読めるKindle版がオススメ(→link)
しかし本書は、上記のようなカラー図版入りかつ実践的なものとはまた違った魅力があるのです。
敗者の城をたどることで、見えてくる歴史の陰影。
そんな陰影を引き立てる、味わいのある名文と筆者の観察眼。
城に到達するまでの、一筋縄ではいかない道のり。
変わりゆく人々の歴史意識や、城をめぐる状況。
2026年大河ドラマ『豊臣兄弟』の前に、一冊、ゆるりと味わってみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい関連記事
-

明智光秀の生涯|ドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多き一生を振り返る
続きを見る
-

石田三成の生涯|秀吉と豊臣政権を支えた五奉行の頭脳 その再評価とは?
続きを見る
-

長束正家の生涯|家康も警戒した豊臣五奉行の一人 なぜ最期は切腹へ?
続きを見る
-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた
続きを見る
-

松永久秀の生涯|三好や信長の下で出世を果たした智将は梟雄にあらず
続きを見る
著者の澤宮優氏(@twitter)からのツイートもいただきました^^
すばらしい書評をいただき、とても感謝しております。https://t.co/qhLR8QatLe
— 澤宮優 (@hat71520) July 11, 2019
【参考】
戦国廃城紀行: 敗者の城を探る (河出文庫)
→Amazon Kindle版(→link)
→Amazon 文庫版(→link)