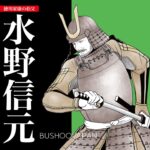こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【家康の三河平定】
をクリックお願いします。
三河忩劇を抑えた家康
織田と手を結び、一向宗とも和睦した家康は、さらなる地固めのため朝廷勢力を頼りました。
摂関家の近衛前久を頼り、工作を開始するのです。
こうした工作は、本来なら足利将軍に願い出ることが通例です。
『麒麟がくる』での織田信長は、助けを求めても満足な結果を得られない13代将軍・足利義輝に失望していました。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用
信長としては、ビシッと紛争を収めると期待していたのに無駄だった……ということがわかる描写です。
しかし、家康は足利義輝を頼ることはできませんでした。
なぜなら、その時には既に【永禄の変】で奮戦の末に殺害されていたからです。
そこで家康は、何かと話が通じる近衛前久に頼み込んだという流れになります。
『どうする家康』では、朝廷工作のシーンで出てくる公卿がいかにもアホな磨呂貴族でしたので、『麒麟がくる』の近衛前久を思い描いた方が現実に近しいのではないでしょうか。
家康はこのとき何を頼んだのか。
・徳川への改姓→このときは近衛前久を通じてのものであり、実は氏姓は「藤原姓」
・叙位および任官→従五位下三河守
永禄3年(1560年)桶狭間の戦いから6年後の永禄9年(1566年)。
三河の戦国大名・徳川氏は、こうして誕生したのでした。
そして上洛へ
『どうする家康』では、ウキウキワクワク、まるで修学旅行のように上洛していた徳川家康。
しかし前述の通り、当時は将軍・足利義輝が横死するという混乱が生じており、とても旅行気分で気軽に上洛できる状況でもありません。
後継ぎ未確定のまま死した将軍職を誰が継ぐのか――。
出家していた義輝の弟(足利義昭)を還俗させ、上洛させるまでにも様々な駆け引きがありました。

足利義昭/wikipediaより引用
『どうする家康』では二日酔いの様子でゲップをしながら現れ、俗物の極みといった醜態を晒していた足利義昭(古田新太さん)。
とても見ていられないあの人物像は、室町幕府最後の将軍=愚者という結果から逆算した結果だったのでしょう。
実際の義昭は、不安定な政情のもと、そこまで愚昧な人物が担ぎ上げられない、として再評価が進んでいます。
要は、あんなバカっぽい人物ではないということです。
『麒麟がくる』は、1991年の大河ドラマ『太平記』で室町幕府の始まりを描いた池端俊策さんの作品です。
彼は当初「今度は室町幕府の終焉を描きたい」と考え、義輝と義昭兄弟を主役にする案を練っていたといいます。
結果的に主人公は明智光秀となりましたが、それでも当初の構想を活かしたのでしょう。室町幕府の将軍と家臣が大きく扱われました。
明智光秀が本能寺へ向かう動機のひとつにも、織田信長から足利義昭の殺害を命じられたことも影響しています。
要するに、この辺りは『麒麟がくる』の方が丁寧に描かれておりますので、まだ未見の方は、VOD等でご覧になられることをオススメします。
大河ドラマの風格。
最新研究の取り込み。
そうした魅力を味わい、歴史を深く味わうキッカケになるでしょう。
誠実で生真面目な人間が、なぜ、謀反人としての命運を歩まねばならないのか――現代人の心に響く誠実な歴史劇が、そこにはあります。
あわせて読みたい関連記事
-

今川義元の生涯|“海道一の弓取り”と呼ばれる名門武士の実力とは?
続きを見る
-

今川氏真は愚将か名将か?仇敵だった家康や信長とその後も友好的でいられた理由
続きを見る
-

家康に捨てられた瀬名が氏真に「遊女」扱いされるなどあり得るのか?
続きを見る
-

水野信元の生涯|織田徳川の同盟に欠かせなかった家康伯父は突如切腹を命じられ
続きを見る
-

早川殿の生涯|武田・徳川・北条に翻弄され今川氏真と共に歩んだ流転の生活
続きを見る
【参考文献】
柴裕之『徳川家康: 境界の領主から天下人へ』(→amazon)
黒田基樹『家康の正妻築山殿』(→amazon)
黒田基樹『お市の方の生涯 「天下一の美人」と娘たちの知られざる政治権力の実像』(→amazon)
二木 謙一『徳川家康 (ちくま新書)』(→amazon)
他